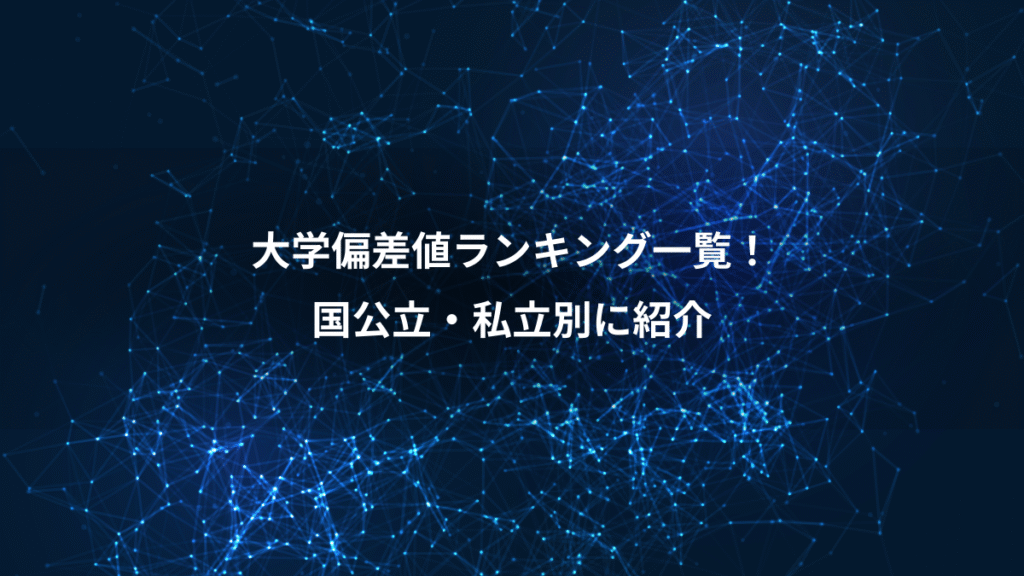大学受験を控える皆さんにとって、「偏差値」は志望校選びの重要な指標の一つです。自分の現在の学力レベルを客観的に把握し、どの大学・学部が合格圏内にあるのかを判断するために、偏差値ランキングは欠かせない情報源といえるでしょう。
しかし、インターネットや雑誌には様々な偏差値情報が溢れており、「どのランキングを信じれば良いのか分からない」「偏差値だけで大学を選んで後悔しないか不安」といった悩みを抱えている受験生や保護者の方も少なくありません。
この記事では、大学受験における偏差値の基本的な知識から、最新の偏差値に基づいた国公立・私立別、学部系統別、エリア別の大学ランキングを網羅的に紹介します。さらに、偏差値という数字だけに囚われず、自分に合った大学を見つけるための後悔しない大学選びのポイントまで、詳しく解説していきます。
この記事を読めば、偏差値についての正しい理解が深まり、膨大な情報の中から自分にとって本当に価値のある大学を見つけ出すための羅針盤を得られるはずです。それでは、大学受験という大きな挑戦に向けて、まずは偏差値の基礎から見ていきましょう。
目次
大学受験における偏差値の基礎知識
大学受験の世界で当たり前のように使われる「偏差値」という言葉。しかし、その意味を正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。ここでは、偏差値がそもそも何を示す数値なのか、そしてその数値をどのように解釈し、活用すべきなのか、基礎から徹底的に解説します。偏差値を正しく理解することは、効果的な学習計画を立て、適切な志望校を選ぶための第一歩です。
偏差値とは
偏差値とは、ある集団の中で、特定の個人の成績がどのくらいの位置にあるかを示す統計上の数値です。テストの点数のように単純な成績評価ではなく、集団全体の成績分布における相対的なポジションを客観的に表すために用いられます。
具体的には、集団の平均点を偏差値50とし、そこからどれだけ上または下に位置するかを示します。一般的な模試では、偏差値は通常25から75の範囲に収まることが多く、偏差値が高いほど、その集団内での学力が上位であることを意味します。
なぜ、素点の点数ではなく偏差値が重要なのでしょうか。それは、テストの難易度が毎回異なるためです。例えば、非常に簡単なテストで90点を取ったとしても、平均点が95点であれば、その人の学力は集団の中で平均以下ということになります。逆に、非常に難しいテストで60点しか取れなくても、平均点が40点であれば、その人は集団の中でかなり上位に位置することになります。このように、テストの難易度に左右されずに、自分の学力が受験者全体の中でどのレベルにあるのかを客観的に比較できる点が、偏差値を用いる最大のメリットです。
偏差値は、以下の計算式で求められます。
偏差値 = (個人の得点 – 平均点) ÷ 標準偏差 × 10 + 50
ここで重要な役割を果たすのが「標準偏差」です。標準偏差とは、集団全体の点数のばらつき具合を示す数値です。標準偏差が大きいほど点数のばらつきが大きく(高得点者と低得点者の差が激しい)、小さいほどばらつきが小さい(多くの人が平均点周辺に集まっている)ことを意味します。この標準偏差を計算に用いることで、より精密に集団内での位置を把握できるのです。
例えば、同じ「平均点より10点上」という結果でも、受験者の点数が平均点周辺に密集しているテスト(標準偏差が小さい)で取る10点と、点数が広範囲にばらついているテスト(標準偏差が大きい)で取る10点とでは、その価値が全く異なります。前者の場合、わずかな点差が大きな順位の差につながるため、偏差値は高く算出されます。
このように、偏差値は単なる点数ではなく、「平均点」と「点数のばらつき(標準偏差)」という2つの要素を考慮して算出される、非常に合理的な指標なのです。
偏差値を見るときの注意点
非常に便利な指標である偏差値ですが、その数値を鵜呑みにするのは危険です。偏差値を利用する際には、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。これらの注意点を押さえることで、情報をより正確に解釈し、誤った判断を避けることができます。
予備校や模試によって数値は異なる
大学の偏差値ランキングを調べると、発表している予備校や模試によって数値が異なっていることに気づくはずです。例えば、河合塾の「全統模試」と駿台予備学校の「駿台全国模試」では、同じ大学・学部でも偏差値が異なる場合があります。
なぜこのような違いが生まれるのかというと、模試を受ける受験者層が異なるからです。一般的に、難関大学を目指す受験生が多く受ける模試では、全体の学力レベルが高いため、同じ学力でも偏差値は低く出る傾向があります。逆に、幅広い学力層の受験生が受ける模試では、偏差値は高く出やすくなります。
| 模試の名称(例) | 主な受験者層の傾向 | 偏差値の傾向 |
|---|---|---|
| 河合塾「全統模試」 | 全国最大規模。浪人生も多く、幅広い学力層が受験。 | 標準的な数値が出やすい。多くの受験生にとって基準となる。 |
| 駿台「駿台全国模試」 | 難関国公立大学や医学部志望者など、学力上位層が多く受験。 | 全体的に偏差値が低めに出る傾向がある。ハイレベルな集団での立ち位置が分かる。 |
| 東進「共通テスト本番レベル模試」 | 現役生が中心。受験者数が多く、共通テスト対策に特化。 | 模試の難易度や受験者層により変動するが、河合塾に近い傾向。 |
(上記は一般的な傾向であり、実際の模試ごとに異なります)
参照:河合塾 Kei-Net、駿台予備学校 I-SUM Club、東進ドットコム
では、どの予備校の偏差値を信じれば良いのでしょうか。最も重要なのは、自分が継続的に受験している模試の偏差値を基準にすることです。同じ模試を受け続けることで、集団内での自分の学力の推移を正確に追跡できます。その上で、他の予備校が発表している偏差値も参考にし、多角的な視点から志望校の難易度を把握することが賢明です。一つの数値に一喜一憂せず、複数の情報を総合的に判断する姿勢が求められます。
同じ大学でも学部や入試方式で違う
大学の偏差値を調べる際、「〇〇大学 偏差値55~65」のような幅のある表記をよく見かけます。これは、同じ大学内でも学部・学科や入試方式によって難易度が大きく異なるためです。
まず、学部・学科による違いです。一般的に、その大学の看板学部や人気の高い学部(例:早稲田大学の政治経済学部、慶應義塾大学の経済学部など)は偏差値が高くなる傾向があります。また、理系の学部は文系に比べて偏差値が低く見えることがありますが、これは入試に必要な科目数が多く、単純比較ができないため注意が必要です。新設された学部は、初年度の偏差値が読みにくく、2年目以降に大きく変動することもあります。
次に、入試方式による違いです。同じ学部であっても、以下のように入試方式が異なれば、求められる偏差値も変わってきます。
- 一般選抜(個別日程): 大学が独自に実施する試験。最もオーソドックスな入試方式で、多くの偏差値ランキングの基準となっています。
- 共通テスト利用入試: 共通テストの成績のみ、あるいは共通テストと大学独自の二次試験の成績を組み合わせて合否を判定する方式。一般的に、募集人数が少なく、国公立大学との併願者が多く出願するため、個別日程よりも偏差値(ボーダーライン)が高く出る傾向があります。
- 全学部日程: 全ての学部が同じ日に同じ問題で試験を行う方式。一度の受験で複数の学部に出願できるメリットがありますが、その分志願者が集まりやすく、難易度が上がることもあります。
したがって、「〇〇大学に行きたい」と漠然と考えるのではなく、「〇〇大学の△△学部の□□方式で合格したい」というように、具体的な学部・学科、入試方式まで落とし込んで偏差値を確認する必要があります。
偏差値は合格の可能性を示す目安
最も重要な注意点は、偏差値はあくまで合格の可能性を示す「目安」であり、絶対的な合格指標ではないということです。予備校が発表する偏差値の多くは、「ボーダーライン偏差値」または「合格者平均偏差値」です。
- ボーダーライン偏差値: その偏差値を取った受験生の合格可能性が50%(あるいは60%など、予備校の基準による)となるライン。つまり、この偏差値に達していても、半数は不合格になる可能性があることを示しています。
- 合格者平均偏差値: その大学・学部に合格した受験生の模試偏差値の平均値。当然、この平均値よりも低い偏差値で合格している人もいれば、高い偏差値で不合格になっている人もいます。
模試の判定(A判定~E判定)も同様です。A判定(合格可能性80%以上)であっても不合格になることはありますし、逆にE判定(合格可能性20%未満)からでも逆転合格を果たす受験生は毎年存在します。
なぜなら、実際の入試は模試とは異なり、一発勝負だからです。以下の要素が合否に大きく影響します。
- 過去問との相性: 自分の得意な形式の問題が多く出題されるか。
- 当日のコンディション: 体調や精神状態が実力発揮を左右する。
- 倍率: その年の志願者数によって競争の激しさが変わる。
- 問題の難化・易化: その年の問題が例年より難しくなるか、簡単になるか。
結論として、偏差値は志望校選びや学習計画の策定において非常に有効なツールですが、それに一喜一憂しすぎるべきではありません。自分の現在の立ち位置を確認するための客観的なデータとして冷静に受け止め、最終的な目標達成に向けて、過去問研究や苦手分野の克服といった具体的な対策を着実に進めていくことが何よりも重要です。
偏差値帯別に見る大学一覧
ここでは、大手予備校が発表する偏差値(主に文系学部・個別日程を基準)を参考に、偏差値帯別にどのような大学が含まれるのかを一覧で紹介します。自分の現在の偏差値や目標とする偏差値帯に、どのような大学が存在するのかを把握することで、志望校選びの解像度を上げることができます。
※ここに掲載する大学名および偏差値はあくまで一例であり、学部や入試方式によって異なります。最新かつ詳細な情報については、各大学の公式ウェブサイトや大手予備校の発表をご確認ください。
偏差値70以上の大学
偏差値70以上は、受験生全体の上位約2.3%に相当する極めて高い学力レベルが求められる領域です。この偏差値帯に位置するのは、日本の学術研究をリードする最難関の国公立大学と私立大学のトップ学部です。合格を勝ち取るためには、全科目で高いレベルの学力と思考力、そして記述力が不可欠となります。
| 区分 | 大学名 | 代表的な学部・学科の例 |
|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 文科一類、理科三類 など |
| 国公立 | 京都大学 | 法学部、医学部医学科 など |
| 国公立 | 一橋大学 | 商学部、経済学部 など |
| 私立 | 慶應義塾大学 | 医学部、法学部、経済学部 など |
| 私立 | 早稲田大学 | 政治経済学部、法学部 など |
| 私立 | 国際基督教大学(ICU) | 教養学部 |
このレベルの大学を目指す受験生は、高校1、2年生の早い段階から受験を意識した学習を始めていることが多く、基礎力は盤石であることが前提となります。その上で、難解な問題に対応できる応用力や、自らの考えを論理的に表現する力が問われます。また、医学部医学科については、他の学部とは一線を画す難易度であり、多くの国公立・私立大学で偏差値70を超える、あるいはそれに近い数値となっています。この偏差値帯の大学を志望する場合、特化した対策と極めて高いレベルでの競争を覚悟する必要があります。
偏差値60〜69の大学
偏差値60以上は、受験生全体の上位約16%にあたり、難関大学と呼ばれる大学群がひしめくボリュームゾーンです。旧帝国大学をはじめとする有力国公立大学や、人気の高い私立大学群(MARCH、関関同立など)の多くがこの範囲に収まります。選択肢が非常に豊富であるため、大学ごとの特色や自分の学びたいことと照らし合わせながら、じっくりと志望校を検討することが重要になります。
| 区分 | 大学名(大学群) | 代表的な学部・学科の例 |
|---|---|---|
| 国公立 | 大阪大学、東北大学、名古屋大学、北海道大学、九州大学(旧帝大) | 多くの学部 |
| 国公立 | 東京工業大学、筑波大学、神戸大学、横浜国立大学、千葉大学 など | 多くの学部 |
| 私立 | 早稲田大学、慶應義塾大学 | 人間科学部、スポーツ科学部など(一部) |
| 私立 | 上智大学、東京理科大学 | 多くの学部 |
| 私立 | MARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学) | 多くの学部 |
| 私立 | 関関同立(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学) | 多くの学部 |
この偏差値帯の大学に合格するためには、苦手科目を作らず、全科目でバランス良く高得点を取ることが基本戦略となります。特に、英語や数学といった主要科目の出来が合否を分けることが多いです。基礎的な知識を完璧に定着させた上で、標準レベルから応用レベルの問題まで、幅広く対応できる実力を養う必要があります。また、大学・学部によって入試問題の傾向が大きく異なるため、志望校を絞り込んだ後は、過去問研究を徹底的に行い、対策を最適化していくことが合格への鍵となります。
偏差値50〜59の大学
偏差値50以上は、受験生全体の平均以上の学力レベルを示します。この偏差値帯には、全国の地方国公立大学や、知名度の高い中堅私立大学群(日東駒専、産近甲龍など)が数多く含まれており、受験者層が最も厚い激戦区の一つです。
| 区分 | 大学名(大学群) | 代表的な学部・学科の例 |
|---|---|---|
| 国公立 | 埼玉大学、信州大学、静岡大学、新潟大学、広島大学 など | 多くの学部 |
| 国公立 | 東京都立大学、大阪公立大学、名古屋市立大学 など(公立大学) | 多くの学部 |
| 私立 | 日東駒専(日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学) | 多くの学部 |
| 私立 | 産近甲龍(京都産業大学、近畿大学、甲南大学、龍谷大学) | 多くの学部 |
| 私立 | 成城大学、明治学院大学、獨協大学、國學院大學、武蔵大学 など | 多くの学部 |
この偏差値帯の大学を目標とする場合、何よりも重要なのは高校で学ぶ基礎学力の徹底的な定着です。教科書レベルの知識を完璧に理解し、標準的な問題集を繰り返し解くことで、合格に必要な学力は十分に身につきます。奇をてらった難問対策よりも、基本的な問題を確実に得点する力が求められます。また、多くの大学が多様な学部・学科を設置しているため、自分の興味や将来の目標に合った学びの場を見つけやすいのもこの偏差値帯の特徴です。オープンキャンパスなどに積極的に参加し、大学の雰囲気を肌で感じてみることをお勧めします。
偏差値40〜49の大学
偏差値40台は、受験生全体の中で平均よりやや下の位置を示しますが、全国にはこの偏差値帯に属する大学が数多く存在します。このレベルの大学は、学力だけでなく、学生の個性や意欲を重視する傾向があります。
| 区分 | 大学名(大学群) | 代表的な学部・学科の例 |
|---|---|---|
| 私立 | 大東亜帝国(大東文化大学、東海大学、亜細亜大学、帝京大学、国士舘大学) | 多くの学部 |
| 私立 | 摂神追桃(摂南大学、神戸学院大学、追手門学院大学、桃山学院大学) | 多くの学部 |
| 私立 | その他、全国の多数の私立大学 | 多くの学部 |
この偏差値帯の大学を目指す場合、諦めずに基礎から学習をやり直すことが合格への最短ルートです。特に英語や国語といった文系科目の基礎、数学Ⅰ・Aといった理系科目の基礎を固めることが重要です。入試方式も多様で、一般選抜だけでなく、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜の枠が比較的多いのも特徴です。自分の強み(部活動の実績、資格、課外活動など)をアピールできる入試方式を探してみるのも一つの戦略です。偏差値の数字だけで判断せず、各大学が提供する教育内容や就職支援、キャンパスライフの充実度などをしっかりと比較検討し、自分にとって最適な環境を選ぶことが、満足度の高い大学生活につながります。
【国公立・私立別】大学偏差値ランキング
大学を大きく分けると、国が運営する「国立大学」、地方自治体が運営する「公立大学」、そして学校法人が運営する「私立大学」の3種類があります。これらは学費や入試科目、学生数、研究環境など、多くの面で特徴が異なります。ここでは、国公立大学と私立大学に分けて、それぞれの偏差値ランキングの上位校を紹介します。
※偏差値は複数の学部・学科の平均的な数値を参考にしているため、あくまで目安です。特に難易度の高い医学部医学科は除外して考慮している場合があります。
参照:河合塾 Kei-Net、東進ドットコム 大学入試偏差値ランキング
国公立大学の偏差値ランキング
国公立大学は、学費が私立大学に比べて安価であること、研究設備が充実している傾向にあること、そして入試では大学入学共通テストで5教科7科目など多くの科目が課されることが特徴です。そのため、幅広い教科で高い学力が求められます。
| 順位帯 | 大学名 | 偏差値帯の目安 | 特徴・代表的な学部 |
|---|---|---|---|
| トップ | 東京大学 | 67.5以上 | 日本の最高学府。全科類で極めて高いレベルが求められる。文科一類、理科三類など。 |
| 京都大学 | 65.0~ | 東京大学に次ぐ難関。自由な学風で知られる。法学部、総合人間学部など。 | |
| 準トップ | 一橋大学 | 65.0~ | 社会科学系に特化した名門。商学部、経済学部など。 |
| 東京工業大学 | 65.0~ | 理工学系のトップ大学。情報理工学院、理学院など。 | |
| 上位 | 大阪大学 | 62.5~ | 西日本を代表する総合大学。文学部、法学部、基礎工学部など。 |
| 東北大学 | 60.0~ | 研究第一主義を掲げる。旧帝国大学の一つ。文学部、経済学部、理学部など。 | |
| 名古屋大学 | 60.0~ | 中部地方のトップ大学。旧帝国大学の一つ。情報学部、法学部、工学部など。 | |
| 北海道大学 | 60.0~ | 広大なキャンパスとリベラルな教育。旧帝国大学の一つ。総合入試、獣医学部など。 | |
| 九州大学 | 60.0~ | 九州地方の拠点大学。旧帝国大学の一つ。共創学部、経済学部、工学部など。 | |
| 筑波大学 | 60.0~ | 「学群・学類」制が特徴の総合大学。社会・国際学群、情報学群など。 | |
| 神戸大学 | 60.0~ | 国際都市に位置する難関大学。経営学部、国際人間科学部など。 | |
| 中堅上位 | 横浜国立大学、千葉大学、お茶の水女子大学、広島大学、岡山大学など | 57.5~ | 各地域の中核を担う有力大学。それぞれに特色ある学部を持つ。 |
国公立大学を目指す場合、共通テストでの高得点獲得が絶対条件となります。共通テストで目標点をクリアした上で、各大学が課す二次試験(個別学力検査)の対策に進むのが一般的な流れです。二次試験は大学・学部によって特色が大きく異なり、論述問題や難易度の高い数学・物理などが課されることも多いため、志望校の過去問を徹底的に分析し、傾向に合わせた対策が不可欠です。
私立大学の偏差値ランキング
私立大学は、国公立に比べて大学の数が圧倒的に多く、建学の精神に基づいた個性豊かな教育を展開しているのが特徴です。入試科目は2~3教科に絞られることが多く、得意科目を活かして受験しやすい一方、人気大学は志願者が集中し、高倍率の厳しい競争となります。
| 順位帯 | 大学名 | 偏差値帯の目安 | 特徴・代表的な学部(大学群) |
|---|---|---|---|
| 最難関 | 慶應義塾大学 | 65.0~ | 「実学の精神」を掲げる名門。医学部、法学部、経済学部など。 |
| 早稲田大学 | 65.0~ | 在野精神が根付く総合大学。政治経済学部、法学部、商学部など。 | |
| 難関上位 | 上智大学 | 62.5~ | 語学教育と国際性に定評。外国語学部、法学部、国際教養学部など。 |
| 国際基督教大学(ICU) | 67.5 | リベラルアーツ教育の最高峰。入試方式が独特。教養学部。 | |
| 東京理科大学 | 60.0~ | 実力主義を貫く理工系大学。薬学部、工学部、理学部など。 | |
| 難関 | 明治大学 (MARCH) | 60.0~ | 志願者数トップクラスの人気大学。商学部、政治経済学部など。 |
| 青山学院大学 (MARCH) | 60.0~ | おしゃれなイメージで人気。文学部、国際政治経済学部など。 | |
| 立教大学 (MARCH) | 60.0~ | 異文化コミュニケーション学部や経営学部が特に人気。 | |
| 同志社大学 (関関同立) | 60.0~ | 関西私大の雄。グローバル・コミュニケーション学部、商学部など。 | |
| 難関 | 中央大学 (MARCH) | 57.5~ | 法学部が特に有名。「法科の中央」として知られる。 |
| 法政大学 (MARCH) | 57.5~ | 多様な学部を持つ総合大学。グローバル教養学部など。 | |
| 関西学院大学 (関関同立) | 57.5~ | 国際学部などが人気。美しいキャンパスで知られる。 | |
| 立命館大学 (関関同立) | 57.5~ | 国際関係学部や映像学部など先進的な学部を持つ。 | |
| 関西大学 (関関同立) | 57.5~ | 親しみやすい雰囲気の総合大学。法学部、外国語学部など。 | |
| 中堅上位 | 学習院大学、成蹊大学、成城大学、明治学院大学、南山大学、西南学院大学など | 55.0~ | 各地域で高い評価と人気を誇る大学群。 |
私立大学の一般選抜では、英語、国語、地歴・公民または数学の3教科が基本となります(理系は英語、数学、理科)。科目数が少ない分、1つのミスが合否に大きく響くシビアな戦いになります。各教科で完成度を極限まで高めることが求められます。また、共通テスト利用入試、全学部日程、学部別日程など、入試方式が非常に多様であるため、自分の学力や得意科目に合わせて最適な入試方式を組み合わせる「受験戦略」が非常に重要になります。
【学部系統別】大学偏差値ランキング
大学選びにおいて、偏差値と並んで重要なのが「何を学びたいか」という視点です。自分の興味・関心がある学問分野から大学を探すことで、学習へのモチベーションが高まり、将来のキャリアにも繋がる有意義な4年間を送ることができます。ここでは、主要な学部系統別に、どのような学びがあるのか、そしてどの大学がその分野で高い評価を得ているのかを偏差値とともに紹介します。
※ここでのランキングも、大手予備校のデータを参考に作成した目安です。
文系学部
文系学部は、人間の活動、社会、文化、歴史などを研究対象とする学問分野です。卒業後の進路が多岐にわたるのが特徴で、民間企業への就職が中心ですが、公務員や教員、専門職を目指す学生も多くいます。
| 学部系統 | 学びの内容 | 偏差値上位の大学例(国公立・私立) |
|---|---|---|
| 法・政治学系 | 社会のルールである法律や、国内外の政治の仕組みを学ぶ。論理的思考力や分析力が養われる。 | 国公立: 東京大学、京都大学、一橋大学、大阪大学 私立: 慶應義塾大学、早稲田大学、中央大学、上智大学 |
| 経済・経営・商学系 | モノやお金の流れ(経済)、企業や組織の運営方法(経営)、商品の流通やマーケティング(商)を学ぶ。実社会に直結する学問。 | 国公立: 東京大学、京都大学、一橋大学、神戸大学 私立: 慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、立教大学 |
| 文・史・哲学系 | 人間の思考や感情、歴史、文化を、文学作品、歴史資料、哲学思想などを通して探求する。教養や人間理解を深める。 | 国公立: 東京大学、京都大学、東北大学、筑波大学 私立: 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、青山学院大学 |
| 国際・外国語学系 | 高度な語学運用能力を身につけるとともに、特定の地域や国際社会が抱える課題について文化・政治・経済など多角的に学ぶ。 | 国公立: 東京外国語大学、大阪大学、神戸市外国語大学 私立: 早稲田大学、上智大学、国際基督教大学、関西学院大学 |
| 社会・社会福祉学系 | 現代社会の様々な現象(メディア、家族、環境問題など)や、福祉の制度・実践について学ぶ。フィールドワークも多い。 | 国公立: 一橋大学、筑波大学、東京都立大学 私立: 早稲田大学、立教大学、法政大学、関西学院大学 |
文系学部を選ぶ際は、学部名だけでなく、その大学のその学部でどのような専門分野を学べるか、どんな教員がいるかまで調べることが重要です。例えば同じ「経済学部」でも、理論経済学に強い大学、歴史研究に強い大学、データ分析に力を入れている大学など、特色は様々です。大学のウェブサイトでシラバス(講義計画)を確認してみましょう。
理系学部
理系学部は、自然科学の法則や、科学技術の応用について研究する学問分野です。実験や演習が多く、論理的思考力や探求心が求められます。専門知識を活かして、研究者や技術者として活躍する道が開かれています。
| 学部系統 | 学びの内容 | 偏差値上位の大学例(国公立・私立) |
|---|---|---|
| 理学系 | 数学、物理学、化学、生物学、地学といった自然科学の基礎原理を探求する。「なぜそうなるのか」を追求する学問。 | 国公立: 東京大学、京都大学、東京工業大学、東北大学 私立: 早稲田大学、慶應義塾大学、東京理科大学 |
| 工学系 | 理学の知見を応用し、人々の生活を豊かにする「ものづくり」や「システムづくり」を目指す。機械、電気電子、情報、建築、応用化学など分野は多岐にわたる。 | 国公立: 東京大学、京都大学、東京工業大学、大阪大学 私立: 早稲田大学、慶應義塾大学、東京理科大学、同志社大学 |
| 農・水産学系 | 食料生産、環境保全、生命科学など、生物資源に関わる幅広い分野を学ぶ。SDGsへの関心の高まりから注目されている。 | 国公立: 東京大学、京都大学、北海道大学、東京農工大学 私立: 明治大学、東京農業大学、近畿大学 |
| 情報科学系 | コンピュータの仕組み、プログラミング、AI、データサイエンス、ネットワーク技術などを学ぶ。近年、需要が急速に高まっている分野。 | 国公立: 東京大学、京都大学、東京工業大学、電気通信大学 私立: 慶應義塾大学、早稲田大学、東京理科大学 |
理系学部は、大学院への進学率が高いことも特徴です。特に研究職や開発職を目指す場合、修士課程への進学が一般的となっています。そのため、学部4年間だけでなく、大学院も含めた6年間の学びを視野に入れて大学を選ぶことも重要です。各大学の研究室のウェブサイトを見て、どのような研究が行われているかを調べるのも良いでしょう。
医・歯・薬・看護・保健系学部
これらの学部は、人の生命や健康に直接関わる、極めて専門性の高い分野です。多くの場合、卒業後に国家資格を取得し、専門職として医療現場などで働くことになります。
| 学部系統 | 学びの内容 | 偏差値上位の大学例(国公立・私立) |
|---|---|---|
| 医学部(医学科) | 6年間の教育で医師になるための知識と技術を学ぶ。偏差値は全学部の中で最も高く、最難関。 | 国公立: 東京大学、京都大学、大阪大学、東京医科歯科大学 私立: 慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、順天堂大学 |
| 歯学部(歯学科) | 6年間の教育で歯科医師になるための知識と技術を学ぶ。 | 国公立: 東京医科歯科大学、大阪大学、東北大学 私立: 東京歯科大学、日本歯科大学 |
| 薬学部 | 薬の専門家である薬剤師を養成する6年制学科と、創薬研究者などを養成する4年制学科がある。 | 国公立: 東京大学、京都大学、千葉大学 私立: 慶應義塾大学、東京理科大学、星薬科大学 |
| 看護・保健学系 | 看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師など、様々な医療専門職(コメディカル)を養成する。 | 国公立: 東京大学、京都大学、千葉大学、神戸大学 私立: 慶應義塾大学、聖路加国際大学、順天堂大学 |
この系統の学部は、資格取得が大きな目標となるため、国家試験の合格率が大学選びの重要な指標となります。また、付属病院の有無やその規模、臨床実習の環境なども、実践的なスキルを身につける上で非常に重要です。偏差値だけでなく、将来自分がどのような医療専門職になりたいかを具体的にイメージし、その実現に最も適した教育環境を持つ大学を選ぶことが求められます。
総合・学際・その他学部
従来の文系・理系の枠にとらわれず、複数の学問分野を横断的に学ぶのが総合・学際系学部です。複雑化する現代社会の課題に対応できる、幅広い視野と複合的な思考力を持つ人材の育成を目指します。
| 学部系統 | 学びの内容 | 偏差値上位の大学例 |
|---|---|---|
| 総合科学・教養学系 | 文理の垣根なく、様々な学問分野の基礎を幅広く学んだ上で、自分の専門分野を決定する(リベラルアーツ教育)。 | 東京大学(教養学部)、国際基督教大学(教養学部)、早稲田大学(国際教養学部)、広島大学(総合科学部) |
| 環境・情報・人間科学系 | 環境問題、情報社会、人間の心理や行動など、現代的なテーマを文理融合のアプローチで探求する。 | 筑波大学(情報学群)、早稲田大学(人間科学部)、慶應義塾大学(環境情報学部)、青山学院大学(社会情報学部) |
これらの学部は、カリキュラムの自由度が高いことが多く、学生自身の主体性や知的好奇心が強く求められます。「まだ何を専門にしたいか決められないが、大学で様々な学問に触れてから考えたい」という人や、「一つの分野だけでなく、複数の視点から物事を捉えたい」という人に向いています。入学後にミスマッチを起こさないよう、その学部で具体的にどのような学びが可能かを、オープンキャンパスや大学のウェブサイトで入念に調べておくことが大切です。
【エリア別】大学偏差値ランキング
大学進学を機に一人暮らしを始める人も、地元の大学に通う人も、キャンパスが位置する「エリア」は大学生活の質を大きく左右する要素です。ここでは、全国を7つのエリアに分け、それぞれのエリアを代表する大学を国公立・私立別に紹介します。地元志向の受験生はもちろん、地方の大学への進学を考えている受験生もぜひ参考にしてください。
※偏差値は文系学部を中心に、各大学の代表的な学部のものを目安として記載しています。
北海道・東北エリア
広大で豊かな自然に恵まれたエリア。学術研究の拠点となる旧帝国大学をはじめ、個性豊かな大学が点在しています。
| 区分 | 大学名 | 所在地 | 偏差値帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 北海道大学 | 北海道 | 60.0~ |
| 国公立 | 東北大学 | 宮城県 | 60.0~ |
| 国公立 | 小樽商科大学 | 北海道 | 55.0~ |
| 国公立 | 弘前大学 | 青森県 | 50.0~ |
| 国公立 | 岩手大学 | 岩手県 | 47.5~ |
| 国公立 | 秋田大学 | 秋田県 | 50.0~ |
| 国公立 | 山形大学 | 山形県 | 50.0~ |
| 国公立 | 福島大学 | 福島県 | 50.0~ |
| 私立 | 北海学園大学 | 北海道 | 45.0~ |
| 私立 | 東北学院大学 | 宮城県 | 45.0~ |
関東エリア
日本の政治・経済・文化の中心地。最難関大学から中堅大学まで、数多くの大学が集中しており、受験生にとって最も選択肢の多いエリアです。
| 区分 | 大学名 | 所在地 | 偏差値帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 東京都 | 67.5~ |
| 国公立 | 一橋大学 | 東京都 | 65.0~ |
| 国公立 | 東京工業大学 | 東京都 | 65.0~ |
| 国公立 | 筑波大学 | 茨城県 | 60.0~ |
| 国公立 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 60.0~ |
| 国公立 | 千葉大学 | 千葉県 | 60.0~ |
| 国公立 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 60.0~ |
| 国公立 | 東京都立大学 | 東京都 | 57.5~ |
| 私立 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 65.0~ |
| 私立 | 早稲田大学 | 東京都 | 65.0~ |
| 私立 | 上智大学 | 東京都 | 62.5~ |
| 私立 | 明治大学 | 東京都 | 60.0~ |
| 私立 | 青山学院大学 | 東京都 | 60.0~ |
| 私立 | 立教大学 | 東京都 | 60.0~ |
甲信越・北陸エリア
豊かな自然環境と、伝統産業が根付くエリア。落ち着いた環境で学問に打ち込みたい学生に適した大学が多くあります。
| 区分 | 大学名 | 所在地 | 偏差値帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 金沢大学 | 石川県 | 52.5~ |
| 国公立 | 新潟大学 | 新潟県 | 50.0~ |
| 国公立 | 信州大学 | 長野県 | 50.0~ |
| 国公立 | 富山大学 | 富山県 | 50.0~ |
| 国公立 | 福井大学 | 福井県 | 50.0~ |
| 国公立 | 山梨大学 | 山梨県 | 50.0~ |
| 私立 | 金沢工業大学 | 石川県 | 45.0~ |
東海エリア
日本のものづくりを支える産業集積地。工学系の学部が充実している大学が多く、企業との共同研究も盛んです。
| 区分 | 大学名 | 所在地 | 偏差値帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 名古屋大学 | 愛知県 | 60.0~ |
| 国公立 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 57.5~ |
| 国公立 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 55.0~ |
| 国公立 | 静岡大学 | 静岡県 | 50.0~ |
| 国公立 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 50.0~ |
| 国公立 | 三重大学 | 三重県 | 50.0~ |
| 私立 | 南山大学 | 愛知県 | 52.5~ |
| 私立 | 中京大学 | 愛知県 | 50.0~ |
| 私立 | 名城大学 | 愛知県 | 50.0~ |
関西エリア
関東に次ぐ大都市圏であり、歴史と文化が色濃く残るエリア。関東とはまた違った個性を持つ難関大学が揃っています。
| 区分 | 大学名 | 所在地 | 偏差値帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 京都大学 | 京都府 | 65.0~ |
| 国公立 | 大阪大学 | 大阪府 | 62.5~ |
| 国公立 | 神戸大学 | 兵庫県 | 60.0~ |
| 国公立 | 大阪公立大学 | 大阪府 | 55.0~ |
| 国公立 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 55.0~ |
| 私立 | 同志社大学 | 京都府 | 60.0~ |
| 私立 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 57.5~ |
| 私立 | 立命館大学 | 京都府 | 57.5~ |
| 私立 | 関西大学 | 大阪府 | 57.5~ |
| 私立 | 近畿大学 | 大阪府 | 52.5~ |
中国・四国エリア
温暖な気候と、瀬戸内海や日本海といった多様な自然環境が魅力のエリア。地域の中核となる国公立大学が教育・研究をリードしています。
| 区分 | 大学名 | 所在地 | 偏差値帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 広島大学 | 広島県 | 52.5~ |
| 国公立 | 岡山大学 | 岡山県 | 52.5~ |
| 国公立 | 山口大学 | 山口県 | 50.0~ |
| 国公立 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 50.0~ |
| 国公立 | 香川大学 | 香川県 | 50.0~ |
| 国公立 | 徳島大学 | 徳島県 | 50.0~ |
| 国公立 | 高知大学 | 高知県 | 50.0~ |
| 私立 | 松山大学 | 愛媛県 | 45.0~ |
九州・沖縄エリア
アジアへの玄関口として、独自の歴史と文化を育んできたエリア。国際交流が盛んな大学や、特色ある研究を行う大学が見られます。
| 区分 | 大学名 | 所在地 | 偏差値帯の目安 |
|---|---|---|---|
| 国公立 | 九州大学 | 福岡県 | 60.0~ |
| 国公立 | 熊本大学 | 熊本県 | 50.0~ |
| 国公立 | 長崎大学 | 長崎県 | 50.0~ |
| 国公立 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 50.0~ |
| 国公立 | 琉球大学 | 沖縄県 | 45.0~ |
| 私立 | 西南学院大学 | 福岡県 | 52.5~ |
| 私立 | 福岡大学 | 福岡県 | 47.5~ |
| 私立 | 立命館アジア太平洋大学(APU) | 大分県 | 55.0~ |
偏差値だけで決めない!後悔しない大学選びのポイント
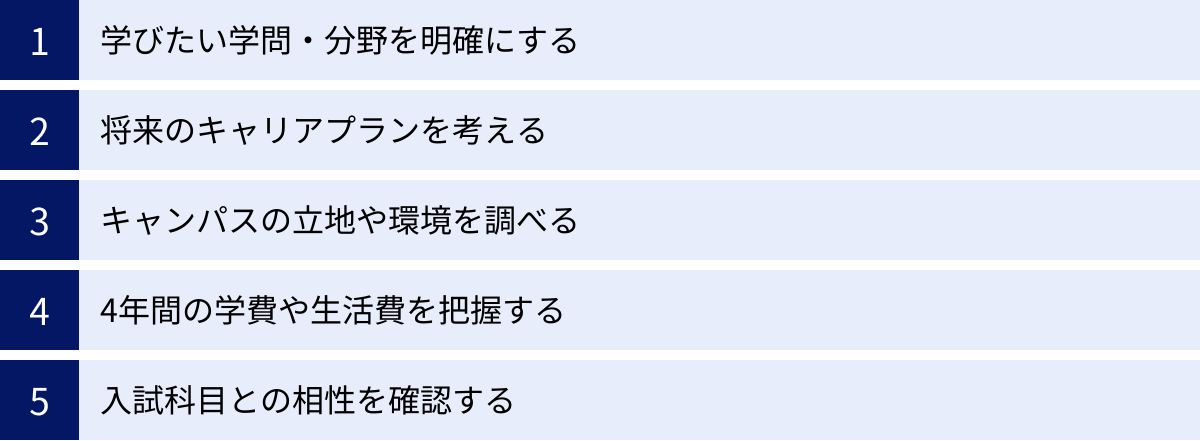
これまで様々な偏差値ランキングを紹介してきましたが、大学選びで最も大切なのは、偏差値という一つの指標だけに依存しないことです。偏差値の高い大学に入学することがゴールではありません。入学後の4年間をいかに有意義に過ごし、将来の自分の糧にできるかが重要です。ここでは、偏差値以外の側面から、後悔しない大学選びをするための5つの重要なポイントを解説します。
学びたい学問・分野を明確にする
大学は、高校までとは違い、自らが専門分野を選んで深く学んでいく場所です。「偏差値が高いから」「知名度があるから」といった理由だけで学部を選ぶと、興味の持てない講義に苦痛を感じ、学習意欲を失ってしまう可能性があります。こうしたミスマッチを防ぐために、まずは自分が本当に学びたいことは何かをじっくり探求しましょう。
- 自己分析: 好きな教科、興味のある社会問題、熱中できる趣味などから、自分の関心の方向性を探ります。「なぜそれが好きなのか?」を深掘りしていくと、学問分野に結びつくことがあります。
- 情報収集: 大学の公式ウェブサイトやパンフレットは情報の宝庫です。特に「学部・学科紹介」のページを熟読し、カリキュラム(どのような授業が何年生で受けられるか)や、所属している教員の専門分野、研究室(ゼミ)のテーマなどを確認しましょう。
- シラバスの確認: 多くの大学では、講義ごとの詳細な計画書である「シラバス」をオンラインで公開しています。実際にどのような内容を、どのような目的で、どのように学ぶのかが具体的に書かれており、学部の学びをリアルにイメージするのに非常に役立ちます。
- オープンキャンパスへの参加: 模擬授業を受けたり、在学生や教員と直接話したりすることで、パンフレットだけでは分からないリアルな雰囲気を掴むことができます。
同じ「文学部」でも、英文学に強い大学、日本史の研究が盛んな大学、心理学のコースが充実している大学など、その特色は千差万別です。自分の知的好奇心を満たしてくれる環境かどうかを、徹底的にリサーチすることが重要です。
将来のキャリアプランを考える
大学生活は、社会に出るための準備期間でもあります。4年後に自分がどのような姿になっていたいか、どのような分野で活躍したいかを少しでもイメージしておくことは、大学選びの重要な軸となります。
- 就職実績・サポート体制: 大学のウェブサイトで「キャリア・就職支援」のページを確認し、主な就職先企業や、業界・業種別の就職者数を見てみましょう。自分の目指す業界への就職者が多い大学は、関連企業とのつながりが強く、OB/OG訪問などがしやすい可能性があります。また、キャリアセンターが実施している支援プログラム(インターンシップの紹介、エントリーシートの添削、面接指導など)の充実度もチェックポイントです。
- 取得可能な資格: 目指す職業によっては、特定の資格が必要な場合があります(教員免許、学芸員、各種国家試験受験資格など)。志望する学部・学科で希望の資格が取得できるかどうかは、必ず確認しておきましょう。
- 大学院進学: 研究者や高度専門職業人を目指す場合、大学院への進学が一般的です。志望大学の大学院進学率や、内部進学のしやすさ、大学院の研究環境なども調べておくと良いでしょう。
漠然とでも将来像を描くことで、その実現のために大学のどのようなリソース(教育、人脈、設備など)を活用できるかという視点で、大学を比較検討できるようになります。
キャンパスの立地や環境を調べる
4年間(あるいはそれ以上)通うことになるキャンパスの立地や環境は、日々の生活の質や学習への集中力に大きく影響します。
- キャンパスの場所と通学時間: 自宅から大学までの通学時間は、毎日のことです。ドアツードアでどのくらいかかるのか、乗り換えはスムーズかなどを具体的にシミュレーションしてみましょう。通学時間が長すぎると、学業やサークル活動、アルバイトに使える時間が削られてしまいます。
- キャンパスのタイプ: 都心にある「都市型キャンパス」は、交通の便が良く、アルバイト先や文化施設も豊富ですが、キャンパスが手狭な場合もあります。一方、郊外にあるキャンパスは、広々とした敷地で落ち着いて学べる環境ですが、都心へのアクセスに時間がかかることがあります。
- タコ足キャンパスの確認: 学年によって通うキャンパスが異なる「タコ足キャンパス(学年割れキャンパス)」の大学もあります。例えば、「1・2年次は郊外のキャンパス、3・4年次は都心のキャンパス」といったケースです。入学前に知っておかないと、住む場所の選択などで後悔する可能性があります。
- 周辺環境: キャンパスの周りに何があるか(飲食店、書店、図書館、スーパーなど)も、学生生活の利便性を左右します。
実際に一度、志望校のキャンパスとその最寄り駅を訪れてみてください。街の雰囲気や学生たちの様子を肌で感じることで、自分に合った環境かどうかを判断する大きな手がかりになります。
4年間の学費や生活費を把握する
大学進学には多額の費用がかかります。保護者の方としっかり相談し、現実的な資金計画を立てることが不可欠です。
- 学費の内訳: 大学のウェブサイトや募集要項で、初年度納付金だけでなく、2年次以降の学費も確認しましょう。入学金、授業料の他に、施設設備費、実験実習費などが必要な場合があります。特に私立大学は、文系、理系、医歯薬系で学費が大きく異なります。
- 国公立と私立の比較: 一般的に、国公立大学の学費は年間約54万円でほぼ一律ですが、私立大学は文系で年間約80~120万円、理系で約110~160万円程度と、大学や学部によって差があります。4年間の総額で比較検討することが重要です。
- 生活費: 一人暮らしをする場合は、学費に加えて家賃、食費、光熱費、通信費などの生活費がかかります。エリアによって家賃相場は大きく異なるため、事前に調べておきましょう。
- 奨学金・特待生制度: 経済的な負担を軽減するために、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金や、大学が独自に設けている奨学金・授業料免除制度、成績優秀者向けの特待生制度などを積極的に活用しましょう。どのような制度があり、どのような条件で利用できるかを事前に調べておくことが大切です。
お金の話は少し気が引けるかもしれませんが、安心して学業に専念するためには避けて通れない問題です。早い段階から情報を集め、計画を立てておきましょう。
入試科目との相性を確認する
どれだけ魅力的な大学でも、入試を突破できなければ入学は叶いません。自分の学力と、志望校の入試科目・配点が合っているか(=相性が良いか)を確認することは、極めて重要な戦略です。
- 入試科目: 志望する大学・学部の入試に必要な科目を正確に把握しましょう。国公立大学は共通テストで多科目が課されるのが基本ですが、私立大学は2~3科目が中心です。自分の苦手科目が課されない大学・学部を選ぶのも一つの戦略です。
- 配点比率: 各科目の配点比率は必ず確認してください。例えば、英語の配点が他の科目より極端に高い大学もあれば、全科目が均等配点の大学もあります。自分の得意科目の配点が高い大学は、他の受験生に対して有利に戦うことができます。
- 問題の傾向: 過去問題(赤本など)を実際に見て、問題の形式や難易度を確認しましょう。マークシート方式が多いか、記述・論述問題が中心か、基礎的な問題が多いか、応用的な難問が出題されるかなど、大学によって傾向は様々です。自分の得意な問題形式の大学を選ぶことで、合格の可能性を高めることができます。
偏差値が同じくらいの大学でも、入試科目や配点、問題傾向は全く異なります。自分の強みを最大限に活かせる「戦いやすい」大学を見つけることが、合格への近道となるのです。
大学の偏差値に関するよくある質問
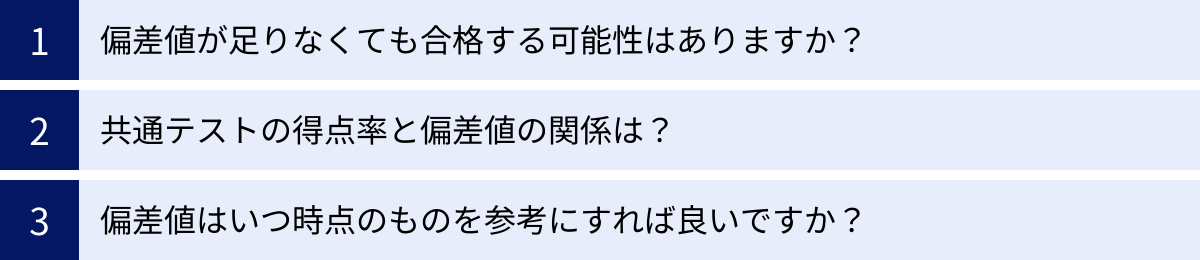
最後に、受験生や保護者の方からよく寄せられる、大学の偏差値に関する質問とその回答をまとめました。多くの人が抱える疑問を解消し、より安心して受験勉強に臨みましょう。
偏差値が足りなくても合格する可能性はありますか?
結論から言うと、可能性は十分にあります。 模試の判定がD判定やE判定であっても、諦めるのはまだ早いです。その理由はいくつかあります。
- 偏差値は過去のデータに過ぎない: 模試の偏差値は、あくまでその時点での学力を示すものです。入試本番までの残された期間で、学力は大きく伸びる可能性があります。特に現役生は、秋以降に成績が急上昇することがよくあります。今の偏差値で未来の合格可能性を決めつけてしまう必要はありません。
- 入試問題との相性: 前の章でも触れましたが、合格の可能性は偏差値だけで決まるわけではありません。たとえ模試の成績が振るわなくても、志望校の入試問題の傾向が自分の得意な形式と合致していれば、高得点を取れる可能性があります。逆もまた然りです。だからこそ、過去問研究が非常に重要になります。
- ボーダーラインの意味: 予備校が出す「ボーダーライン偏差値」は、合格可能性50%のラインです。これはつまり、その偏差値に満たない受験生でも、かなりの数が合格していることを意味します。合格者の下位層は、ボーダーライン偏差値よりも低い偏差値であることが一般的です。
- 当日のコンディションと運: 入試は一発勝負です。当日の体調や精神状態、そして問題との巡り合わせといった要素も合否に影響します。最後まで諦めずに努力を続けた人が、こうしたチャンスを掴むことができます。
もちろん、偏差値が大きく足りない状況からの逆転合格は簡単ではありません。しかし、「どうせ無理だ」と最初から諦めるのではなく、「合格するためには、あと何が足りないのか」を冷静に分析し、残された時間で戦略的に学習を進めることが、可能性を切り拓く鍵となります。
共通テストの得点率と偏差値の関係は?
「共通テストで〇〇%取れれば、偏差値△△の大学に合格できますか?」という質問は非常に多いですが、「共通テストの得点率」と「(模試の)偏差値」は、それぞれ異なる性質を持つ指標であり、直接的な換算はできません。
- 共通テストの得点率: これは、大学入学共通テストという「単一の試験」における、満点に対する自分の得点の割合を示す絶対的な指標です。例えば、900点満点で720点取れば、得点率は80%となります。
- 偏差値: これは、模試という「特定の受験者集団」の中での、自分の学力の相対的な位置を示す指標です。平均点が50になるように正規化されています。
この二つを結びつけて合格可能性を判断するために、予備校は主に以下の2つのデータを提供しています。
- 共通テストボーダー得点率(またはボーダーライン): 国公立大学の出願や、私立大学の共通テスト利用入試において、合格者と不合格者の数が半々になると予想される共通テストの得点率のことです。
- 二次試験ボーダー偏差値: 国公立大学の二次試験や、私立大学の個別日程試験における、合格可能性50%の偏差値のことです。
国公立大学の場合、まず共通テストでボーダーラインを突破できるかが第一関門となり、次に二次試験の学力(偏差値で示される)が問われます。この二つの成績を大学ごとの配点比率で合算して、最終的な合否が決まります。
したがって、これら二つの指標を別個のものとして理解し、自分が志望する大学の入試方式に合わせて、両方の目標値を設定し対策を進める必要があります。
偏差値はいつ時点のものを参考にすれば良いですか?
大学の偏差値は毎年少しずつ変動するため、基本的には、受験する年度の最新のものを参考にすべきです。予備校は通常、春から夏にかけて前年度の入試結果を反映した新しい偏差値データを発表します。
しかし、参考にする「時期」については、もう少し深く考える必要があります。
- 高1・高2の段階: この時期は、まだ学力が固まっていないため、偏差値の数値に一喜一憂する必要はありません。現時点での偏差値はあくまで参考程度にとどめ、様々な大学の情報を幅広く集め、自分の興味関心を探ることに時間を使いましょう。
- 高3の夏休み前(春~夏): この時期の模試の偏差値は、自分の基礎学力の定着度や苦手分野を把握するための重要なデータとなります。志望校をある程度絞り込み、夏休みの学習計画を立てる際の参考にしましょう。
- 高3の秋以降: 受験生にとって最も重要度が高いのが、この時期に受ける模試の偏差値です。部活動を引退した現役生も本格的に受験勉強にシフトし、浪人生も含めた本番に近い受験者層の中での自分の立ち位置が、より正確に分かります。この時期の偏差値と合格判定をもとに、最終的な出願校を決定していくことになります。
結論として、志望校選びの初期段階では前年度の偏差値を参考にし、学年が上がるにつれて、自分が受験した最新の模試の結果を重視していくのが良いでしょう。また、一度の模試結果だけでなく、複数回の模試の結果を並べて見ることで、自分の学力の推移(伸びているのか、停滞しているのか)を客観的に把握し、学習方法を見直すきっかけにすることも大切です。
参照:
- 河合塾 Kei-Net
- 東進ドットコム 大学入試偏差値ランキング
- 駿台予備学校 I-SUM Club