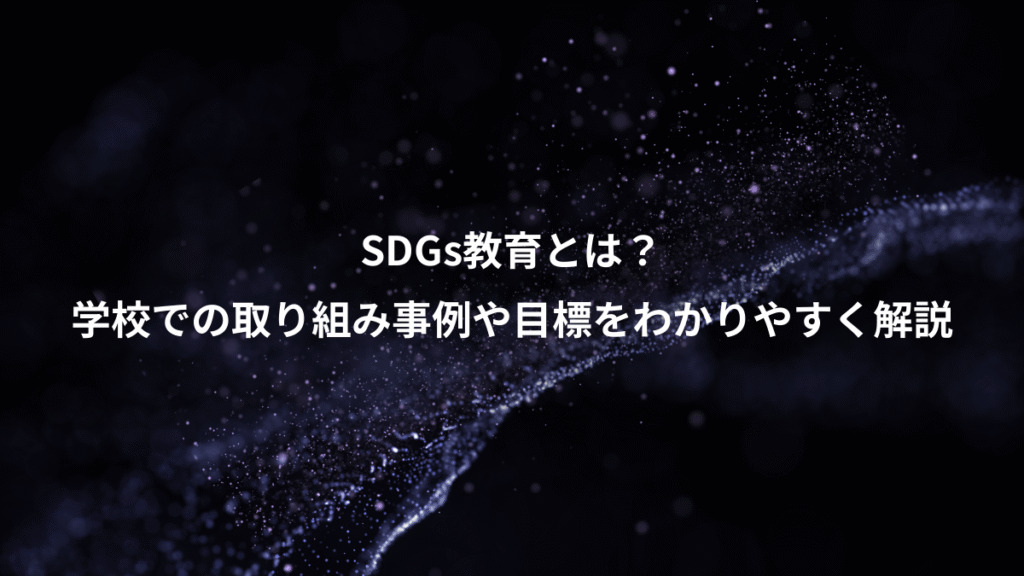近年、教育現場で「SDGs教育」という言葉を耳にする機会が急速に増えています。2020年度から順次施行されている新しい学習指導要領にも「持続可能な社会の創り手」の育成が明記され、全国の学校でその導入が進められています。しかし、SDGsという言葉自体は知っていても、「なぜ教育でSDGsを扱う必要があるのか」「具体的にどのような授業が行われているのか」「家庭では何ができるのか」といった点について、疑問を持つ方も少なくないでしょう。
SDGs教育は、単に17の目標を暗記するための学習ではありません。それは、貧困、気候変動、ジェンダー平等といった地球規模の複雑な課題を「自分ごと」として捉え、解決に向けて主体的に行動できる市民を育むための、未来志向の教育です。変化が激しく、予測困難な時代を生きる子どもたちにとって、多様な価値観を理解し、他者と協働しながら新たな価値を創造していく力は、不可欠なスキルとなります。
この記事では、SDGs教育の根幹にある考え方から、その重要性、教育現場が抱える課題、そして小学校・中学校・高校といった校種別の具体的な取り組み事例まで、網羅的に解説します。さらに、家庭で今日から始められるSDGs教育のヒントや、授業や自主学習に役立つ教材・ツールも紹介します。
本記事を通じて、SDGs教育がなぜ現代社会にとって重要なのかを深く理解し、子どもたちの未来をより良いものにするためのヒントを得ていただければ幸いです。
目次
SDGs教育とは
SDGs教育という言葉を理解するためには、まずその土台となる「SDGs(持続可能な開発目標)」について正確に知る必要があります。SDGs教育は、この世界共通の目標を達成するための「人づくり」を目的とした教育活動全般を指します。ここでは、SDGsの基本的な概念から、それが生まれた背景、そしてSDGs教育の定義について詳しく解説します。
そもそもSDGs(持続可能な開発目標)とは
SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。2015年9月にニューヨークの国連本部で開催された「国連持続可能な開発サミット」において、国連に加盟する193カ国が全会一致で採択した国際目標であり、「国連持も続可能な開発のための2030アジェンダ」という文書に記載されています。
SDGsの最大の特徴は、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」という普遍的な理念を掲げている点です。これは、地球上のすべての人々が、その出自や居住地、性別、年齢、障害の有無などに関わらず、尊厳を持って生きられる社会を目指すという強い意志の表れです。この目標は、2030年までの15年間で達成することを目指しており、地球上の「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を誓っています。
具体的には、貧困や飢餓、教育、健康、ジェンダー、水、エネルギーといった社会課題から、気候変動や生物多様性といった環境課題、さらには働きがいや経済成長、技術革新、不平等の是正、平和と公正まで、現代世界が直面する課題を網羅した17のゴール(目標)と、それらをより具体的にした169のターゲットで構成されています。これらの目標は、先進国と開発途上国が共に取り組むべきユニバーサル(普遍的)なものとして位置づけられています。
SDGsが生まれた背景
SDGsが誕生する以前にも、国際社会には同様の目標が存在しました。それが、2000年に採択された「MDGs(ミレニアム開発目標)」です。MDGsは、2015年を達成期限とし、極度の貧困や飢餓の撲滅、初等教育の完全普及、乳幼児死亡率の削減など、8つのゴールと21のターゲットを掲げ、一定の成果を上げました。
しかし、MDGsにはいくつかの課題がありました。その最大の課題は、目標が主に開発途上国の課題に焦点を当てており、先進国は「支援する側」という位置づけだった点です。グローバル化が進行し、環境問題や経済格差が世界共通の課題となる中で、先進国を含むすべての国が当事者として取り組む新たな目標の必要性が認識されるようになりました。
また、MDGsが「人間開発」の側面に重点を置いていたのに対し、気候変動や資源の枯渇といった環境問題への対応が不十分であるという指摘もありました。そこで、MDGsの後継として策定されたSDGsでは、「社会」「経済」「環境」の3つの側面を不可分なものとして捉え、これらを統合的に解決していくことが目指されています。つまり、経済成長を追求するだけでなく、それが環境に与える影響や、社会的な公正さにも配慮しなければ「持続可能」ではない、という考え方が根底にあります。
このような背景から、SDGsは先進国も開発途上国も、政府だけでなく、企業、市民社会、そして私たち一人ひとりが主体的に取り組むべき普遍的な目標として誕生したのです。そして、この壮大な目標を達成するためには、次代を担う子どもたちがSDGsの本質を理解し、行動できる力を身につけることが不可欠です。SDGs教育とは、まさにこの「持続可能な社会の創り手」を育むための教育に他なりません。
SDGsの17の目標一覧
SDGsの17の目標は、私たちの生活のあらゆる側面に関わっています。以下に、17の目標を一覧で示します。それぞれのアイコンが何を表しているのかを想像しながらご覧いただくと、より理解が深まります。
| 目標番号 | アイコン | 目標の概要 |
|---|---|---|
| 目標1 | 貧困をなくそう | あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 |
| 目標2 | 飢餓をゼロに | 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農林水産業を促進する。 |
| 目標3 | すべての人に健康と福祉を | あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。 |
| 目標4 | 質の高い教育をみんなに | すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。 |
| 目標5 | ジェンダー平等を実現しよう | ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う。 |
| 目標6 | 安全な水とトイレを世界中に | すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。 |
| 目標7 | エネルギーをみんなにそしてクリーンに | すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。 |
| 目標8 | 働きがいも経済成長も | 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する。 |
| 目標9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう | 強靭(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及び技術革新の推進を図る。 |
| 目標10 | 人や国の不平等をなくそう | 各国内及び各国間の不平等を是正する。 |
| 目標11 | 住み続けられるまちづくりを | 包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する。 |
| 目標12 | つくる責任 つかう責任 | 持続可能な生産消費形態を確保する。 |
| 目標13 | 気候変動に具体的な対策を | 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。 |
| 目標14 | 海の豊かさを守ろう | 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。 |
| 目標15 | 陸の豊かさも守ろう | 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。 |
| 目標16 | 平和と公正をすべての人に | 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 |
| 目標17 | パートナーシップで目標を達成しよう | 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。 |
これらの17の目標は、それぞれが独立しているわけではなく、密接に相互関連しています。例えば、質の高い教育(目標4)は、貧困の削減(目標1)やジェンダー平等(目標5)に繋がり、ひいては経済成長(目標8)にも貢献します。一方で、気候変動対策(目標13)を過度に進めると、エネルギーコストが上昇し、貧しい人々の生活を圧迫する可能性(トレードオフ)もあります。SDGs教育では、こうした目標間の複雑な繋がりを理解し、バランスの取れた解決策を考える力を養うことが重要になります。
なぜ今、SDGs教育が重要視されるのか
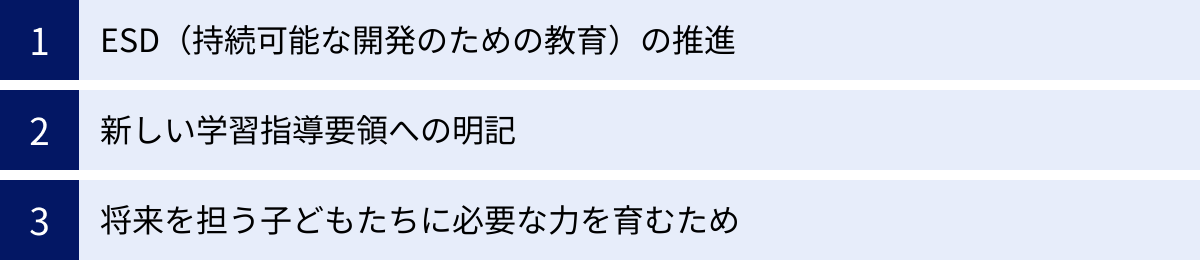
SDGs教育が単なる一過性のブームではなく、現代の教育において不可欠な要素として位置づけられているのには、明確な理由があります。それは、国際的な教育の潮流、国内の教育政策の転換、そして未来社会を生きる子どもたちに求められる能力の変化という、3つの大きな文脈が重なり合っているからです。
ESD(持続可能な開発のための教育)の推進
SDGs教育の重要性を語る上で欠かせないのが、「ESD(Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育)」という概念です。実は、SDGs教育という言葉が広まるずっと以前から、ESDは国際的に推進されてきました。
ESDとは、持続可能な社会の創り手を育む教育のことです。それは、私たちが直面する環境、社会、経済の諸課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組み、それによって新たな価値を創造し、持続可能な社会を実現していくことを目指す学習や活動を指します。ESDは、単に環境問題について学ぶ「環境教育」にとどまらず、人権、平和、開発、多文化共生といった多様なテーマを包括する、より広い概念です。
このESDは、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が中心となって2005年から2014年までを「国連ESDの10年」として推進してきました。そして、2015年にSDGsが採択されると、ESDはSDGs、特に目標4「質の高い教育をみんなに」のターゲット4.7(※)を達成するための鍵として、その重要性が再確認されました。
※ターゲット4.7:「2030年までに、持続可能な開発と持続可能なライフスタイルのための教育、人権、ジェンダー平等、平和と非暴力の文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化の多様性と文化のSDGsへの貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識とスキルを習得できるようにする。」(参照:外務省 JAPAN SDGs Action Platform)
つまり、SDGsが「何を(What)」目指すかという目標(ゴール)であるのに対し、ESDは「どのように(How)」その担い手を育てるかという教育のアプローチや考え方を示しています。SDGs教育は、このESDの理念を土台として、SDGsという明確な17の目標をフレームワークに活用することで、より具体的に、そして世界中の人々と共通の言語で実践しやすくなった教育活動であると言えます。ESDの長年にわたる蓄積があるからこそ、今日のSDGs教育は豊かな内容で展開されているのです。
新しい学習指導要領への明記
SDGs教育の重要性が国内で一気に高まった最大の要因は、新しい学習指導要領への明記です。2017年から2018年にかけて改訂され、小学校(2020年度)、中学校(2021年度)、高等学校(2022年度)から順次全面実施されている学習指導要領では、その前文において、教育の目的として「持続可能な社会の創り手」を育成することが明確にうたわれています。
具体的には、前文に「これからの学校には、(中略)様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と記されています。これは、SDGs教育/ESDの理念が、日本の教育政策の根幹に正式に位置づけられたことを意味します。
この理念は、特定の教科だけで実現されるものではありません。新しい学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」という考え方が重視されています。これは、教育課程を学校内だけで完結させるのではなく、社会や世界の課題と結びつけ、子どもたちが社会の一員としてより良い社会づくりに参画する力を育むことを目指すものです。
この実現のために、各学校には「カリキュラム・マネジメント」が求められます。これは、各教科の学びをバラバラに行うのではなく、教科等を横断した視点で、SDGsの17目標のような現代的な諸課題を関連付けながら、教育活動全体をデザインしていく取り組みです。
例えば、
- 社会科で世界の貧困問題を学び(目標1)、
- 理科で気候変動のメカニズムを学び(目標13)、
- 国語科で多様な文化をテーマにした文学作品を読み解き(目標10)、
- 数学科で食品ロスの統計データを分析し(目標12)、
- 総合的な学習(探究)の時間で、これらの学びを統合し、地域課題の解決策を探究する
といったように、すべての教育活動が「持続可能な社会の創り手」の育成という一つの目標に向かって有機的に連携することが期待されています。このように、SDGs教育は国の教育方針として明確に位置づけられており、すべての学校、すべての教員が取り組むべき重要なテーマとなっているのです。
将来を担う子どもたちに必要な力を育むため
グローバル化、AIの急速な進化、気候変動の深刻化、そしてパンデミック――現代社会は、変化が激しく、将来の予測が極めて困難な「VUCA(ブーカ:変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)」の時代だと言われています。このような時代を生き抜くためには、従来の知識詰め込み型の教育で養われる力だけでは不十分です。
これからの社会で求められるのは、未知の課題に直面した際に、自ら課題を発見し、多様な人々と協力しながら、粘り強く解決策を探究していく力です。具体的には、批判的思考力、創造性、コミュニケーション能力、協働性といった、いわゆる「21世紀型スキル」や「非認知能力」と呼ばれる資質・能力が重要になります。
SDGs教育は、まさにこれらの力を育むための最適な学びのフレームワークを提供します。なぜなら、SDGsが扱う17の課題は、どれも唯一の正解が存在しない複雑な問題ばかりだからです。
例えば、「プラスチックごみを減らす」という課題一つをとっても、
- 消費者はどう行動すべきか?
- 企業はどのような製品開発をすべきか?
- 政府はどのような規制や支援をすべきか?
- プラスチック産業で働く人々の雇用はどうなるのか?
など、様々な立場や利害が絡み合います。これらの課題に取り組む学習プロセスを通じて、子どもたちは、
- 物事を多角的に捉え、本質的な問題を見抜く力
- 異なる意見に耳を傾け、合意形成を図る力
- 失敗を恐れずに挑戦し、試行錯誤を繰り返す力
- 自分たちの活動が社会や世界とどう繋がっているかを想像する力
を自然と身につけていきます。SDGs教育は、子どもたちが未来社会の「良き市民」として、また「責任ある変革の担い手」として、豊かで幸せな人生を歩んでいくために不可欠な「生きる力」そのものを育む教育なのです。それは、単なる社会貢献活動ではなく、子どもたち自身の未来を切り拓くための、最も重要な学びの一つと言えるでしょう。
SDGs教育の目的と育むべき3つの力
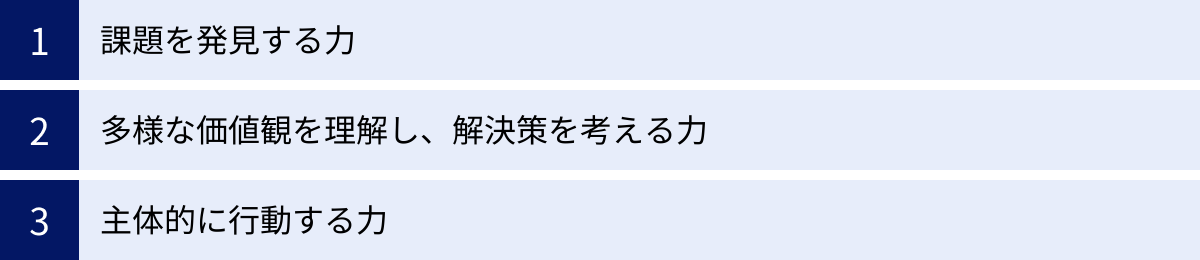
SDGs教育が目指すのは、単に17の目標に関する知識を子どもたちに与えることではありません。その本質的な目的は、持続可能な社会の実現に向けて、自ら考え、判断し、行動できる「チェンジ・メーカー(変革の担い手)」を育てることにあります。そのために、SDGs教育を通じて特に育成すべき力は、大きく分けて「課題を発見する力」「多様な価値観を理解し、解決策を考える力」「主体的に行動する力」の3つに集約されます。
① 課題を発見する力
SDGs教育の第一歩は、地球規模の壮大な目標を、自分たちの足元にある身近な課題として「自分ごと化」する力を育むことから始まります。遠い国の貧困や大規模な環境破壊の話を聞いても、多くの子どもたちはそれを自分に関係のあることだとは感じにくいかもしれません。しかし、SDGsの17の目標は、私たちの日常生活のあらゆる場面に潜んでいます。その繋がりを発見する力が、すべての学びの出発点となります。
この力を育むためには、まず身の回りにある「当たり前」に疑問を持つ視点を養うことが重要です。
- なぜ給食でこんなに食べ残しが出るのだろう?(目標2, 12)
- 使っていない教室の電気がつけっぱなしなのはなぜ?(目標7, 13)
- 遊びの役割が、なんとなく男女で決まっていないだろうか?(目標5)
- 近所の川は昔と比べてきれいなのだろうか?(目標6, 14)
こうした「なぜ?」という小さな問いを立てる習慣こそが、課題発見能力の核となります。教員や保護者は、答えをすぐに教えるのではなく、「どうしてそう思う?」「他にどんなことが関係しているかな?」と問い返すことで、子どもたちの思考を深める手助けができます。
また、信頼できる情報源から正確な情報を収集し、それを読み解く情報リテラシーも不可欠です。新聞やニュース、公的機関が発表するデータ、信頼性の高いウェブサイトなどを活用し、課題の背景にある事実や数値を客観的に捉える訓練が必要です。例えば、「日本の食品ロスは年間約523万トン(参照:農林水水産省・環境省 令和3年度推計値)」という事実を知ることで、給食の食べ残しという身近な問題が、社会全体の大きな課題の一部であることが理解できます。
このように、身近な現象から問いを立て、情報を基にその背景や構造を理解し、より本質的な課題を浮き彫りにする一連のプロセスが「課題を発見する力」です。この力がなければ、その後の思考や行動も的外れなものになってしまいます。
② 多様な価値観を理解し、解決策を考える力
SDGsが扱う課題のほとんどは、唯一の絶対的な正解が存在しない「厄介な問題(Wicked Problem)」です。一つの課題を解決しようとすると、別の新たな問題が生まれたり(トレードオフ)、立場によって何が「正義」かが異なったりします。
例えば、「再生可能エネルギーを増やす(目標7, 13)」という目標は多くの人が賛同するでしょう。しかし、そのために大規模な太陽光パネルを設置すれば、景観が損なわれたり、森林を伐採して生態系に影響を与えたりするかもしれません(目標15とのトレードオフ)。また、建設コストは誰が負担するのか、電気料金への影響はどうなるのかといった経済的な問題も絡んできます。
こうした複雑な状況の中で、最適な解決策を見出すためには、自分とは異なる立場や価値観を持つ人々の意見に耳を傾け、それぞれの背景を理解し、対話を通じて合意形成を図っていく能力が不可欠です。これを「多様な価値観を理解し、解決策を考える力」と呼びます。
この力を育むためには、ディベートやグループディスカッションが有効な手法となります。あるテーマについて、あえて自分とは異なる利害関係者(例:消費者、生産者、企業、行政、NPOなど)の役割を演じて議論することで、物事を多角的に見る視点が養われます。なぜその人はそう主張するのか、その背景にはどのような事情があるのかを想像する経験が、他者への共感力や寛容さを育みます。
さらに、物事の繋がりを体系的に捉える「システム思考」も重要なスキルです。例えば、「安いTシャツを買う」という一つの行動が、生産国の労働者の人権(目標8)や、大量生産・大量廃棄による環境負荷(目標12)、さらには輸送エネルギー(目標13)など、様々な要素と繋がっていることをシステム図などを使って可視化することで、問題の全体像を捉えることができます。
そして、複数の目標達成に同時に貢献する相乗効果(シナジー)のある打ち手を見つけ出すことも重要です。例えば、「地域の子ども食堂を支援する」という活動は、子どもの貧困対策(目標1)や飢餓対策(目標2)になるだけでなく、食品ロスの削減(目標12)、地域のコミュニティ活性化(目標11)、世代間交流の促進など、多くの目標にプラスの影響を与えます。
このように、トレードオフとシナジーの関係性を理解し、様々なステークホルダーとの対話を通じて、部分的最適ではなく全体的最適に近い、バランスの取れた納得解を粘り強く模索していく力が、SDGs時代の問題解決には求められるのです。
③ 主体的に行動する力
どれだけ素晴らしい課題を発見し、画期的な解決策を考えついたとしても、それを行動に移さなければ、世界は何も変わりません。SDGs教育の最終的なゴールは、子どもたちが知識や思考を具体的なアクションに結びつけ、社会に働きかけていく「主体的に行動する力」を育むことです。
ここで言う「行動」とは、必ずしも世界を変えるような大きな活動である必要はありません。むしろ、日常生活の中で自分にできることから始める「スモールステップ」の積み重ねが重要です。節水や節電を心がける、ごみを正しく分別する、地元の食材を買うといった小さな行動の一つひとつが、SDGsの目標達成に繋がっていることを実感させることが、行動へのモチベーションを高めます。
学校現場では、計画(Plan)、実行(Do)、評価・振り返り(Check)、改善(Action)というPDCAサイクルを回す経験を積ませることが非常に有効です。例えば、「学級の食品ロスを減らす」という目標を立て、そのための具体的な計画(ポスター作成、呼びかけ活動など)を立てて実行し、一定期間後にどれだけロスが減ったかをデータで確認し、次の改善策を考える、といった一連のプロジェクト型学習(PBL)が考えられます。
このプロセスを通じて、子どもたちは計画通りに進まない困難に直面したり、仲間と意見がぶつかったりすることもあるでしょう。しかし、そうした試行錯誤の経験こそが、粘り強さや協働性、レジリエンス(回復力)といった非認知能力を鍛え上げます。
さらに、自分たちの取り組みや学びの成果を、ポスター、プレゼンテーション、学校のウェブサイト、地域のイベントなどで積極的に発信する力も、主体的な行動の重要な一部です。発信することで、自分たちの活動を客観的に振り返る機会が生まれるだけでなく、周りの人々(他の生徒、教員、保護者、地域住民など)からの共感や協力を得て、活動の輪を広げていくことができます。自分たちの小さな行動が、他者を動かし、より大きな変化を生み出すかもしれないという手応えは、子どもたちにとって大きな自信となり、さらなる行動への意欲をかき立てるでしょう。知識と思考と行動が一体となったとき、学びは初めて「生きる力」となるのです。
SDGs教育における現状と課題
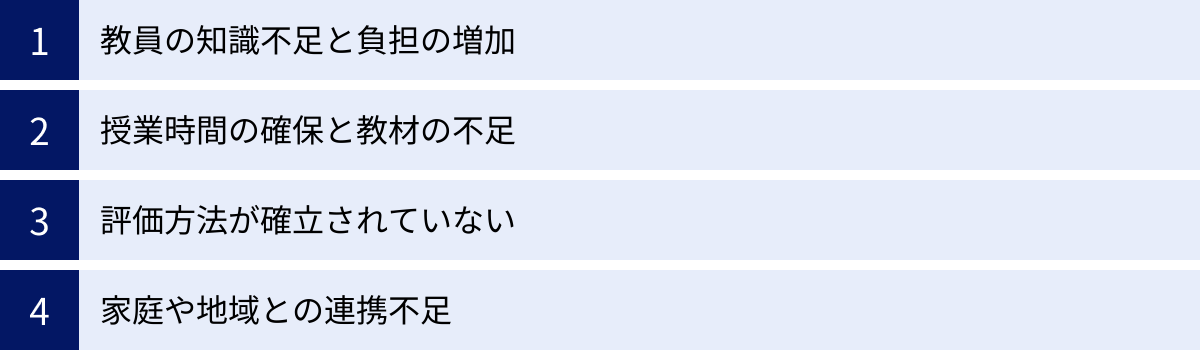
SDGs教育の重要性が認識され、新しい学習指導要領にも明記されたことで、多くの学校現場で取り組みが進められています。しかし、その理想とは裏腹に、教育の最前線では様々な困難や課題が山積しているのも事実です。ここでは、SDGs教育を推進する上での主な4つの課題と、その解決に向けた視点について掘り下げます。
教員の知識不足と負担の増加
SDGs教育を実践する上で、最も大きな壁となっているのが、指導する側の教員の知識不足と、それに伴う業務負担の増加です。SDGsは、貧困、人権、環境、経済、平和など、17の目標が示す通り非常に広範で専門的なテーマを扱います。すべての分野に精通している教員はほとんどおらず、特に自身の専門教科以外のテーマを扱う際には、自信を持って指導することに困難を感じるケースが少なくありません。
また、インターネット上にはSDGsに関する情報や教材が溢れていますが、その中から信頼性が高く、かつ児童生徒の発達段階に適したものを取捨選択する作業は、多大な時間と労力を要します。結果として、既存の授業準備に加えてSDGs関連の学習準備が重くのしかかり、すでに多忙を極める教員の負担をさらに増大させているのが現状です。この負担感が、SDGs教育への積極的な取り組みを躊躇させる一因となっています。
この課題を乗り越えるためには、まず教員一人で全てを抱え込まない仕組みづくりが不可欠です。自治体や教育委員会は、SDGs/ESDに関する体系的な研修プログラムを充実させ、教員が専門知識をアップデートできる機会を確保する必要があります。さらに重要なのは、学校内での教員間の連携です。理科の教員が環境問題の専門知識を共有し、社会科の教員が国際情勢の背景を解説するなど、教科の垣根を越えて協力し合う「チーム・ティーチング」や、共同で教材を開発する体制を築くことが有効です。
加えて、学校外のリソースを積極的に活用する視点も求められます。地域のNPO/NGO、SDGsに取り組む企業、大学の研究者などをゲストティーチャーとして招聘し、専門的な知見や現場のリアルな声を授業に取り入れることで、教員の負担を軽減しつつ、学習の質を高めることができます。
授業時間の確保と教材の不足
次に深刻なのが、SDGs教育を実践するための「時間」と「モノ(教材)」の不足です。日本の学校カリキュラムは、各教科で教えるべき内容が密に詰まっており、SDGs教育のためだけに新たな授業時間を確保することは現実的に困難です。多くの学校では、「総合的な学習(探究)の時間」がその主な受け皿となっていますが、この時間だけで体系的なSDGs教育を行うには限界があります。
また、市販の教材やオンラインで提供される教材は増えてきているものの、自分たちの学校が置かれた地域の実情や、目の前の児童生徒の興味・関心に完全に合致するものは多くありません。特に、地域課題をテーマにした実践的な学習を行おうとすると、既成の教材だけでは対応できず、教員が独自に教材を開発する必要に迫られますが、前述の通り、その時間的余裕がないのが実情です。
この課題に対する最も効果的な解決策は、「カリキュラム・マネジメント」の考え方を徹底することです。つまり、新たな時間を無理に作るのではなく、既存の各教科の単元の中に、SDGsの17目標を関連付けて織り込んでいくのです。例えば、国語で説明文の読解を学ぶ際にSDGs関連の文章を教材として使ったり、数学で統計を学ぶ際にCO2排出量のデータを扱ったりすることで、教科本来の目標を達成しつつ、自然な形でSDGsの視点を導入できます。
教材については、後述するJICAや国連などが提供する質の高い公的な無料教材の存在を、まず教員間で共有し、活用することが第一歩です。その上で、最も価値ある教材は「地域」そのものであるという認識を持つことが重要です。地域の商店街の活性化、放置竹林の問題、伝統文化の継承など、子どもたちの身の回りにある「生きた課題」を教材とすることで、学習はよりリアルで探究的なものになります。
評価方法が確立されていない
SDGs教育が目指すのは、知識の暗記量ではなく、「主体性」「協働性」「思考力」といった、数値化しにくい非認知能力の育成です。しかし、これらの能力をどのように客観的に評価し、成績として記録すればよいのか、その具体的な方法論が確立されていないことが、教員を悩ませる大きな要因となっています。
従来のペーパーテストでは、これらの能力を測ることはできません。評価基準が曖昧なままだと、教員は評価への不安から、結局は知識の伝達に偏った授業に終始してしまったり、そもそも実践に踏み出せなかったりする危険性があります。
この評価の課題に対応するためには、学習の「結果(アウトプット)」だけでなく、「過程(プロセス)」を多角的に評価する視点が必要です。そのための有効な手法として、「ポートフォリオ評価」が挙げられます。これは、生徒が学習過程で作成したレポート、作品、活動記録、振り返りの記述などをファイルに蓄積し、それらを総合的に評価する方法です。個々の成果物だけでなく、学習を通じてどのように思考が深まり、スキルが向上したかという成長の軌跡を捉えることができます。
また、「ルーブリック」の活用も効果的です。ルーブリックとは、評価の観点(例:「課題発見力」「協働性」「表現力」など)と、その達成度レベル(例:「S, A, B, C」や「十分できる, できる, もう少し」など)を具体的な行動記述で示した評価基準表のことです。これを事前に生徒と共有することで、生徒自身が目標を明確に認識し、自己評価を行う助けにもなります。
重要なのは、評価を「序列をつけるためのもの」から「学びを促進するためのもの」へと転換することです。教員による評価だけでなく、生徒同士が評価し合う「相互評価」や、生徒自身が振り返る「自己評価」を組み合わせることで、生徒は自身の学びを客観視し、次へのステップに繋げることができます。
家庭や地域との連携不足
SDGs教育の効果を最大化するためには、学校だけで完結させるのではなく、家庭や地域社会を巻き込んだ三位一体の取り組みが不可欠です。しかし、現状では、学校での学びが家庭での実践に十分に繋がっていなかったり、地域が持つ豊かな教育資源(人材、場所、情報など)が活用されていなかったりするケースが少なくありません。
多くの保護者は、自身が子どもの頃にSDGs教育を受けていないため、その目的や重要性について十分に理解していない場合があります。そのため、子どもが学校で学んできたことを家庭で話しても、関心を持ってもらえなかったり、「そんなことより勉強しなさい」と言われてしまったりすることもあります。
また、地域にはSDGsに関連する活動をしている企業、NPO、自治体の部署、専門知識を持つ市民などが多数存在するにもかかわらず、学校側がその存在を知らなかったり、連携するためのノウハウや人的な余裕がなかったりして、宝の持ち腐れになっている状況が見られます。
これらの連携不足を解消するためには、まず学校から家庭や地域へ、SDGs教育に関する積極的な情報発信を行うことが重要です。学校だよりやウェブサイト、保護者会などの機会を通じて、どのような目的で、どのような活動を行っているのかを丁寧に説明し、理解と協力を求めていく必要があります。親子で参加できるSDGsワークショップや、地域の清掃活動などを企画することも、家庭を巻き込む良いきっかけになります。
地域との連携については、学校と地域社会を繋ぐ「地域連携コーディネーター」のような役割を担う人材や組織の存在が鍵となります。コーディネーターが間に入ることで、学校のニーズと地域のリソースを効果的にマッチングさせ、ゲストティーチャーの派遣や職場体験、共同プロジェクトの実施などを円滑に進めることができます。SDGsは社会全体の目標であるからこそ、その教育も社会全体で支えていくという視点が、今後の発展には不可欠です。
【校種別】学校におけるSDGs教育の取り組み
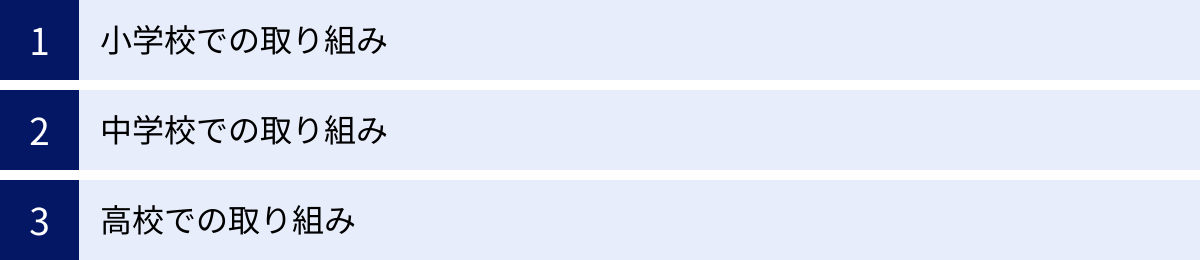
SDGs教育は、子どもたちの発達段階に応じて、そのアプローチや内容を柔軟に変えていく必要があります。ここでは、小学校、中学校、高等学校のそれぞれの校種で、どのような取り組みが考えられるのか、具体的な(架空の)事例を交えながら解説します。
小学校での取り組み
小学校段階でのSDGs教育は、難しい理論よりも、五感を使った体験活動や、身近な生活との関連付けを重視します。子どもたちが「楽しい」「面白い」と感じながら、自然とSDGsの考え方に触れられるような工夫が求められます。
【低学年:生活科・図工】
低学年の子どもたちには、まず自分の身の回りの世界に興味を持つことが大切です。
- 生活科「いきものとなかよし」: 学校の敷地内にいる虫や草花を観察し、絵を描いたりお世話をしたりする活動を通じて、小さな命を大切にする心(目標15)を育みます。なぜここに生き物がいるのか、どうすればもっと増えるのかを考えることで、環境への配慮の芽生えを促します。
- 生活科「やさいをそだてよう」: アサガオやミニトマトなどを育てる活動は、多くの小学校で行われています。ここにSDGsの視点を加えるなら、収穫した野菜をみんなで調理して食べるまでを体験させます。食べ物がどうやってできるのか、その過程にある苦労や喜びを知ることで、食べ物を大切にする気持ち(目標2)が育まれます。また、「のこさずたべようキャンペーン」などを実施し、給食の食べ残し問題(目標12)を意識させることもできます。
【中学年:総合的な学習の時間・社会科】
中学年になると、少しずつ社会の仕組みへと関心が広がっていきます。
- 総合的な学習の時間「わたしたちの町の『水』のひみつ」: 「水」をテーマに、蛇口をひねれば水が出ることの不思議さから探究を始めます。浄水場の仕組みを調べたり、世界の水不足に苦しむ国々の状況を映像で見たりすることで、安全な水が当たり前ではないこと(目標6)を学びます。そして、自分たちにできることとして、歯磨き中の節水や、雨水の活用法などを考え、ポスターで校内に呼びかける活動に発展させます。
- 社会科「スーパーマーケットのひみつ」: 地域のスーパーマーケットを見学し、商品がどこから来ているのかを調べます。多くの食品が外国から長い距離を運ばれてきていること(フードマイレージ)を知り、それが環境に与える影響(目標13)を考えます。その上で、地元で採れた野菜(地産地消)を選ぶことの良さ(目標11, 12)に気づくことができます。
【高学年:理科・総合的な学習の時間】
高学年では、物事をより論理的・多角的に捉える力が育ってきます。
- 理科「電気のつくりと働き」: 火力、水力、原子力、そして太陽光や風力といった再生可能エネルギーなど、様々な発電方法の仕組みと、それぞれのメリット・デメリットを学びます。これが、エネルギー問題(目標7)や地球温暖化問題(目標13)に直結していることを理解し、「持続可能なエネルギー社会を実現するためにはどうすればよいか」というテーマでディスカッションを行います。
- 総合的な学習の時間「みんなにやさしい町づくりプロジェクト」: ユニバーサルデザインの視点で、自分たちの学校や地域に「不便」な場所がないかを調査します。車いす体験やアイマスク体験などを通じて、高齢者や障害のある人の立場を想像し、どこにスロープが必要か、どのような表示があれば分かりやすいかなどを考え、改善案をまとめて地域の自治会や役場に提案する、といった社会参画型の学習(目標10, 11)も可能です。
中学校での取り組み
中学校では、小学校での体験的な学びを土台に、より専門的・探究的な学習へと深化させていきます。社会の仕組みや課題の複雑な構造を、教科の専門性を活かして多角的に分析し、論理的に考察する力が求められます。
- 社会科(地理・歴史・公民)での横断的学習:
- 地理: 私たちが日常的に使うスマートフォンを題材に、その生産過程を追います。内部に使われているレアメタルの産地では、採掘をめぐる紛争や、劣悪な環境で働く児童労働の問題があること(目標1, 8, 16)を学び、グローバルなサプライチェーンの光と影を考察します。
- 歴史: 日本が経験した水俣病や四日市ぜんそくといった公害の歴史を学びます。なぜ公害が起きたのか、被害者はどのような苦しみを味わったのか、そして社会はどのようにそれを乗り越えようとしてきたのかを学ぶことは、現代の環境問題(目標3, 11, 12)を考える上で重要な示唆を与えます。
- 公民: 模擬裁判や模擬国会といった活動を通じて、法の下の平等や民主的な意思決定プロセスの重要性を体験的に学びます。これは、SDGsの土台となる「平和と公正(目標16)」を自分ごととして捉える絶好の機会です。
- 技術・家庭科:
- 技術: プログラミング教育の中で、地域の防災マップアプリや、食品ロス削減を呼びかけるシンプルなウェブサイトを作成するなど、情報技術を活用した課題解決に挑戦します(目標9, 11)。
- 家庭科: 「フェアトレード」認証のついたチョコレートとそうでないチョコレートを食べ比べ、価格の違いの背景にある生産者の労働環境(目標8)や、環境への配慮(目標12)について学びます。消費という日常的な行為が、世界とどのようにつながっているのかを考えさせます。
- 総合的な学習の時間(PBL:Project Based Learning):
地域の企業やNPOと連携し、より実践的な課題解決学習を行います。例えば、「地元の商店街を活性化させるための新商品を開発する」というプロジェクトを立ち上げます。生徒たちは、商店街の現状を調査・分析し、地元の特産品を使い、かつ環境に配慮した(例:包装を減らす、規格外野菜を使う)新商品を企画し、実際に企業にプレゼンテーションします。このプロセスを通じて、マーケティング、コスト計算、協働、プレゼンテーションといった多様なスキルを統合的に学ぶことができます。
高校での取り組み
高等学校では、義務教育で培った基礎学力を基に、生徒自身の興味・関心に基づいた、より専門的で高度な探究活動が中心となります。自らの進路やキャリア形成とSDGsを結びつけ、卒業後に社会で活躍するための実践力を養います。
- 総合的な探究の時間:
高校教育の核となるこの時間で、生徒一人ひとりがSDGsの17目標の中から自身の関心に合ったテーマを設定し、1年間かけて研究を行います。例えば、「マイクロプラスチックによる海洋汚染の実態調査と分解バクテリアの探索(目標14)」「災害時における外国人避難者への情報提供の課題と多言語ツールの開発(目標10, 11)」「地元の耕作放棄地を活用したアグロエコツーリズム事業の提案(目標8, 15)」など、具体的で専門性の高いテーマが考えられます。最終的には、論文にまとめたり、外部のコンテストや学会で発表したりすることを目指します。 - 教科横断型の探究:
- 数学×情報×地理: 各国政府や国連が公開しているCO2排出量、貧困率、ジェンダーギャップ指数などのオープンデータを活用し、統計的な分析を行います。データの相関関係や経年変化をグラフなどで可視化し、課題の現状や要因を客観的に分析・考察する力を養います(目標5, 10, 13)。
- 英語×国際交流: 海外の姉妹校とオンラインで協働し、両国に共通するSDGs課題(例:若者の政治参加、フードロスなど)についてディスカッションや共同調査を行います。文化や価値観の違いを乗り越え、英語というツールを使って合意形成を図る経験は、グローバルなパートナーシップ(目標17)を実践する力を育みます。
- 社会参画活動:
NPOや社会的企業でのインターンシップやボランティア活動を、単位として認定するなどの制度を設けます。社会課題解決の最前線で働く大人たちの姿に触れることは、生徒にとって強烈な刺激となり、自らの将来のキャリアを考える上で、利益追求だけでなく「社会貢献」という視点を持つきっかけになります。子ども食堂の手伝い、地域の環境保全活動、国際協力イベントの運営サポートなど、多様な活動を通じて、教室の学びと実社会を結びつけます。
家庭でできるSDGs教育の始め方
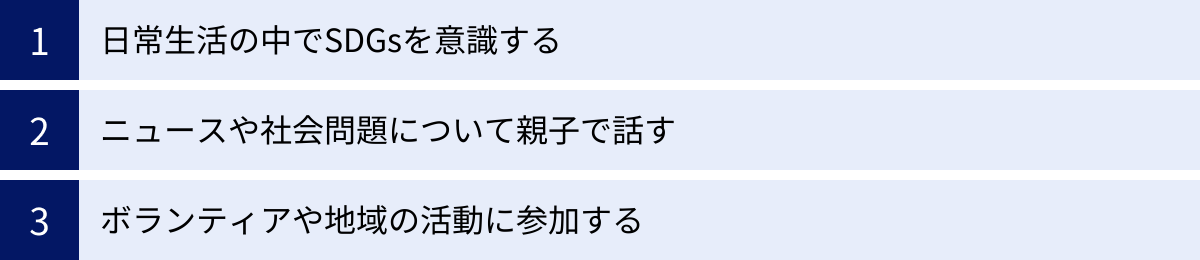
SDGs教育は、学校だけで完結するものではありません。子どもたちが多くの時間を過ごす家庭での取り組みが、学校での学びを深め、習慣として定着させる上で極めて重要です。特別な準備や費用は必要ありません。普段の生活の中に少しだけSDGsの視点を取り入れるだけで、家庭は素晴らしい学びの場になります。
日常生活の中でSDGsを意識する
SDGs教育を家庭で始める最も簡単で効果的な方法は、親子で日常生活の中に隠れているSDGsを探し、意識して行動を変えてみることです。大人が「これはSDGsの目標〇番に関係しているね」と声かけをするだけで、子どもの意識は大きく変わります。
- 「食」に関すること(目標2, 12, 15)
- 買い物: 「今日は地元の野菜を買ってみようか。遠くから運んでくるよりエネルギーを使わないから環境にやさしいんだよ(地産地消)」「この『フェアトレード』って書いてあるチョコは、作った人がちゃんと暮らせるお給料をもらえているしるしなんだ」といった会話をしながら買い物をします。
- 調理・食事: 食べ残しが出ないように、食べきれる量だけ作る・よそうことを徹底します。野菜の皮や芯など、普段捨ててしまう部分もスープの出汁に使うなど、食材を無駄なく使い切る「フードロス削減」を親子で実践します。
- 「モノ」に関すること(目標12, 14)
- 買い物: マイバッグやマイボトルを持参するのは基本のアクションです。何かを買う前には、「本当にこれ、必要かな?」「長く使えるかな?」と親子で話し合う習慣をつけましょう。過剰な包装は断る勇気も大切です。
- ごみ: ごみの分別は、なぜそれが必要なのかを説明しながら一緒に行います。「このペットボトルは、リサイクルされて新しい服や文房具に生まれ変わるんだよ」と伝えることで、面倒な作業も意味のある行動に変わります。
- 「エネルギー・水」に関すること(目標6, 7, 13)
- 節電・節水: 「使わない部屋の電気は消そうね」「歯を磨いている間は水を止めよう」といった声かけを習慣にします。なぜそうするのか、「電気や水を作るのにもたくさんのエネルギーが必要で、それが地球温暖化に繋がるんだよ」と理由をセットで伝えることが重要です。お風呂の残り湯を洗濯や掃除に使うのも、立派なSDGsアクションです。
親子でSDGsクイズを出すのも楽しい方法です。「このリサイクルマークは何に生まれ変わるでしょう?」「世界では、学校に行けない子どもが何人くらいいると思う?」など、クイズ形式で知識を増やし、関心を高めることができます。
ニュースや社会問題について親子で話す
子どもの社会への関心を高め、多角的な視点を養うためには、家庭での対話が欠かせません。子ども向けのニュース番組や新聞などを一緒に見ながら、社会で起きている出来事について話す時間を作りましょう。
重要なのは、親が一方的に知識を教え込むのではなく、子どもの意見や感情を引き出し、一緒に考える姿勢です。
- 「ウクライナで戦争が起きているニュースを見たけど、どうして戦争はなくならないんだと思う?」(目標16)
- 「また大雨で大きな被害が出ているね。地球温暖化と関係があるのかな?私たちにできることは何だろう?」(目標13)
- 「このアニメの主人公、男の子なのにピンクが好きで素敵だね。好きな色に男も女も関係ないよね」(目標5)
こうした問いかけに対して、子どもが何か意見を言ったら、まずは「なるほど、そういう考え方もあるね」「そう感じたんだね」と肯定的に受け止める(傾聴する)ことが大切です。親の価値観を押し付けるのではなく、多様な考え方があることを対話の中で示していくことで、子どもの思考は柔軟になります。
また、世界各国の文化や暮らしを紹介するドキュメンタリー番組や本、映画などに親子で触れるのも良い方法です。自分たちの「当たり前」が、世界では当たり前ではないことを知る経験は、多様性への理解と尊重(目標10)の心を育みます。
ボランティアや地域の活動に参加する
知識として学ぶだけでなく、実際に体を動かして社会と関わる体験は、子どもの心に深く刻まれます。主体的に行動する力を育むために、親子で地域の活動に積極的に参加してみましょう。
- 地域の清掃活動: 公園や海岸のゴミ拾いに参加することで、ポイ捨て問題の深刻さや、自分たちの町をきれいに保つことの重要性を肌で感じることができます(目標11, 14, 15)。「こんなごみが落ちているね」「どうすればごみは減るかな」と話しながら活動することで、学びが深まります。
- フードバンクや子ども食堂のお手伝い: 寄付された食料の仕分けを手伝ったり、食事の配膳を手伝ったりする体験は、日本にも食に困っている人がいるという現実(目標1, 2)や、食品ロスの問題(目標12)を「自分ごと」として捉える強烈なきっかけになります。
- 地域のイベント参加: 国際交流フェスティバルや環境フェア、リサイクル関連のワークショップなど、自治体やNPOが主催するイベントはたくさんあります。まずは気軽な気持ちで参加し、様々な取り組みに触れるだけでも、新たな発見や興味に繋がります。
いきなり本格的なボランティア活動に参加するのが難しければ、まずは赤い羽根共同募金やコンビニのレジ横にある募金箱に、お小遣いの中から少しだけ募金することから始めても構いません。「このお金が、困っている誰かのために役立つんだよ」と伝えることが、社会貢献への第一歩となります。家庭での小さな実践と対話、そして社会との接点を持つ体験。この3つが揃ったとき、SDGs教育は子どもの中に深く根付いていくのです。
SDGs教育に役立つおすすめ教材・ツール5選
SDGs教育を学校や家庭で実践する際、質の高い教材やツールを活用することで、学びはより深く、そして楽しくなります。ここでは、教育現場で広く活用され、信頼性も高いおすすめの教材・ツールを5つ厳選して紹介します。いずれも、それぞれの公式サイトから多くの情報を得ることができます。
① JICA 地球ひろば
【提供元】
独立行政法人国際協力機構(JICA)
【特徴】
JICAは、日本の政府開発援助(ODA)を実施する機関であり、その知見を活かした教育コンテンツを豊富に提供しています。「JICA地球ひろば」は、その拠点となる施設(東京・市ヶ谷)の名称であり、同時にオンラインで提供される教材群の総称でもあります。最大の特徴は、開発途上国の現状や国際協力の現場に関する、リアルで信頼性の高い一次情報に基づいている点です。
【活用方法】
- 教員向け: 授業でそのまま使えるワークシートや指導案、写真・映像資料が無料でダウンロードできます。特に、国際協力の専門家を学校に派遣する「国際協力出前講座」は、生徒が世界の課題を身近に感じる絶好の機会となります。
- 生徒・親子向け: JICA地球ひろばのウェブサイトには、「見てみよう!世界の暮らし」や「世界を知る・学ぶ」といった、子ども向けの分かりやすいコンテンツが満載です。東京・市ヶ谷にある体験型展示施設は、ゲーム感覚で世界の課題を学べる仕掛けが多く、親子でのお出かけにも最適です。
- 参照:JICA地球ひろば 公式サイト
② Edu Town SDGs
【提供元】
東京書籍株式会社
【特徴】
教科書会社である東京書籍が運営する、小中学生向けの学習支援ウェブサイトです。SDGsの17の目標それぞれについて、「なぜこの目標が必要なの?」「私たちにできることは?」といった視点から、イラストや図解を多用して非常にわかりやすく解説しています。調べ学習の導入や、基礎知識の習得に最適です。
【活用方法】
- 生徒の調べ学習に: 生徒が個人やグループで探究学習を進める際の「最初の入口」として非常に役立ちます。各目標のページには、関連する企業の取り組み事例(※一般的な紹介)や動画へのリンクも整理されており、興味を深めるきっかけになります。
- 授業の導入に: 教員が授業の冒頭で、ある目標の概要を説明する際に、このサイトの図解やイラストをプロジェクターで映して見せるなど、視覚的な補助教材として活用できます。複雑な内容をシンプルに伝えたい場合に効果的です。
- 参照:Edu Town SDGs 公式サイト
③ 先生のためのSDGs解説書(国連広報センター)
【提供元】
国際連合広報センター(UNIC Tokyo)
【特徴】
その名の通り、国連が日本の教員のために作成した公式のSDGs解説書です。PDF形式で誰でも無料でダウンロードできます。国際目標であるSDGsの「本家」が提供する資料であるため、情報の正確性と信頼性は群を抜いています。各目標が設定された背景、具体的なターゲットの内容、そして授業で使えるアクティビティのヒントまで、網羅的に記載されています。
【活用方法】
- 教員の自己研修に: SDGsについて指導する前に、教員自身が各目標の本質を深く、そして正しく理解するための必読書と言えます。「なぜこの目標が必要なのか」という根本的な問いに対して、グローバルな視点からの答えがここにあります。
- 授業案作成の土台に: 授業を設計する際の、最も確かな情報源となります。この解説書をベースに、他の教材や地域の実態を組み合わせることで、質の高い授業を構築することができます。
- 参照:国際連合広報センター 公式サイト
④ Think the Earth
【提供元】
一般社団法人Think the Earth
【特徴】
Think the Earthは、コミュニケーションやクリエイティブの力で、環境問題や社会課題への無関心をなくすことを目指すNPOです。彼らが制作する教材は、科学的なデータやロジックだけでなく、美しい写真や映像、心に響くストーリーテリングといった、感性に訴えかけるアプローチが特徴です。
【活用方法】
- 生徒の興味喚起に: 例えば、書籍『1秒の世界』は、世界で1秒間に起きていることをビジュアルで示したもので、生徒が直感的に世界のスケールを感じるきっかけになります。また、ウェブコンテンツ「みずものがたり」は、水の循環を美しい映像と音楽で表現しており、理科や総合的な学習の導入に活用できます。
- 表現活動のヒントに: SDGsに関する探究学習の成果をポスターや映像で表現する際に、Think the Earthのクリエイティブな作品は、生徒たちにとって素晴らしいインスピレーションの源泉となるでしょう。
- 参照:Think the Earth 公式サイト
⑤ THE SDGs アクションカードゲーム X(クロス)
【提供元】
株式会社リバースプロジェクト、株式会社Gab
【特徴】
SDGsの複雑な関係性を、ゲームを通じて楽しく体験できるツールです。プレイヤーは、リソース(お金、時間)を使って様々なアクション(例:「再生可能エネルギーを導入する」)を実行し、SDGsの目標達成を目指します。このゲームの秀逸な点は、あるアクションが、意図した目標だけでなく、他の目標にも良い影響(シナジー)や悪い影響(トレードオフ)を与えるという、SDGsの本質的な構造が巧みに組み込まれていることです。
【活用方法】
- 協働性とシステム思考の育成に: 複数人のチームでプレイするため、自然と対話が生まれ、協働性が育まれます。「このアクションを実行すると、こっちの目標にはマイナスだから、別の方法を考えよう」といった議論を通じて、物事の繋がりを体系的に捉えるシステム思考が養われます。
- アイスブレイクやワークショップに: 中学生から高校生、さらには大人まで、幅広い層が夢中になれるゲーム性を持っています。授業のアイスブレイクや、SDGsワークショップのメインコンテンツとして活用することで、参加者の主体的な学びを促進します。
- 参照:THE SDGs アクションカードゲーム X(クロス)公式サイト
まとめ
本記事では、SDGs教育の基本的な概念から、その重要性、教育現場での具体的な取り組み、そして家庭でできることまで、多角的に解説してきました。
SDGs教育とは、単に17の目標に関する知識を詰め込むためのものではありません。その本質は、地球規模の複雑な課題を「自分ごと」として捉え、多様な人々と協働しながら、より良い未来を創造していくための思考力、判断力、そして行動力を育む「生きるための教育」です。
今、SDGs教育が重要視される背景には、ESD(持続可能な開発のための教育)という国際的な潮流、新しい学習指導要領への「持続可能な社会の創り手」の育成の明記、そして、予測困難な時代を生き抜くために子どもたちに不可欠な力を育むという、社会からの強い要請があります。
その目的は、「課題を発見する力」「多様な価値観を理解し、解決策を考える力」「主体的に行動する力」という3つの力を統合的に育成することにあります。このプロセスを通じて、子どもたちは未来社会の責任ある担い手として成長していきます。
もちろん、教育現場では、教員の負担増、授業時間の確保、評価方法の未確立といった多くの課題が存在します。しかし、これらの課題は、学校、家庭、地域が連携し、それぞれの立場で知恵を出し合い、できることから一歩ずつ行動することで、乗り越えていくことができるはずです。小学校での体験的な学びから、中学校での探究的な学び、そして高校での社会参画へと、発達段階に応じて学びを深化させていくことが重要です。
そして、その学びは学校だけで完結するものではありません。家庭の食卓での会話、地域のイベントへの参加といった一つひとつの経験が、子どもの中にSDGsの精神を根付かせます。
SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」社会の実現は、遠い未来の話ではなく、今日の私たちの選択と行動、そして次代を担う子どもたちへの教育にかかっています。 SDGs教育を通じて育った子どもたちが、多様性を尊重し、地球全体の未来を考えながら行動する市民となったとき、私たちはより持続可能で希望に満ちた社会へと、着実に近づいていくことができるでしょう。