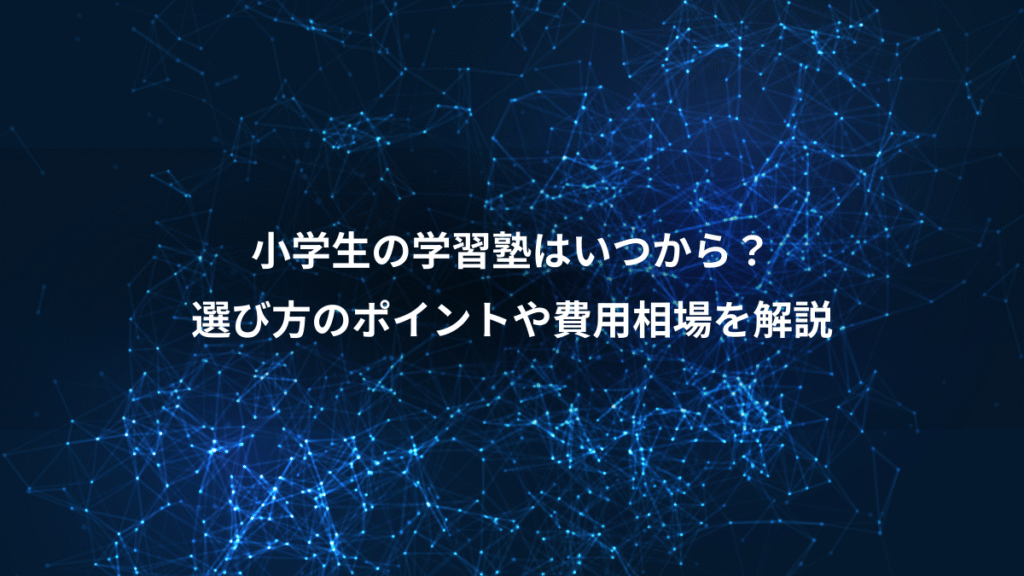小学生のお子さんを持つ保護者の方にとって、「塾にはいつから通わせるべき?」「どんな塾を選べば良いの?」といった悩みは尽きないものです。周りの友達が塾に通い始めると、焦りを感じることもあるかもしれません。しかし、最適なタイミングや塾の形式は、お子さんの性格や学習状況、そしてご家庭の教育方針によって大きく異なります。
この記事では、小学生の学習塾に関するあらゆる疑問にお答えします。通塾を始めるべき具体的なタイミングの目安から、塾に通うことのメリット・デメリット、気になる費用相場、そして最も重要な「失敗しない塾選びの7つのポイント」まで、網羅的に詳しく解説します。
さらに、目的別に分類したおすすめの学習塾や、入塾前に親子で確認しておきたいこと、よくある質問への回答もまとめました。この記事を最後まで読めば、漠然とした不安が解消され、お子さんにとって最適な学習環境を見つけるための具体的な行動計画が立てられるようになります。
目次
小学生はいつから塾に通うのがベスト?
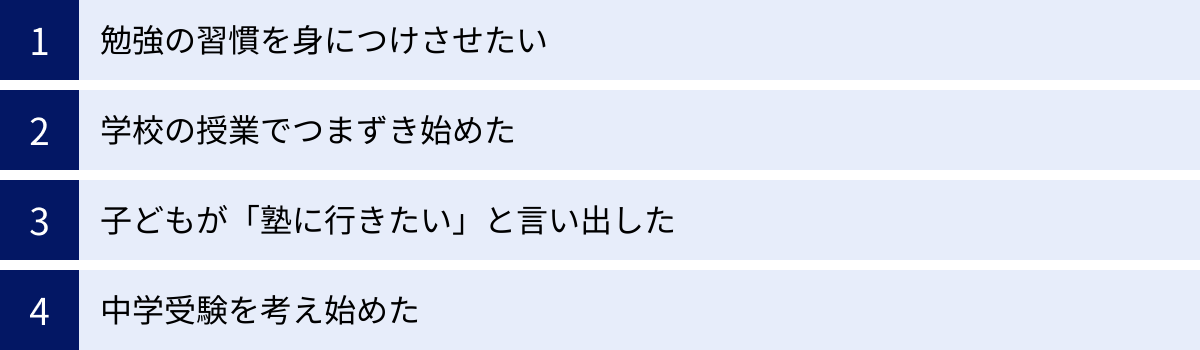
「いつから塾に通わせるか」という問いに、唯一の正解はありません。しかし、一般的な傾向や、学年ごとの発達段階、そして中学受験の有無といった要素から、最適なタイミングを見極めることは可能です。まずは、小学生の通塾に関する現状を把握し、どのようなきっかけで塾通いを始める家庭が多いのかを見ていきましょう。
小学生の通塾率の現状
近年、小学生の学習塾利用はごく一般的な選択肢となっています。文部科学省が実施している「子供の学習費調査」を見ると、その実態がよく分かります。
令和3年度の調査結果によると、学校外活動費のうち「補助学習費(学習塾や家庭教師など)」に支出している公立小学生の割合は、全体で49.8%にものぼります。つまり、公立小学校に通う児童の約半数が、何らかの形で学校外での学習にお金をかけていることになります。学年別に見ると、その割合は学年が上がるにつれて増加する傾向にあります。
- 小学1年生: 25.6%
- 小学2年生: 32.2%
- 小学3年生: 42.1%
- 小学4年生: 51.5%
- 小学5年生: 61.6%
- 小学6年生: 72.5%
参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
このように、高学年、特に小学6年生になると7割以上の児童が塾などを利用しており、中学校進学を目前に控えて学習への意識が高まることがうかがえます。また、これは全国平均の数値であり、都市部、特に中学受験が盛んな地域では、この割合はさらに高くなる傾向にあります。低学年のうちから通塾を開始する早期化の動きも見られ、小学生の学習環境が多様化していることが分かります。
塾に通い始める主なきっかけ
では、保護者や子どもたちは、どのようなタイミングや理由で「塾に通おう」と決めるのでしょうか。主なきっかけは、大きく4つのパターンに分けられます。
勉強の習慣を身につけさせたい
低学年の保護者の方に特に多いのが、「早いうちから学習習慣を定着させたい」という動機です。小学校に入ると、毎日宿題が出されますが、家庭学習の習慣がついていないと「宿題をしなさい!」と親子で毎日言い争いになってしまうことも少なくありません。
塾に通うことで、週に1〜2回、決まった時間に机に向かうというリズムが生まれます。 また、塾から出される宿題が、家庭での学習を促すペースメーカーの役割を果たします。この段階では、難しい勉強をさせるというよりも、「勉強は楽しいもの」「決まった時間に勉強するのは当たり前」という感覚を養うことが主な目的となります。この時期に良い習慣が身につけば、その後の学校生活をスムーズに送るための大きな土台となるでしょう。
学校の授業でつまずき始めた
小学校中学年(3〜4年生)頃になると、学習内容が徐々に高度化・抽象化し、個人差が表れ始めます。算数では割り算の筆算や小数・分数、国語では長文読解や複雑な漢字が登場し、理科や社会といった新しい教科も始まります。
この時期に、「テストの点数が急に下がった」「特定の科目に苦手意識を持っているようだ」「授業が分からないと子どもが口にするようになった」といったサインが見られたときが、塾を検討する一つのタイミングです。学校の授業は集団で行われるため、一度つまずくと、分からないまま授業が先に進んでしまい、苦手意識が雪だるま式に膨らんでしまうことがあります。
塾では、学校で分からなかった部分を丁寧に教えてもらえたり、子どもが理解できるまで繰り返し演習したりできます。 このように、学校の授業を補う「補習」を目的として塾に通い始めるケースは非常に多く見られます。
子どもが「塾に行きたい」と言い出した
意外に多いのが、子ども自身の希望がきっかけとなるケースです。「仲の良い友達が塾に通い始めて楽しそう」「もっと難しい問題にチャレンジしてみたい」など、子どもの口から「塾に行きたい」という言葉が出たら、それは大きなチャンスです。
本人の自発的な意欲は、学習効果を最大限に高めるための最も重要な要素です。 このような場合、子どもは前向きな気持ちで塾通いをスタートできるため、学習内容をスムーズに吸収し、成績向上につながりやすい傾向があります。
ただし、注意点もあります。友達と一緒に行きたいという気持ちが先行している場合、その友達が辞めてしまうと、途端にやる気を失ってしまう可能性もあります。なぜ塾に行きたいのか、塾で何を学びたいのかを親子でじっくり話し合い、子ども自身の学習意欲を確かめることが大切です。
中学受験を考え始めた
小学生が塾に通う最も明確で、かつ大きなきっかけが「中学受験」です。国公立中高一貫校や私立中学校の入試問題は、小学校の教科書レベルをはるかに超える内容が出題されます。特殊算や適性検査型の問題など、家庭学習や学校の授業だけで対策するのは極めて困難です。
そのため、中学受験をすると決めた場合、専門のカリキュラムと豊富な情報を持つ進学塾に通うことが、ほぼ必須の選択肢となります。 中学受験のための準備には、一般的に2〜3年の期間が必要とされるため、多くの家庭では小学3年生の終わり(新4年生になる直前の2月)頃から塾通いをスタートさせます。これが、中学受験における王道のスタート時期と言われています。
【学年別】塾に通い始めるタイミングの目安
子どもの発達段階や学習内容に合わせて、塾に求める役割も変わってきます。ここでは、学年別に通塾を始める際の一般的な目安と目的を解説します。
小学1〜2年生(低学年)
この時期の通塾は、本格的な学力向上というよりも、「学習習慣の定着」と「勉強へのポジティブな意識付け」が主な目的となります。鉛筆の正しい持ち方、ノートの取り方といった基礎的な学習姿勢から、読み・書き・計算といった基礎学力の土台作りを中心に行います。
ゲーム感覚で学べる教材を取り入れたり、子どもを褒めて伸ばす指導をしたりする塾が多く、勉強を「楽しいもの」として認識させることに重きを置いています。無理なく続けられるよう、週1回・1科目から始めるのが一般的です。焦って詰め込むのではなく、まずは学習の土台を築く時期と捉えましょう。
小学3〜4年生(中学年)
小学校の学習内容が本格化し、学力差が生まれやすいのがこの時期です。算数では複雑な計算が、国語では論理的な思考を要する読解問題が増えてきます。学校の授業でつまずきを感じ始めたら、「授業の補習」や「苦手科目の克服」を目的として塾に通い始めるのに適したタイミングです。
また、中学受験を視野に入れるのであれば、この時期からのスタートが最も一般的です。多くの進学塾では、新小学4年生(小学3年生の2月)から中学受験に向けた本格的なカリキュラムを開始します。 このタイミングで入塾することで、無理のないペースで受験に必要な基礎学力を固めていくことができます。
小学5〜6年生(高学年)
この時期になると、通塾の目的は「中学校への準備」と「中学受験対策」の二極化が進みます。
中学受験をしない場合でも、中学校での学習をスムーズにスタートさせるために塾を利用する生徒が増えます。特に、難易度が上がる英語や数学の先取り学習は人気があります。小学校の学習内容を総復習し、中学校の勉強方法に慣れておくことで、入学後の学習面での不安を軽減できます。
一方、中学受験組にとっては、この時期はまさしく正念場です。志望校の過去問演習や弱点補強など、より実践的な対策が中心となります。週のほとんどを塾で過ごす生活になり、学習量も精神的なプレッシャーもピークに達します。もし小学5年生や6年生から中学受験を目指す場合は、かなり集中的な学習が必要になるため、個別指導塾などで遅れをキャッチアップする戦略が有効になることもあります。
中学受験の有無で最適な時期は変わる
ここまで見てきたように、小学生が塾に通い始める最適な時期は、「中学受験をするか、しないか」によって大きく異なります。
- 中学受験をする場合
多くの大手進学塾のカリキュ-ラムは、小学3年生の2月からスタートし、約3年間かけて入試本番に備えるように設計されています。そのため、難関校を目指すのであれば、小学3年生の2月(新4年生)が通塾開始のデッドラインと考えるのが一般的です。もちろん、それ以前から低学年向けのコースで準備を始める家庭もありますが、本格的なスタートはこの時期です。 - 中学受験をしない場合
こちらの場合は、「この時期までに始めなければならない」という明確なデッドラインは存在しません。最も重要なのは、子ども自身や家庭が「必要性を感じたとき」です。学校の授業で分からなくなってきた、本人がもっと勉強したいと言い出した、学習習慣をつけさせたい、など、それぞれの家庭の状況や子どもの様子に合わせて柔軟に判断しましょう。焦って周りに合わせる必要は全くありません。高学年になってから、中学校の準備のために通い始めるというのも、非常に合理的で良いタイミングと言えるでしょう。
小学生が塾に通うメリットとデメリット
塾に通うことは、学力向上や学習習慣の定着など多くのメリットが期待できる一方で、費用や子どもの負担といったデメリットも存在します。入塾を決める前に、両方の側面を冷静に比較検討し、ご家庭の方針とお子さんの状況に合っているかを判断することが重要です。
塾に通う5つのメリット
まずは、小学生が塾に通うことで得られる主なメリットを5つご紹介します。
| メリット一覧 |
|---|
| ① 学習習慣が身につく |
| ② 学校の授業が分かりやすくなる |
| ③ 苦手科目を克服できる |
| ④ 中学受験の専門的な対策ができる |
| ⑤ 同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる |
① 学習習慣が身につく
塾に通う最大のメリットの一つが、規則正しい学習習慣が自然と身につくことです。自宅だけでは、テレビやゲームなどの誘惑が多く、子どもが自主的に勉強時間を確保するのは難しいものです。「宿題はやったの?」と毎日声をかけることに疲れてしまう保護者の方も少なくないでしょう。
塾に通えば、週に数回、決まった時間に強制的に勉強する環境に身を置くことになります。また、多くの塾では毎回宿題が出されるため、それをこなすために家庭での学習時間も確保せざるを得ません。この「塾の授業+宿題」というサイクルを繰り返すうちに、勉強することが生活の一部として定着し、自ら机に向かう習慣が育まれていきます。
② 学校の授業が分かりやすくなる
塾では、学校の授業内容を先取りして学習する「予習型」や、学校で習った内容を復習する「復習型」のカリキュラムが組まれています。
予習型の塾に通えば、学校の授業が「初めて聞く内容」ではなく「塾で一度習った内容」になるため、余裕を持って授業に臨むことができます。 内容が理解できると、授業中に手を挙げて発言する機会も増え、学習に対する自信や積極性につながります。
復習型の塾では、学校の授業で理解が曖昧だった部分を再確認し、知識を確実に定着させることができます。「分かったつもり」を防ぎ、基礎を固めることで、応用問題にも対応できる力が養われます。どちらのタイプであれ、塾での学習が学校の授業の理解を助け、相乗効果を生み出すことは間違いありません。
③ 苦手科目を克服できる
「算数の文章問題だけがどうしても苦手」「漢字を覚えるのが嫌い」など、特定の分野に苦手意識を持つ子どもは少なくありません。学校の集団授業では、一人ひとりの苦手分野に時間を割いて指導することは困難です。
その点、塾、特に個別指導塾では、子どもの苦手な単元や分野に絞って、集中的に指導を受けられます。 なぜその問題が解けないのか、どこでつまずいているのかを講師が丁寧に見つけ出し、子どもが理解できるまで根気強く教えてくれます。学校では質問しづらい内気な子でも、塾の個別指導であれば気軽に質問できるでしょう。苦手科目を克服することは、テストの点数を上げるだけでなく、子どもの自信を取り戻し、勉強全体のモチベーションを高める上で非常に重要です。
④ 中学受験の専門的な対策ができる
中学受験を考えている家庭にとって、これは塾を利用する最大のメリットと言えるでしょう。私立中学や公立中高一貫校の入試では、「つるかめ算」や「流水算」といった特殊算、論理的思考力や表現力を問う適性検査など、学校では一切扱わない特殊な問題が数多く出題されます。
これらの問題に対応するには、専門的な知識と解法テクニックを学ぶ必要があります。進学塾には、長年にわたって蓄積された受験のノウハウ、志望校別の出題傾向の分析データ、そして質の高いオリジナル教材があります。合格に向けて最適化されたカリキュラムに沿って学習を進めることで、効率的に実力を伸ばすことができます。 これは、家庭学習だけでは決して得られない、塾ならではの価値です。
⑤ 同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる
特に集団指導塾の場合、同じ目標を持つ仲間やライバルの存在が、大きな刺激となります。自分一人で勉強していると、つい甘えが出たり、モチベーションが続かなくなったりすることがあります。しかし、塾に行けば、周りの友達が真剣に問題に取り組む姿を見て、「自分も頑張らなければ」という気持ちになります。
テストの成績で一喜一憂したり、難しい問題を一緒に考えたりする中で、連帯感が生まれることもあります。特に長丁場となる中学受験では、共に励まし合える仲間の存在が、苦しい時期を乗り越えるための大きな支えとなるでしょう。学校とは違うコミュニティに所属することは、子どもの社会性を育む上でも良い経験となります。
塾に通う4つのデメリット
一方で、塾通いにはデメリットや注意すべき点もあります。メリットばかりに目を向けるのではなく、これらの点も十分に理解した上で判断することが大切です。
| デメリット一覧 |
|---|
| ① 費用がかかる |
| ② 子どもの負担になる可能性がある |
| ③ 友達と遊ぶ時間が減る |
| ④ 先生との相性が合わない場合がある |
① 費用がかかる
塾に通わせる上で、最も現実的な問題が費用です。入会金や月々の授業料はもちろん、教材費、季節講習費、模試代など、年間を通すとかなりの金額になります。特に、中学受験を目指す進学塾の場合、高学年になると年間100万円を超えることも珍しくありません。
この経済的な負担が、家計を圧迫する可能性があります。塾に通わせることで、他の習い事や家族旅行などを我慢しなければならない状況も考えられます。「本当にその費用に見合う効果が得られるのか」を慎重に検討し、家計の状況と照らし合わせて無理のない範囲で計画を立てる必要があります。
② 子どもの負担になる可能性がある
小学生にとって、学校生活だけでも決して楽ではありません。それに加えて塾の授業や大量の宿題が加わると、子どもが心身ともに疲弊してしまう可能性があります。
平日は学校が終わってから急いで塾へ向かい、帰宅は夜遅く。そこから塾の宿題をこなすと、就寝時間が遅くなり、睡眠不足に陥るケースも少なくありません。睡眠不足は、翌日の学校の授業への集中力低下を招き、本末転倒な結果になりかねません。子どもの体力や性格を考慮し、無理のないスケジュールを組むことが不可欠です。
③ 友達と遊ぶ時間が減る
放課後や休日は、子どもにとって友達と自由に遊び、心身をリフレッシュさせるための貴重な時間です。しかし、塾に通うようになると、その時間が大幅に削られてしまいます。
周りの友達が公園で遊んでいる中、自分だけが塾に行かなければならない状況は、子どもにとって大きなストレスとなることがあります。友達との関わりの中で育まれる社会性やコミュニケーション能力も、子どもの成長にとって非常に重要です。 学習と遊びのバランスをどのように取るか、家庭内でルールを決めたり、子どもと話し合ったりすることが大切です。
④ 先生との相性が合わない場合がある
学習効果は、教える講師の質や子どもとの相性に大きく左右されます。どれだけ評判の良い塾でも、担当になった講師との相性が悪ければ、子どものモチベーションは上がりません。
厳しい指導が合う子もいれば、優しく褒められることで伸びる子もいます。講師の教え方が分かりにくかったり、質問しにくい雰囲気だったりすると、塾に通うこと自体が苦痛になってしまいます。入塾前の体験授業などを利用して、教室の雰囲気だけでなく、実際に指導する講師がどのような人物か、子どもが心を開いて話せそうかを見極めることが非常に重要です。
小学生向け学習塾の費用相場
学習塾を検討する上で、誰もが気になるのが「費用」の問題です。塾にかかる費用は、目的や学年、指導形式によって大きく変動します。ここでは、費用の内訳から具体的な相場、そして少しでも負担を抑えるための方法まで、詳しく解説していきます。
塾にかかる費用の内訳
塾の費用は、月々の授業料(月謝)だけではありません。年間を通して、以下のような様々な費用が発生します。これらのトータルコストを把握しておくことが、後々の「こんなはずではなかった」を防ぐために重要です。
入会金
入塾時に一度だけ支払う費用です。相場は10,000円から30,000円程度が一般的です。ただし、多くの塾では「春の入会キャンペーン」や「兄弟割引」「友達紹介」などで、この入会金が無料または割引になる制度を設けています。入塾を検討する際は、こうしたキャンペーンの有無を必ずチェックしましょう。
月謝(授業料)
毎月継続的に発生する、最も中心的な費用です。月謝は、以下の要素によって大きく変動します。
- 指導形式: 一般的に、「集団指導」よりも「個別指導」の方が高くなります。
- 通塾回数・科目数: 週1回よりも週2回、1科目よりも2科目と、回数や科目数が増えるほど高くなります。
- 学年: 学年が上がるにつれて、授業内容が高度になるため、月謝も上がるのが一般的です。
- 目的: 学校の補習を目的とした塾よりも、中学受験対策を行う進学塾の方が、専門的な指導を行うため高額になります。
教材費
授業で使用するテキストや問題集、プリントなどの費用です。半年ごとや年一括で支払うケースが多く、年間で数千円から、中学受験塾などでは数万円かかることもあります。塾独自のオリジナル教材を使用している場合は、比較的高くなる傾向があります。
季節講習費(夏期・冬期など)
夏休みや冬休み、春休みといった長期休暇中に行われる集中講座の費用です。これは月謝とは別途請求されることがほとんどで、家計にとっては大きな負担となり得ます。
特に、中学受験を控えた小学6年生の夏期講習は、合宿なども含めると20万円以上になることも珍しくありません。受験学年にとっては必須参加となる場合が多いため、あらかじめ予算に組み込んでおく必要があります。
模試代・その他の諸経費
学力の定着度や志望校の合格可能性を測るための模擬試験の費用です。1回あたり3,000円〜6,000円程度が相場です。
その他にも、教室の維持管理費や冷暖房費、通信費といった名目で「諸経費」が毎月数千円程度かかる場合があります。入塾前に、月謝以外にどのような費用が、いつ、どれくらいかかるのかを詳細に確認しておくことが大切です。
【学年・目的別】月謝の平均費用
では、実際に月謝はどれくらいかかるのでしょうか。文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」や、各塾の料金体系を参考に、学年別・目的別の費用相場を見ていきましょう。
学年別の費用相場
公立小学校に通う子どもが支出する学習塾費の年間平均額は、以下のようになっています。これを12ヶ月で割ることで、大まかな月謝のイメージが掴めます。
- 小学1年生: 67,235円(月あたり 約5,600円)
- 小学2年生: 78,518円(月あたり 約6,500円)
- 小学3年生: 98,247円(月あたり 約8,200円)
- 小学4年生: 136,589円(月あたり 約11,400円)
- 小学5年生: 197,364円(月あたり 約16,400円)
- 小学6年生: 285,151円(月あたり 約23,800円)
参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
学年が上がるにつれて費用が大きく増加していることが分かります。特に、中学受験の準備が本格化する小学5、6年生で支出が急増しています。
目的別の費用相場(補習・中学受験)
上記のデータはあくまで平均値であり、実際には塾の目的(補習か、中学受験か)によって費用は大きく異なります。
| 目的・指導形式 | 月謝相場(週1〜2回) | 年間総額の目安(季節講習など含む) |
|---|---|---|
| 学校の補習(個別指導) | 10,000円 〜 25,000円 | 20万円 〜 40万円 |
| 学校の補習(集団指導) | 8,000円 〜 20,000円 | 15万円 〜 30万円 |
| 中学受験(集団指導・低学年) | 15,000円 〜 30,000円 | 25万円 〜 50万円 |
| 中学受験(集団指導・高学年) | 30,000円 〜 60,000円 | 60万円 〜 120万円以上 |
学校の補習を目的とする場合は、個別指導でも集団指導でも、比較的費用は抑えられます。週に通う回数や科目数を調整することで、家庭の予算に合わせやすいでしょう。
一方で、中学受験を目的とする進学塾は、高学年になると通塾日数も増え、授業料は跳ね上がります。小学6年生になると、月謝だけで5万円を超え、季節講習や特別講座、模試代などを含めた年間総額では100万円を超えるケースも決して珍しくありません。中学受験を検討する場合は、この高額な費用を3年間程度支払い続ける覚悟が必要です。
塾の費用を抑える方法
高額になりがちな塾の費用ですが、工夫次第で負担を軽減することも可能です。以下のような方法を検討してみましょう。
- 各種割引制度を活用する: 多くの塾が「兄弟姉妹割引」を設けています。また、成績優秀者には授業料が免除・減額される「特待生制度」がある場合も。入塾時の「入会金無料キャンペーン」や「友達紹介キャンペーン」も積極的に利用しましょう。
- 指導形式を検討する: 一般的に個別指導よりも集団指導の方が費用は安価です。また、校舎を持たないオンライン塾は、さらに費用を抑えられる傾向にあります。
- 通信教育と組み合わせる: 主要な科目は塾で学び、副教科や基礎演習は安価な通信教育やオンライン教材(スタディサプリなど)を活用することで、トータルコストを抑えることができます。
- 必要な講座に絞る: 塾から勧められるがままに、全てのオプション講座を取る必要はありません。子どもの学力や目標に合わせて、本当に必要な講座だけを選択するようにしましょう。
- 自治体の助成制度を調べる: 自治体によっては、所得などの条件に応じて塾代を助成する「塾代助成事業」などを実施している場合があります。お住まいの市区町村のウェブサイトなどで確認してみましょう。
費用だけで塾を決めるのは避けるべきですが、長期的に無理なく通い続けるためにも、こうした工夫を取り入れながら、ご家庭に合ったプランを立てることが重要です。
失敗しない!小学生の学習塾の選び方7つのポイント
数多くある学習塾の中から、我が子にぴったりの一校を見つけ出すのは至難の業です。「有名な塾だから」「友達が通っているから」といった理由だけで安易に決めてしまうと、後悔につながることも少なくありません。ここでは、塾選びで失敗しないための7つの重要なポイントを、具体的なチェック項目とともに解説します。
| 失敗しない塾選びのポイント |
|---|
| ① 塾に通う目的をはっきりさせる |
| ② 塾の指導形式で選ぶ |
| ③ 子どもの性格や学力に合っているか確認する |
| ④ カリキュラムや教材の内容をチェックする |
| ⑤ 講師の質や教室の雰囲気を確かめる |
| ⑥ 無理なく安全に通える場所か確認する |
| ⑦ 必ず体験授業に参加する |
① 塾に通う目的をはっきりさせる
塾選びの全ての出発点となるのが、「何のために塾に通うのか」という目的を明確にすることです。 この目的が曖昧なままでは、適切な塾を選ぶことはできません。まずは親子でじっくりと話し合い、目標を共有しましょう。
- 目的の例:
- 学校の授業についていけるようにしたい(授業の補習)
- 算数の計算ミスをなくしたい(苦手科目の克服)
- 毎日勉強する習慣を身につけたい(学習習慣の定着)
- 中学校の勉強を先取りしたい(中学準備)
- 〇〇中学校に合格したい(中学受験)
例えば、「苦手科目の克服」が目的なら、一人ひとりに合わせて指導してくれる個別指導塾が向いています。一方で、「難関中学への合格」が目的なら、合格実績が豊富な大手進学塾の集団指導が適しているでしょう。このように、目的によって選ぶべき塾のタイプは全く異なります。最初に目的をしっかり定めることで、塾選びの軸がぶれなくなります。
② 塾の指導形式で選ぶ
塾の指導形式は、主に「集団指導」「個別指導」「オンライン塾」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、お子さんの性格や目的に合った形式を選びましょう。
| 指導形式 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |
|---|---|---|---|
| 集団指導 | ・競争環境でやる気が出る ・体系的なカリキュラム ・費用が比較的安い |
・自分のペースで進めない ・質問しにくい場合がある ・授業についていけないリスク |
・負けず嫌いで競争を楽しめる子 ・周りの影響を受けやすい子 ・決められたペースで学習できる子 |
| 個別指導 | ・自分のペースで学べる ・苦手分野を集中対策できる ・質問しやすい環境 |
・費用が高い傾向にある ・競争意識が芽生えにくい ・講師の質にばらつきが出やすい |
・マイペースで学習したい子 ・特定の苦手科目がある子 ・内気で質問するのが苦手な子 |
| オンライン塾 | ・場所や時間を選ばない ・費用が比較的安い ・有名講師の授業も受けられる ・送迎が不要 |
・自己管理能力が必要 ・モチベーション維持が課題 ・すぐに質問できない場合も |
・自宅で集中して学習できる子 ・自主性を持って取り組める子 ・近くに通いたい塾がない子 |
集団指導塾の特徴
学校のクラスのように、1人の講師が10〜30人程度の生徒に対して一斉に授業を行う形式です。決められたカリキュラムに沿って授業が進むため、体系的な知識を効率よく学ぶことができます。ライバルの存在が良い刺激となり、競争心が高いお子さんには最適な環境です。一方で、授業のペースが速く、一度つまずくと遅れを取り戻すのが難しいというデメリットもあります。
個別指導塾の特徴
講師1人に対して生徒が1〜3人程度の少人数で指導を受ける形式です。最大のメリットは、一人ひとりの学力やペース、目標に合わせたオーダーメイドの指導が受けられること。 苦手科目の克服や、特定の単元の集中学習に非常に効果的です。ただし、集団指導に比べて費用は高くなる傾向があります。
オンライン塾の特徴
近年急速に普及しているのが、インターネットを利用したオンラインでの指導です。録画された映像授業を視聴するタイプや、リアルタイムで双方向のやり取りができるライブ授業タイプなどがあります。校舎を持たないため費用が安く、地方にいながら都市部の有名講師の授業を受けられるのが大きな魅力です。ただし、学習を進めるには高い自己管理能力が求められます。
③ 子どもの性格や学力に合っているか確認する
塾は子ども自身が通う場所です。そのため、子どもの性格に合っているかどうかは非常に重要な要素です。
- 競争好きで負けず嫌いな子 → 集団指導塾で仲間と切磋琢磨する環境が向いているかもしれません。
- マイペースでじっくり考えたい子 → 個別指導塾で自分のペースを尊重してもらう方が力を発揮しやすいでしょう。
- 人見知りで質問が苦手な子 → マンツーマンに近い個別指導塾の方が、安心して学習に取り組めます。
また、塾のレベルとお子さんの現在の学力が合っているかも必ず確認しましょう。簡単すぎれば退屈してしまい、難しすぎれば自信を失って勉強嫌いにつながります。「少し頑張ればついていける」くらいのレベルの塾を選ぶのが理想です。
④ カリキュラムや教材の内容をチェックする
塾によって、カリキュラムの方針や使用する教材は様々です。
- カリキュラム: 学校の授業を先取りする「予習型」か、復習を重視する「復習型」か。中学受験塾であれば、志望校のレベルや出題傾向に合ったカリキュラムになっているかを確認します。
- 教材: 学校の教科書に準拠した教材か、塾が独自に開発したオリジナル教材か。特にオリジナル教材の場合、その内容がお子さんのレベルに合っているか、解説は分かりやすいかなどを、実際に手に取って確認することをおすすめします。
⑤ 講師の質や教室の雰囲気を確かめる
子どもの学習意欲を左右する最大の要因は、講師の存在です。
- 講師の質: 講師は学生アルバイトが中心か、経験豊富なプロの正社員講師か。講師の交代は頻繁にあるか。教え方の上手さだけでなく、子どものやる気を引き出す力や、親身に相談に乗ってくれるかも重要なポイントです。
- 教室の雰囲気: 教室は清潔で整理整頓されていますか?生徒たちは集中して学習に取り組んでいますか?あるいは活気のある雰囲気ですか?自習室の有無やその利用しやすさもチェックしましょう。子どもが「この場所で勉強したい」と思えるような、前向きな雰囲気が感じられるかが大切です。
⑥ 無理なく安全に通える場所か確認する
塾通いは長期間にわたることもあります。無理なく通い続けられる立地であることは、意外と見落としがちな重要ポイントです。
- 通塾の利便性: 自宅からの距離はどれくらいか。徒歩、自転車、電車など、子どもが一人で安全に通える手段があるか。
- 安全性: 塾の周りの環境は安全か。夜遅くなった場合の帰り道は、人通りが多く明るいか。
- 安全対策: 多くの塾では、子どもが塾に入室・退室した際に、保護者のスマートフォンにメールなどで通知が届くシステムを導入しています。こうした安全対策の有無も確認しておくと安心です。
⑦ 必ず体験授業に参加する
ここまでに挙げた6つのポイントを最終的に確認する上で、最も重要なのが「体験授業」です。 パンフレットやウェブサイトの情報、口コミだけでは、実際の塾の姿は分かりません。
必ず親子で体験授業に参加し、以下の点をご自身の目と耳で確かめてください。
- 子ども自身の感想: 授業は分かりやすかったか?楽しかったか?先生は質問しやすかったか?「また行きたい」と思えるか?
- 保護者の視点: 講師の教え方や生徒への接し方はどうか?教室の雰囲気はどうか?他の生徒の様子はどうか?
可能であれば、複数の塾の体験授業に参加し、比較検討することをおすすめします。 実際に体験することで、それぞれの塾の長所・短所が明確になり、お子さんにとって本当に相性の良い塾を見つけることができます。
目的別|小学生におすすめの学習塾15選
ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、目的別に小学生におすすめの学習塾を具体的に紹介します。各塾の公式サイトなどで公開されている客観的な情報に基づき、その特徴をまとめました。塾選びの際の比較検討の材料としてご活用ください。
※紹介する順番は優劣を示すものではありません。料金やコースの詳細は、各塾の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
【中学受験対策】に強い塾5選
中学受験は、情報戦とも言われます。豊富な合格実績と専門的なカリキュラムを持つ大手進学塾が、合格への近道となることが多いです。ここでは、特に難関中学への合格実績で知られる塾を中心に紹介します。
| 塾名 | 指導形式 | 特徴 |
|---|---|---|
| SAPIX小学部 | 集団指導 | 難関校に圧倒的な実績、復習中心の授業スタイル、思考力を鍛えるオリジナル教材 |
| 日能研 | 集団指導 | 全国最大級の規模、豊富なデータに基づく進路指導、中堅〜難関まで幅広く対応 |
| 四谷大塚 | 集団指導 | 定評ある基幹教材「予習シリーズ」を使用、提携塾(YTnet)が全国に多数 |
| 早稲田アカデミー | 集団指導 | 「本気でやる子を育てる」熱血指導、体育会系な雰囲気、難関・上位校に強い |
| 浜学園 | 集団指導 | 関西を拠点とする最難関受験塾、徹底した復習主義と厳しい指導 |
① SAPIX小学部
御三家をはじめとする最難関中学への圧倒的な合格実績で知られる進学塾です。授業はディスカッション形式を取り入れ、その場で考えさせることを重視。家庭での復習を前提とした「復習中心主義」のカリキュラムと、思考力を徹底的に鍛えるオリジナル教材「サピックスメソッド」が特徴です。競争が非常に激しく、クラス昇降も頻繁に行われるため、競争心旺盛で自律的に学習できる子に向いています。(参照:SAPIX小学部 公式サイト)
② 日能研
全国に教室を展開する、中学受験塾の最大手の一つ。「未来への学び」をコンセプトに、子どもたちが自ら学ぶ楽しさを発見できるような指導を心がけています。長年の実績から蓄積された膨大な受験データに基づいた、精度の高い進路指導が強み。全国規模で実施される「全国公開模試」は、自身の立ち位置を知る上で重要な指標となります。中堅校から難関校まで、幅広い層の生徒に対応しています。(参照:日能研 公式サイト)
③ 四谷大塚
中学受験界のバイブルとも言われる教材「予習シリーズ」を開発・発行していることで有名です。この教材は、多くの塾で採用されており、質の高さに定評があります。自社の直営校舎に加え、「YTnet」という提携塾のネットワークを全国に展開しており、地方にいながら四谷大塚のカリキュラムとテストを受けることが可能です。週に一度の「週テスト」で学習内容の定着度を測りながら、着実に学力を伸ばしていくシステムです。(参照:四谷大塚 公式サイト)
④ 早稲田アカデミー
「本気でやる子を育てる」というキャッチフレーズの通り、講師陣の熱意あふれる指導が特徴です。授業は活気があり、生徒のやる気を引き出すための声かけや演出も多く、体育会系と評されることもあります。難関中学校への合格実績も豊富で、特に早慶附属中などの対策に定評があります。合宿やイベントも多く、生徒と講師の一体感が強い塾です。元気で活発、熱い雰囲気が好きな子に合うでしょう。(参照:早稲田アカデミー 公式サイト)
⑤ 浜学園
主に関西地方で最難関中学への圧倒的な実績を誇る進学塾で、近年は関東にも進出しています。「講義→家庭学習→復習テスト」という学習サイクルを徹底する復習主義を貫いています。講師陣は厳しい採用基準と研修をクリアしたプロフェッショナルで、緊張感のある質の高い授業が展開されます。宿題の量も多く、厳しい環境で自分を追い込みたい、高い目標を持つ生徒向けの塾です。(参照:浜学園 公式サイト)
【授業の補習・苦手克服】に強い塾5選
学校の授業のフォローや苦手科目の克服が目的の場合、一人ひとりのペースに合わせてくれる個別指導塾がおすすめです。ここでは、全国に教室を展開し、実績のある個別指導塾を紹介します。
| 塾名 | 指導形式 | 特徴 |
|---|---|---|
| 個別教室のトライ | 個別指導(マンツーマン) | 完全マンツーマン指導、AIによる学習診断、全国No.1の教室数 |
| 東京個別指導学院 | 個別指導(1対1 or 1対2) | ベネッセグループ、担当講師を選べる制度、オーダーメイドのカリキュラム |
| 明光義塾 | 個別指導 | 「自立学習」を促す指導スタイル、対話を通じて「分かったつもり」を防ぐ |
| スクールIE | 個別指導(1対1 or 1対2) | 個性診断テストに基づいた指導、完全オーダーメイドのテキスト作成 |
| ITTO個別指導学院 | 個別指導 | 講師1人対生徒3人までが基本、手頃な価格設定、独自開発の教材 |
① 個別教室のトライ
「家庭教師のトライ」で培ったノウハウを活かした、完全マンツーマンの個別指導塾です。講師が常に隣にいるため、いつでも質問でき、きめ細やかな指導が受けられます。AIを活用した学習診断で苦手分野を特定し、効率的な学習プランを提案してくれるのも特徴。全国に多数の教室があり、通いやすいのも魅力です。(参照:個別教室のトライ 公式サイト)
② 東京個別指導学院
ベネッセグループが運営する個別指導塾。講師1人に対して生徒は最大2人まで。事前に複数の講師の授業を受けて、自分に最も合う講師を指名できる「担当講師制度」があり、相性のミスマッチを防げます。豊富な情報力を活かし、一人ひとりの目標に合わせたオーダーメイドのカリキュ-ラムを作成してくれます。(参照:東京個別指導学院 公式サイト)
③ 明光義塾
個別指導塾のパイオニア的存在で、全国に多数の教室を展開しています。ただ答えを教えるのではなく、生徒自身が考え、答えを導き出す「自立学習」の力を育むことを重視しています。講師との対話を通じて、生徒が「分かったこと」を自分の言葉で説明するプロセスを取り入れ、「分かったつもり」を防ぎます。(参照:明光義塾 公式サイト)
④ スクールIE
「やる気スイッチ」のCMでおなじみの個別指導塾。独自の「個性診断テスト」で子どもの性格や学習習慣、生活習慣を分析し、その結果に基づいて相性の良い講師を選定し、指導方法を最適化します。さらに、その診断結果と学力診断に基づいて、一人ひとり専用のオーダーメイドテキストを作成してくれるのが最大の特長です。(参照:スクールIE 公式サイト)
⑤ ITTO個別指導学院
全国に1,000校舎以上を展開する個別指導塾。講師1人に対して生徒3人までを基本とし、解説を受ける時間と自分で問題演習する時間のバランスを取った指導を行います。個別指導でありながら比較的リーズナブルな料金設定も魅力の一つ。定期テスト対策にも力を入れています。(参照:ITTO個別指導学院 公式サイト)
【オンライン】で学べる塾・教材5選
時間や場所の制約を受けずに学習したい、費用を抑えたいというニーズに応えるのがオンラインの学習サービスです。映像授業タイプから個別指導タイプまで、多様なサービスが登場しています。
| サービス名 | 形式 | 特徴 |
|---|---|---|
| スタディサプリ | 映像授業 | 超有名講師の授業が見放題、圧倒的な低価格、基礎から応用までカバー |
| スマイルゼミ | タブレット教材 | ゲーム感覚で楽しく学べる、自動丸付け機能、タブレット1台で完結 |
| Z会 | 通信教育(紙・タブレット) | 質の高い教材で定評、思考力を養う問題が豊富、中学受験コースもあり |
| 進研ゼミ小学講座 | 通信教育(紙・タブレット) | 「赤ペン先生」の添削指導が特徴、キャラクターと一緒に楽しく学べる |
| トウコベ | オンライン個別指導 | 現役東大生・東大院生が講師、質の高い指導を全国どこでも受けられる |
① スタディサプリ
リクルートが運営する映像授業サービス。月額数千円という圧倒的な低価格で、小学校4年生から高校生までの主要科目の授業動画が見放題です。テレビ出演などもする超有名カリスマ講師陣による授業は、「分かりやすい」と評判です。基礎レベルから応用レベルまで網羅しており、子どものペースで先取り学習やさかのぼり学習が自由にできます。(参照:スタディサプリ 公式サイト)
② スマイルゼミ
専用のタブレット端末を使って学習する通信教育サービス。アニメーションやゲーム的な要素が豊富で、子どもが楽しみながら学習に取り組める工夫が満載です。問題を解くと自動で丸付けをしてくれるため、保護者の負担も軽減されます。学習データが記録され、子どもの理解度に合わせて最適な問題が出題されるのも魅力です。(参照:スマイルゼミ 公式サイト)
③ Z会
古くから質の高い教材で定評のある通信教育の老舗。単なる知識の暗記ではなく、物事の本質を理解し、自ら考える力を養うことを重視した良質な問題が多く含まれています。小学生コースでは、タブレットコースと紙の教材コースを選択可能。中学受験コースもあり、難関校を目指すためのハイレベルな学習にも対応しています。(参照:Z会 公式サイト)
④ 進研ゼミ小学講座
ベネッセコーポレーションが提供する、言わずと知れた通信教育サービス。「チャレンジ」(紙教材)と「チャレンジタッチ」(タブレット教材)から学習スタイルを選べます。長年の特徴である「赤ペン先生」による丁寧な添削指導は、子どものやる気を引き出します。可愛らしいキャラクターと一緒に学習を進めるなど、子どもを飽きさせない工夫が随所に凝らされています。(参照:進研ゼミ小学講座 公式サイト)
⑤ トウコベ
講師が全員、現役の東大生・東大院生というオンライン個別指導サービスです。採用率15%以下の厳しい選考を突破した優秀な講師から、マンツーマンで質の高い指導を受けられます。自身の難関大合格経験に基づいた、効率的な勉強法や思考法を学べるのが大きな強み。首都圏以外の地域に住んでいても、国内トップクラスの頭脳を持つ講師の指導を受けられるのが魅力です。(参照:トウコベ 公式サイト)
入塾前に親子で確認しておきたいこと
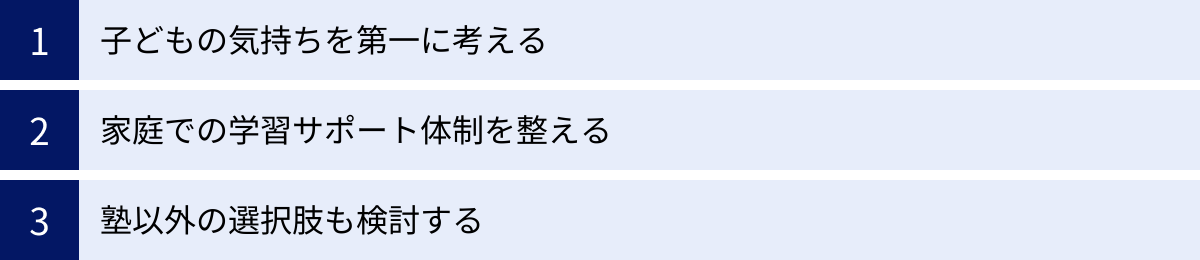
最適な塾を見つけ、いざ入塾!となっても、それで安心ではありません。塾の効果を最大限に引き出し、子どもが健やかに学び続けるためには、入塾後の家庭での関わり方が非常に重要になります。ここでは、入塾を決める前に、親子でしっかりと確認・準備しておきたい3つのことを解説します。
子どもの気持ちを第一に考える
塾に通うのは、親ではなく子ども自身です。どれだけ親が「この塾は素晴らしい」と思っても、子どもにやる気がなければ、その効果は半減してしまいます。親の期待や不安を押し付ける形で塾を決めるのは、絶対に避けなければなりません。
入塾を検討する段階で、まずは「なぜ塾に通うのか」という目的を親子で共有しましょう。「中学受験に挑戦して、あの中学校に行きたいね」「算数が得意になったら、もっと学校が楽しくなるかもね」といった形で、子ども自身が前向きな目標を持てるように対話することが大切です。
もし子どもが塾に行くことを嫌がっている場合は、その理由を頭ごなしに否定せず、丁寧に耳を傾けましょう。「友達と遊ぶ時間がなくなるのが嫌だ」「勉強ばかりしたくない」という気持ちは、子どもにとって自然なものです。その気持ちを受け止めた上で、「週に1回だけ頑張ってみない?」「この曜日なら遊ぶ時間も作れるよ」など、折り合いのつく提案を探っていく姿勢が求められます。
最終的に「この塾で頑張ってみたい」と子ども自身が納得してスタートを切れるかどうか。 これが、長い塾生活を乗り切るための最も重要な土台となります。
家庭での学習サポート体制を整える
「塾に通わせれば、あとはお任せで安心」と考えてしまうのは危険です。塾はあくまで学習をサポートする場所であり、学力を定着させる主役は家庭学習です。 塾の効果を最大化するためには、家庭での適切なサポートが不可欠になります。
具体的には、以下のようなサポート体制を整えておきましょう。
- 学習環境の整備: 子どもが集中して勉強できる静かなスペースを確保する。必要な文房具を揃えるなど、物理的な環境を整えます。
- 宿題の進捗管理: 塾の宿題はきちんとやっているか、声かけや確認をします。ただし、ガミガミ言うのではなく、「今日の宿題はどこまで進んだ?」と寄り添う姿勢が大切です。
- 丸付けと間違い直し: 特に低学年のうちは、宿題の丸付けは親が行う必要があります。間違えた問題は、すぐに答えを教えるのではなく、「どこで間違えたのかな?」「もう一度教科書を見てみようか」と、子どもが自分で考えるのを助けるヒントを与えましょう。このプロセスが学力定着につながります。
- 生活リズムの管理: 塾で夜遅くなる日も、できるだけ早く夕食を食べさせ、十分な睡眠時間を確保できるよう配慮します。栄養バランスの取れた食事や、リフレッシュできる時間を作ることも、親の重要な役割です。
ただし、サポートと過干渉は紙一重です。子どもの学習に口を出しすぎると、子どもの自主性を奪い、親子関係が悪化する原因にもなりかねません。適度な距離感を保ちながら、子どもが困っているときに手を差し伸べる「伴走者」としてのスタンスを心がけましょう。
塾以外の選択肢も検討する
学力を向上させる方法は、塾だけではありません。子どもの性格や家庭の状況によっては、塾以外の選択肢の方が合っている場合もあります。入塾を決める前に、他の選択肢のメリット・デメリットも理解し、比較検討することが大切です。
家庭教師
家庭教師は、講師が自宅に来て、完全マンツーマンで指導してくれるサービスです。
- メリット:
- 完全オーダーメイド指導: 子どもの学力や性格に100%合わせた指導が受けられます。
- 通塾の負担がない: 自宅で受けられるため、送迎の手間や移動時間がかかりません。
- 質問しやすい: 常に講師が隣にいるため、どんな些細なことでも質問しやすい環境です。
- デメリット:
- 費用が高い: 一般的に、塾よりも時間あたりの料金は高額になります。
- 講師との相性が全て: 講師との相性が合わない場合、変更が難しいこともあります。
- 競争環境がない: ライバルの存在による刺激はありません。
通信教育
自宅に送られてくる教材や、タブレットなどを使って学習を進める方法です。
- メリット:
- 費用が安い: 塾や家庭教師に比べて、費用を大幅に抑えられます。
- 自分のペースで学習できる: 時間や場所に縛られず、好きな時に好きなだけ学習できます。
- 学習習慣の定着: 毎月教材が届くことで、学習のペースメーカーになります。
- デメリット:
- 高い自己管理能力が必要: 強い意志がないと、教材を溜め込んでしまいがちです。
- モチベーション維持が難しい: 一人で学習するため、やる気を維持するのが大変です。
- 質問がすぐにできない: 疑問点をその場で解決することが難しい場合があります。
これらの選択肢も含めて、「我が子にとって、そして我が家にとって、どの学習スタイルが最適か」という視点で総合的に判断することが、後悔のない選択につながります。
小学生の塾に関するよくある質問

最後に、小学生の塾に関して、保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
塾に行っているのに成績が上がらない場合はどうすればいい?
これは多くの保護者の方が抱える悩みです。まず、焦らずに原因を分析することが重要です。考えられる原因はいくつかあります。
- 塾のレベルが合っていない: 授業が難しすぎてついていけていない、あるいは簡単すぎて物足りない可能性があります。
- 学習方法に問題がある: 塾の授業を聞いているだけで満足してしまい、家庭での復習や宿題が疎かになっている。「分かったつもり」で終わっているケースです。
- 講師との相性が悪い: 質問しにくい、教え方が分かりにくいなど、講師との関係がうまくいっていない可能性があります。
- 子どもにやる気がない: そもそも本人が塾に行く目的を見失っていたり、他にやりたいことがあったりする場合です。
対策としては、まず塾の担当講師に面談を申し込み、塾での学習状況や授業態度について詳しく聞くことから始めましょう。その上で、家庭での学習習慣を見直したり、塾のクラスやコースの変更を相談したりします。それでも改善が見られない場合は、指導形式の変更(集団指導から個別指導へなど)や、思い切って転塾を検討することも必要です。
塾の宿題はどれくらいの量ですか?
宿題の量は、塾の目的や方針、学年によって大きく異なります。
- 補習塾の場合: 学校の宿題と合わせても、1日30分〜1時間程度で終わる量であることが多いです。学習習慣をつけることが目的なので、無理のない範囲で設定されています。
- 中学受験塾の場合: かなり多くの宿題が出されます。特に高学年になると、平日は毎日2〜3時間、休日はそれ以上の時間を宿題に費やすことも珍しくありません。授業で習ったことを定着させるために、大量の演習が必要になるためです。
入塾を検討する際には、体験授業の際などに「平均的な宿題の量はどれくらいですか?」「宿題を終えるのに、皆さんどれくらい時間をかけていますか?」と具体的に質問しておくことをおすすめします。
途中で塾をやめることはできますか?
はい、もちろん途中で退塾することは可能です。ただし、手続きに関しては塾の規約に従う必要があります。
一般的には、「退塾を希望する月の前月〇日までに、所定の用紙で届け出ること」といったルールが定められています。これを過ぎてしまうと、翌月分の授業料が発生してしまう場合があるので注意が必要です。入塾時に受け取る規約などを必ず確認しておきましょう。
また、子どもが「塾をやめたい」と言い出したときは、すぐに手続きをするのではなく、まずはその理由をじっくり聞くことが大切です。一時的な感情なのか、解決できる問題があるのかを見極め、塾の講師にも相談してみましょう。安易な退塾は、根本的な問題の解決にならない場合もあります。
勉強が嫌いな子でも塾に通えますか?
はい、通えます。むしろ、勉強が嫌いな子にこそ、適切な塾選びが重要になります。勉強が嫌いになってしまった原因は、「授業が分からない」「問題が解けない」といった、つまづきの経験が積み重なっていることが多いです。
このようなお子さんを、いきなり競争の激しい進学塾に入れるのは逆効果です。まずは、小さな成功体験を積み重ね、「自分にもできる!」という自信を取り戻させてくれる場所を選ぶべきです。具体的には、以下のような塾がおすすめです。
- 褒めて伸ばす方針の個別指導塾: 一人ひとりのペースに合わせて、できるまで丁寧に教えてくれ、少しでもできたら大いに褒めてくれるような塾。
- ゲーム感覚で学べるオンライン教材: 楽しみながら学習に取り組むうちに、自然と知識が身につくようなサービス。
勉強への苦手意識を克服するには時間がかかります。焦らず、子どものペースに寄り添ってくれる環境を探してあげることが、勉強嫌いを克服する第一歩となるでしょう。
まとめ
小学生の学習塾選びは、お子さんの将来にも関わる重要な決断です。最適な通塾開始時期は、中学受験をするなら小学3年生の2月、補習目的ならば家庭で必要性を感じたときが目安となります。
塾には学習習慣の定着や苦手克服といったメリットがある一方で、費用や子どもの負担といったデメリットも存在します。これらを総合的に判断し、ご家庭の方針と照らし合わせることが大切です。
失敗しない塾を選ぶためには、
- 塾に通う目的を明確にする
- 子どもの性格に合った指導形式を選ぶ
- 必ず体験授業に参加し、子ども自身の意思を確認する
といった点が特に重要です。
そして何より忘れてはならないのは、塾はあくまで学習をサポートするツールの一つであるということです。塾に任せきりにせず、家庭での学習サポートや、家庭教師・通信教育といった他の選択肢も視野に入れ、お子さん自身が最も前向きな気持ちで学習に取り組める環境を整えてあげること。それが、お子さんの学力を真に伸ばすための、一番の近道と言えるでしょう。