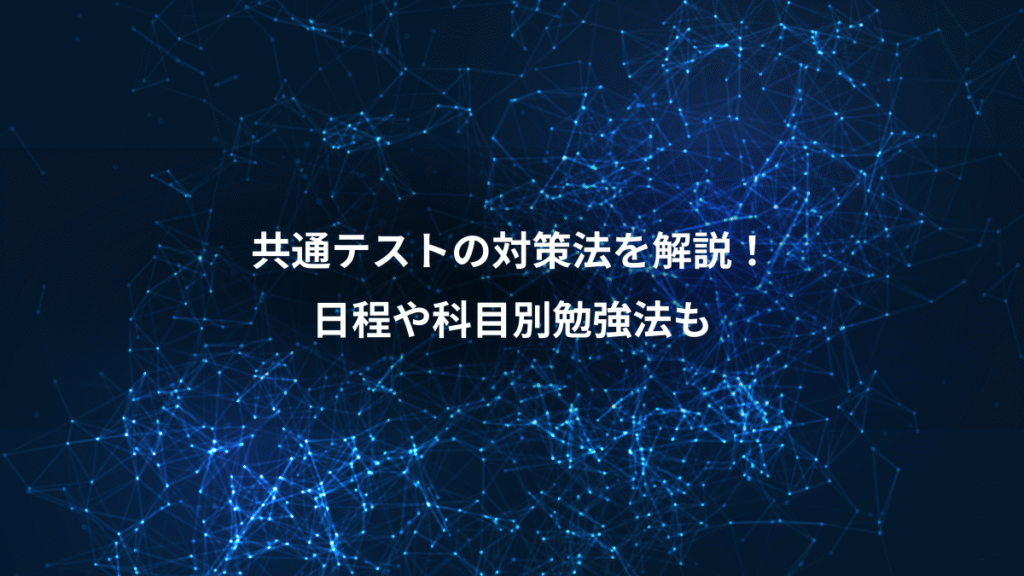大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は、多くの大学受験生にとって最初の大きな関門です。国公立大学の一般選抜では原則として受験が必須であり、多くの私立大学でも利用されています。従来のセンター試験とは異なり、単なる知識の暗記だけでは高得点を狙うのが難しく、思考力や判断力、表現力が問われる試験へと変化しました。
この記事では、共通テストの概要から、2025年度の最新情報、具体的な対策法、科目別の勉強法、直前期の過ごし方まで、受験生が知りたい情報を網羅的に解説します。共通テストを制するためには、その特性を正しく理解し、計画的に対策を進めることが不可欠です。この記事を参考に、万全の準備で本番に臨みましょう。
目次
大学入学共通テストとは

大学入学共通テストは、独立行政法人大学入試センターが実施する、大学への入学を志願する者の高等学校段階における基礎的な学習の達成度を判定することを目的とした試験です。2021年度から、それまでの大学入試センター試験(以下、センター試験)に代わって導入されました。国公立大学の一般選抜では、原則として受験生に共通テストの受験を課しており、第一次選抜(足切り)や最終的な合否判定にその成績が利用されます。また、多くの私立大学でも共通テストの成績を利用する入試方式(共通テスト利用入試)が採用されており、大学受験において極めて重要な位置を占めています。
この試験の最大の特徴は、知識の有無だけでなく、その知識をいかに活用できるかを問う点にあります。思考力、判断力、表現力を重視した問題設計がなされており、受験生にはこれまで以上に深い学びが求められます。
センター試験との違い
共通テストとセンター試験は、どちらも大学入試の基盤となるマークシート方式の全国一斉試験という点では共通していますが、その内容は大きく異なります。最も大きな違いは、試験で評価しようとする能力にあります。
センター試験は、主に「知識・技能」の習熟度を測ることに重きが置かれていました。つまり、教科書に書かれている内容をどれだけ正確に記憶し、基本的な問題を解けるかが評価の中心でした。
一方、共通テストでは、これからの社会で求められる資質・能力を育成するという新しい学習指導要領の趣旨を踏まえ、「知識・技能」に加えて「思考力・判断力・表現力」を多層的に評価することを目指しています。この方針転換により、問題の形式や内容が大きく変化しました。
| 項目 | 大学入試センター試験 | 大学入学共通テスト |
|---|---|---|
| 評価の主眼 | 知識・技能の習熟度 | 知識・技能の活用力(思考力・判断力・表現力) |
| 問題形式 | 知識を直接問う問題が中心 | 日常生活や社会の事象と関連付けた問題、複数の資料(文章、図、グラフ、表など)を読み解き、情報を統合・考察させる問題が多数出題 |
| 解答形式 | 正解が一つに定まる問題がほとんど | 複数の正解があり得る問題や、解答の根拠となる思考プロセスを問う問題も含まれる |
| 英語の配点 | 筆記200点、リスニング50点(計250点)を各大学が圧縮して利用 | リーディング100点、リスニング100点(計200点)。センター試験よりもリスニングの比重が大幅に増加 |
| 数学・国語 | 典型的な問題形式が中心 | 会話形式で問題解決のプロセスを追う問題や、実用的な文章(契約書、説明書など)を題材にした問題など、より実践的な思考力を問う出題が増加 |
このように、共通テストは単なる暗記では太刀打ちできない試験です。なぜそうなるのかという原理原則の理解に基づき、初見の資料や複雑な設定の中から必要な情報を抽出し、論理的に考察する能力が不可欠となります。これが、センター試験との本質的な違いと言えるでしょう。
共通テストで問われる能力
共通テストが受験生に求めている能力は、大きく分けて3つあります。これらは相互に関連し合っており、日々の学習から意識することが重要です。
- 知識・技能の深い理解と応用力
共通テストも、基礎となる知識や技能がなければ解けません。しかし、求められるのは表面的な暗記ではなく、各教科の概念や原理原則を本質的に理解していることです。例えば、歴史の年号や出来事をただ覚えるだけでなく、「なぜその出来事が起きたのか」「その出来事が社会にどのような影響を与えたのか」といった因果関係や背景まで含めて理解している必要があります。数学の公式も、ただ暗記するのではなく、その公式が導き出される過程や、どのような場面で使えるのかを理解していることが問われます。このように深く理解した知識・技能を、未知の問題設定や複雑な状況に応用する力が求められるのです。 - 情報処理能力と論理的思考力
共通テストの多くの科目で、複数の文章、図、グラフ、表、会話文といった多様な資料が提示されます。受験生は、これらの膨大な情報の中から、問題解決に必要な情報を迅速かつ正確に見つけ出し、整理・分析する能力が求められます。
例えば、国語では異なる立場の二つの文章を比較・検討させたり、理科や地理では実験データや統計資料から法則性や傾向を読み取らせたりする問題が出題されます。そこでは、単に情報を抜き出すだけでなく、「このデータは何を意味するのか」「Aという情報とBという情報を組み合わせると何が言えるのか」といった論理的な思考力が不可欠です。与えられた情報を鵜呑みにせず、批判的な視点(クリティカル・シンキング)で吟味し、自分なりに解釈・再構成する力が試されます。 - 問題発見・解決能力
共通テストの問題には、日常生活や社会的な文脈、あるいは探究学習の場面を想定したものが多く含まれます。これは、学習した知識を現実世界の問題と結びつけ、解決策を考える力を評価するためです。
例えば、数学では「最適なプランを選択する」「提示されたモデルの妥当性を検討する」といった問題が出題されます。これらは、単一の正解を求めるのではなく、問題の本質を見抜き、解決までの道筋を自分で構想し、実行する能力を測るものです。解答のプロセス自体が重視されることもあり、なぜその解答に至ったのかという思考の過程を理解していることが重要になります。
これらの能力は、一朝一夕で身につくものではありません。普段の授業から「なぜ?」「どうして?」と問いを持つこと、教科書の内容を鵜呑みにせず、他の資料と関連付けて考える習慣を持つことが、共通テスト対策の第一歩となります。
各大学での利用状況
共通テストの成績は、全国の大学で非常に幅広く利用されています。その利用方法は大学や学部、入試方式によって様々ですが、大きく分けると以下の3つのパターンがあります。
- 国公立大学:原則として必須
ほぼすべての国公立大学の一般選抜では、共通テストの受験が必須です。共通テストの成績は、主に2つの目的で利用されます。- 第一次選抜(いわゆる「足切り」):志願者数が募集人員に対して大幅に多い場合、大学が独自に設定した共通テストの得点(または得点率)の基準に満たない受験生を、二次試験(個別学力検査)に進めなくする制度です。
- 最終的な合否判定:共通テストの成績と、大学が独自に実施する二次試験の成績を合計して、総合点で最終的な合否を決定します。共通テストと二次試験の配点比率は大学・学部によって大きく異なり、共通テスト重視の大学もあれば、二次試験重視の大学もあります。自分の志望校の配点比率を事前に確認し、対策のウェイトを考えることが重要です。
- 私立大学:共通テスト利用入試
多くの私立大学では、「共通テスト利用入試」という方式を導入しています。これは、大学独自の試験を課さず、共通テストの成績のみで合否を判定する入試方式です。受験生にとっては、共通テストを受けるだけで複数の大学・学部に出願できるため、移動や受験の負担を軽減できるメリットがあります。また、一般選抜の前に合否が判明することも多く、早い段階で合格を確保できる可能性があります。ただし、募集人数が少なく、合格に必要な得点率(ボーダーライン)が高めに設定される傾向があるため、注意が必要です。 - 私立大学:一般選抜との併用方式
共通テストの成績と、大学独自の個別試験の成績を組み合わせて合否を判定する方式です。例えば、「共通テストの特定科目の成績」と「大学独自の英語の試験」の合計点で判定する、といった形です。この方式は、受験生の多角的な能力を評価することを目的としており、特定の科目が得意な受験生にとって有利に働く場合があります。
このように、共通テストは大学受験戦略を立てる上で中心的な役割を果たします。自分の志望校が共通テストをどのように利用しているのかを大学の募集要項などで正確に把握し、自分に合った受験計画を立てることが合格への鍵となります。
平均点の推移
共通テストの平均点は、試験の難易度を示す重要な指標の一つです。年度によって変動があり、特に難易度が大きく上下した年は「難化」「易化」などと表現されます。ここでは、主要科目の過去の平均点の推移を見てみましょう。(100点満点換算)
| 科目 | 2024年度 (R6) | 2023年度 (R5) | 2022年度 (R4) | 2021年度 (R3) |
|---|---|---|---|---|
| 英語(リーディング) | 51.58 | 53.81 | 61.80 | 60.35 |
| 英語(リスニング) | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 |
| 数学I・A | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 |
| 数学II・B | 57.24 | 61.48 | 43.06 | 59.93 |
| 国語 | 61.45 (122.90/200) | 57.97 (115.93/200) | 55.48 (110.96/200) | 60.18 (120.35/200) |
| 物理 | 62.97 | 63.39 | 48.46 | 62.25 |
| 化学 | 54.77 | 54.00 | 47.65 | 57.51 |
| 生物 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 |
| 日本史B | 56.92 | 59.75 | 52.81 | 64.25 |
| 世界史B | 60.84 | 58.41 | 65.39 | 63.66 |
| 地理B | 65.18 | 60.58 | 61.76 | 65.77 |
参照:独立行政法人大学入試センター 令和3~6年度大学入学共通テスト実施結果の概要
この表からいくつかの傾向が読み取れます。
特に注目すべきは、2022年度(令和4年度)の数学の大幅な難化です。数学I・Aの平均点は37.96点と、過去に例を見ない低さとなり、多くの受験生を苦しめました。これは、共通テストが単なる計算力だけでなく、問題文の読解力や思考力を高いレベルで要求する試験であることを象徴する出来事でした。
一方で、英語のリスニングは年々平均点が上昇傾向にあり、対策を積んだ受験生が着実に得点できるようになっていることがうかがえます。
このように、共通テストの難易度は年度によって大きく変動する可能性があることを念頭に置く必要があります。特定の年度の過去問だけを基準にするのではなく、複数の年度の問題を解き、どのような難易度にも対応できる実力を養うことが重要です。また、平均点が低い年は、必ずしも自分の実力不足だけが原因ではないと理解し、冷静に自己分析を行うことも大切です。
【2025年度】大学入学共通テストの基本情報
2025年度(令和7年1月実施)の共通テストは、新学習指導要領に対応した初めての試験となり、多くの変更点があります。受験生はこれらの変更点を正確に把握し、早めに準備を進めることが重要です。ここでは、大学入試センターが公表している情報に基づき、2025年度共通テストの基本情報をまとめます。
試験日程・スケジュール
まずは、試験本番までの大まかなスケジュールを把握しましょう。重要な日程は手帳やカレンダーに書き込み、見逃さないように注意が必要です。
| イベント | 日程 |
|---|---|
| 試験日(本試験) | 令和7年(2025年)1月18日(土)、19日(日) |
| 追・再試験日 | 令和7年(2025年)1月25日(土)、26日(日) |
| 得点調整の実施有無の発表 | 令和7年(2025年)1月24日(金)(予定) |
| 段階表示(情報Ⅰ)の換算得点の発表 | 令和7年(2025年)1月24日(金)(予定) |
| 平均点等の中間発表 | 令和7年(2025年)1月22日(水)(予定) |
| 平均点等の最終発表 | 令和7年(2025年)2月7日(金)(予定) |
参照:独立行政法人大学入試センター 令和7年度大学入学共通テスト実施要項
本試験は1月の第3土曜日・日曜日に実施されます。病気や事故など、やむを得ない事情で本試験を受験できなかった受験生のために、翌週に追・再試験が設けられています。自分が追試験の対象になるかどうかは、大学入試センターの規定をよく確認する必要があります。
出願期間
共通テストを受験するためには、期間内に必ず出願手続きを完了させる必要があります。出願期間は比較的短いため、絶対に忘れないようにしましょう。
- 出願期間:令和6年(2024年)9月25日(水)~ 10月8日(火)
現役生は、原則として在学している高等学校を経由して出願します。学校の先生の指示に従い、書類の準備や提出を行いましょう。既卒生(浪人生)や高等学校卒業程度認定試験合格者などは、個人で直接出願します。出願書類に不備があると受理されない場合があるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
受験案内配布の時期
出願に必要な書類一式が含まれた「受験案内」は、出願期間よりも早く配布が開始されます。
- 受験案内配布開始:令和6年(2024年)9月2日(月)から
現役生は学校で配布されるのが一般的です。既卒生などは、共通テストを利用する大学の入試窓口で受け取るか、大学入試センターに郵送を請求して取り寄せます。受験案内の内容は毎年変更される可能性があるため、必ず令和7年度用のものを入手し、熟読してください。
出題科目・配点
2025年度の共通テストでは、新学習指導要領に対応して出題教科・科目が再編されます。特に「地理歴史・公民」と、新たに加わる「情報」が大きな変更点です。
| 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|
| 国語 | 『国語』 | 200点 |
| 地理歴史・公民 | ①『地理総合,地理探究』②『歴史総合,日本史探究』③『歴史総合,世界史探究』④『地理総合,歴史総合,公共』⑤『公共,倫理』⑥『公共,政治・経済』から最大2科目選択 | 各100点 |
| 数学 | ①『数学Ⅰ,数学A』②『数学Ⅱ,数学B,数学C』から最大2科目選択 | 各100点 |
| 理科 | ①『物理基礎,化学基礎,生物基礎,地学基礎』から2科目選択、または②『物理』『化学』『生物』『地学』から最大2科目選択 | ①各50点(計100点)、②各100点 |
| 外国語 | 『英語(リーディング/リスニング)』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』から1科目選択 | 英語:200点(リーディング100点、リスニング100点)、その他:200点 |
| 情報 | 『情報Ⅰ』 | 100点 |
参照:独立行政法人大学入試センター 令和7年度大学入学共通テスト実施要項
地理歴史・公民の科目選択は非常に複雑になっています。多くの大学では、旧課程の「地理歴史から1科目、公民から1科目」のような指定ではなく、新しい6つの科目群から2科目を選択する方式に変わります。ただし、同じ名称を含む科目(例:②と③)の組み合わせは選択できないなどのルールがあります。必ず志望大学の募集要項で、どの科目の組み合わせが必要かを確認してください。
試験時間割
2025年度は、国語と数学②の試験時間が延長されるなど、時間割にも変更があります。
【1日目】 令和7年1月18日(土)
| 教科 | 科目 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 地理歴史・公民 | 1科目選択者 | 9:30 ~ 10:30 (60分) |
| 2科目選択者 | 9:30 ~ 11:40 (130分、解答時間120分) | |
| 国語 | 『国語』 | 13:00 ~ 14:30 (90分) |
| 外国語 | 『英語(リーディング)』など | 15:10 ~ 16:30 (80分) |
| 『英語(リスニング)』 | 17:10 ~ 18:10 (60分、解答時間30分) |
【2日目】 令和7年1月19日(日)
| 教科 | 科目 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 理科① | 『物理基礎』『化学基礎』など | 9:30 ~ 10:40 (70分、解答時間60分) |
| 数学① | 『数学Ⅰ,数学A』 | 11:20 ~ 12:30 (70分) |
| 数学② | 『数学Ⅱ,数学B,数学C』 | 13:50 ~ 15:00 (70分) |
| 理科② | 1科目選択者 | 15:40 ~ 16:40 (60分) |
| 2科目選択者 | 15:40 ~ 17:50 (130分、解答時間120分) | |
| 情報 | 『情報Ⅰ』 | 15:40 ~ 16:40 (60分) |
参照:独立行政法人大学入試センター 令和7年度大学入学共通テスト実施要項
※理科②と情報は同じ時間帯に実施されるため、同時に選択することはできません。
2025年度からの変更点(新課程への対応)
2025年度共通テストの最大のトピックは、新学習指導要領への全面的な移行です。これにより、いくつかの教科で大きな変更が加えられます。
- 国語:試験時間が80分から90分に延長
これまでの大問構成(現代文2問、古文1問、漢文1問)に加え、近代以降の文章に関する大問が1問追加される可能性があります。大学入試センターが公表した試作問題では、文章の構成や表現の効果について分析・評価させる問題など、より多角的な読解力を問う設問が示唆されています。単に速く読むだけでなく、文章を構造的に捉え、批判的に吟味する力がこれまで以上に求められます。 - 数学:数学②の試験時間が60分から70分に延長、出題範囲の変更
数学②は『数学Ⅱ,数学B,数学C』からの出題となります。旧課程の「数学B」で扱われていた「確率分布と統計的な推測」と「ベクトル」、そして「数学C」で新しく導入される「平面上の曲線と複素数平面」が範囲に含まれます。受験生は、「ベクトル」「確率分布と統計的な推測」「平面上の曲線と複素数平面」の3項目から2項目を選択して解答することになります。試験時間が10分延長されるものの、思考力を要する問題が出題されることを考えると、時間的な余裕は少ないと予想されます。 - 地理歴史・公民:科目再編
前述の通り、科目が「地理総合」「歴史総合」「公共」を軸とした6つの科目に再編されます。「歴史総合」では近現代の日本史と世界史を関連付けて学ぶため、これまでのように日本史だけ、世界史だけを学習するスタイルでは対応が難しくなります。また、「公共」では倫理分野と政治・経済分野の双方の知識を基に、現代社会の課題について考察する力が問われます。暗記学習から、事象の背景や関連性を考える探究的な学習へのシフトが不可欠です。 - 情報:「情報Ⅰ」が新設
国立大学では原則として「情報Ⅰ」の受験が必須となります。出題内容は、プログラミングの基本的な考え方、情報デザイン、データ活用、情報セキュリティなど多岐にわたります。単なる知識問題だけでなく、与えられた課題を解決するためのアルゴリズムを考えたり、擬似言語で書かれたプログラムの動作を理解したりする思考力・実践力が問われます。多くの受験生にとって未経験の科目となるため、早期からの計画的な対策が合否を分ける可能性があります。
これらの変更点を踏まえ、2025年度以降の受験生は、旧課程の過去問を参考にしつつも、大学入試センターが公表する試作問題や、新課程に対応した問題集に積極的に取り組む必要があります。
共通テスト対策はいつから始めるべき?学年別の進め方
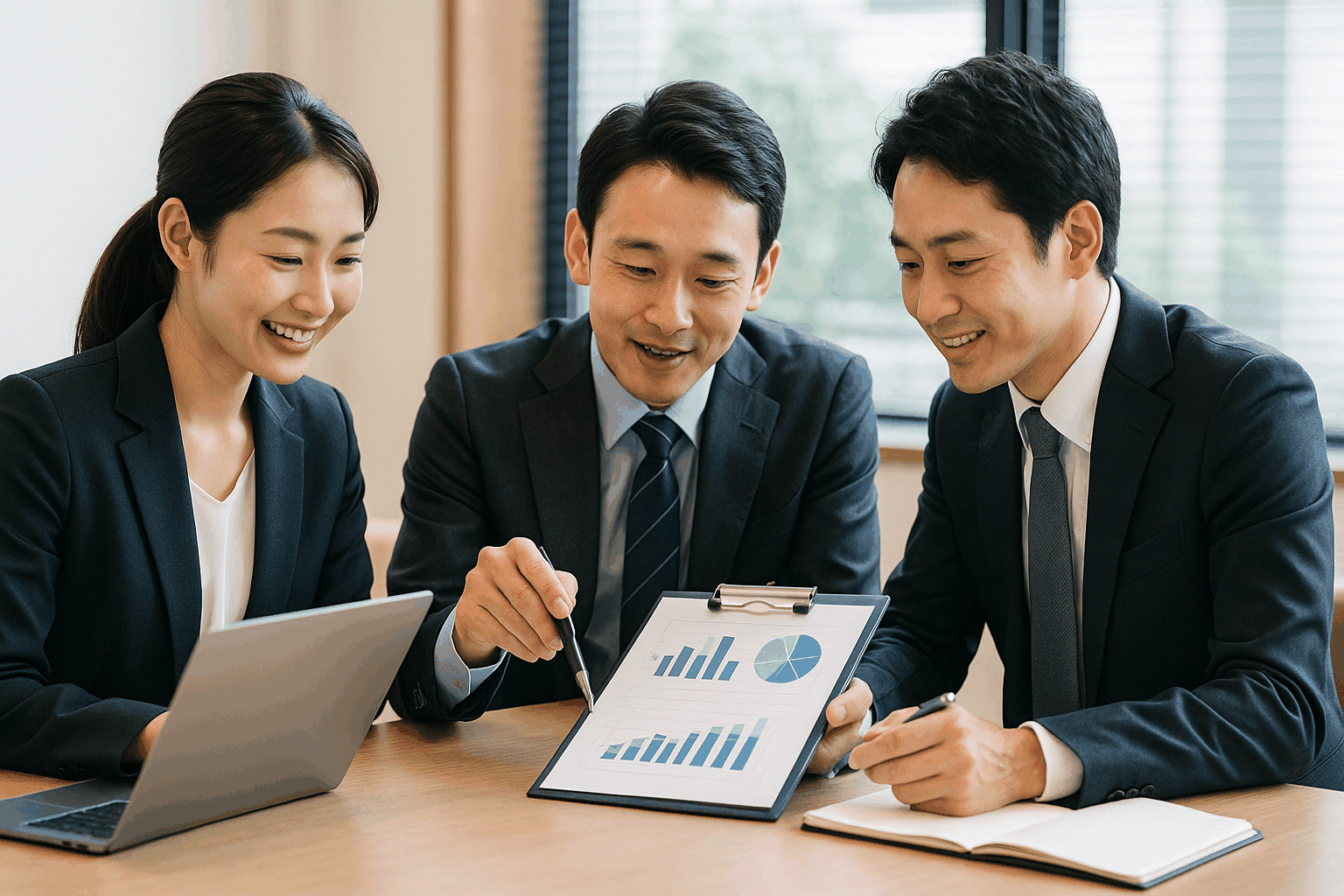
共通テストで高得点を狙うためには、早期からの計画的な学習が欠かせません。「いつから始めれば良いのか」という疑問は多くの受験生が抱くものですが、その答えは学年や現在の学力によって異なります。ここでは、学年別の理想的な対策の進め方を紹介します。
【高校1・2年生】まずは教科書レベルの基礎固めから
高校1・2年生の段階で「共通テスト対策」と意気込む必要は必ずしもありません。この時期に最も重要なのは、日々の授業内容を確実に理解し、教科書レベルの知識を徹底的に固めることです。実は、これが最も効果的な共通テストの準備になります。
- 定期テストを最大限に活用する
高校1・2年生にとって、最も身近な目標は定期テストです。定期テストの範囲は、共通テストで問われる膨大な知識のパーツに他なりません。定期テストで毎回高得点を目指す学習習慣こそが、受験期の大きなアドバンテージとなります。テスト前に一夜漬けで暗記するのではなく、普段から予習・復習を習慣づけ、授業内容をその日のうちに理解することを心がけましょう。特に英語の単語・文法や、数学の公式・定理など、積み重ねが重要な科目は、毎日少しずつでも触れることが大切です。 - 「なぜ?」を大切にする学習
共通テストは思考力を問う試験です。公式や年号をただ丸暗記するだけでは、応用問題に対応できません。高校1・2年生のうちから、「なぜこの公式が成り立つのか?」「なぜこの歴史的事件が起こったのか?」と、常に物事の背景や原理原則に疑問を持ち、自分で調べたり先生に質問したりする癖をつけましょう。この探究的な学習姿勢が、共通テストで求められる思考力の土台を築きます。 - 苦手科目を放置しない
受験学年になってから苦手科目を克服するのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。高校1・2年生の段階であれば、比較的時間をかけてじっくりと苦手分野に取り組むことが可能です。「数学のこの単元が分からない」「古文の助動詞が覚えられない」といった弱点があれば、長期休暇などを利用して、中学校の範囲に遡ってでも復習し、徹底的に潰しておきましょう。早期に苦手意識をなくすことが、受験全体の成功に繋がります。 - 英語と数学を優先的に
全科目まんべんなく学習するのが理想ですが、特に英語と数学は習得に時間がかかる科目です。この2教科は、多くの大学で配点が高く設定されており、一度つまずくと取り返すのが困難です。高校1・2年生のうちは、この2教科に重点的に時間を割き、安定した学力の基盤を築くことをおすすめします。英単語の暗記、英文の多読、数学の網羅系参考書を使った基礎問題の反復練習などを、毎日の学習ルーティンに取り入れましょう。
この時期は、焦って応用問題に手を出す必要はありません。学校の授業と教科書を完璧にすること。これが、高校1・2年生にとって最高の共通テスト対策です。
【高校3年生】夏休み明けには本格的な演習へ
高校3年生になると、いよいよ受験は本格化します。年間を通した学習計画を立て、戦略的に対策を進めていく必要があります。
- 春~夏休み前(4月~7月):基礎の総復習と完成
この時期の目標は、夏休みが終わるまでに、全教科の教科書レベルの知識を一通りインプットし終えることです。高校1・2年生で固めた基礎を、受験という視点でもう一度総復習します。特に、まだ手つかずの範囲や苦手分野が残っている場合は、この時期に必ず完成させましょう。
具体的には、網羅系の参考書(教科書内容を体系的にまとめたもの)を1冊決め、それを繰り返し読み込み、例題をすべて自力で解けるようにします。この段階で、共通テスト形式の問題に少しずつ触れ始めるのも良いでしょう。ただし、目的は点数を取ることではなく、「共通テストではどのような形で知識が問われるのか」を知ることにあります。 - 夏休み(8月):苦手分野の克服と演習への橋渡し
夏休みは、まとまった勉強時間を確保できる貴重な期間です。この期間をどう過ごすかで、秋以降の伸びが大きく変わります。
前半は、春までの学習で明らかになった苦手分野の克服に集中します。特定の単元を徹底的に復習したり、基礎的な問題集を解き直したりして、知識の穴を完全に埋めましょう。
後半からは、いよいよ共通テストの過去問や、共通テスト形式の問題集を使った演習に少しずつ移行していきます。最初は時間を気にせず、じっくりと問題文を読み、なぜその答えになるのかを解説を読み込みながら深く理解することに重点を置きます。 - 秋~冬(9月~12月):本格的な演習と時間配分の習得
夏休み明けからは、共通テスト対策が学習の中心になります。この時期のテーマは「実践力の養成」です。
共通テストの過去問や、質の高い予想問題集を使い、本番と同じ時間設定で解く練習を繰り返します。ここで重要なのは、ただ解いて丸付けをするだけでなく、徹底的な復習を行うことです。- なぜ間違えたのか?(知識不足、読解ミス、計算ミスなど)
- 時間が足りなかったのはどの部分か?
- 次に同じ問題を解くなら、どういう手順で、どのくらいの時間で解くか?
これを科目ごとに分析し、自分の弱点を客観的に把握して、次の演習に活かしていくのです。このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことで、得点力は飛躍的に向上します。また、定期的に実施される模試は、本番のシミュレーションと自分の立ち位置を確認する絶好の機会です。結果に一喜一憂せず、弱点分析の材料として最大限に活用しましょう。
- 直前期(1月):最終調整と体調管理
試験直前期は、新しいことに手を出すのではなく、これまで使ってきた参考書や問題集、ノートを見直し、知識の最終確認を行うことに徹します。特に、何度も間違えた問題や、不安な公式・単語などを集めた自分だけの「まとめノート」は、最強の武器になります。
生活リズムを本番の試験時間に合わせて整え、体調管理に万全を期すことも非常に重要です。自信を持って本番に臨めるよう、心身ともに最高のコンディションを整えましょう。
共通テスト対策でやるべき3つのこと
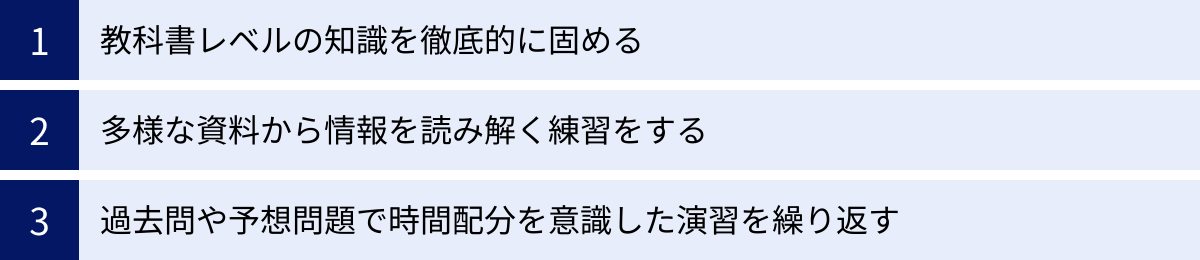
共通テストで目標点を達成するためには、やみくもに勉強するのではなく、その特性に合わせた効果的な対策が必要です。ここでは、すべての受験生に共通して重要となる3つの柱を紹介します。
教科書レベルの知識を徹底的に固める
共通テストが「思考力・判断力」を重視する試験であると聞くと、難しい応用問題集ばかりに手を出すべきだと考えがちですが、それは大きな誤解です。共通テストで出題される問題の根幹にあるのは、すべて教科書に記載されている基本的な知識や概念です。応用力や思考力は、盤石な基礎知識という土台があって初めて発揮されます。
では、なぜ教科書がそれほど重要なのでしょうか。
第一に、共通テストの作問は、高等学校学習指導要領と、それに基づいた教科書の内容を逸脱しないという大原則があるからです。つまり、教科書に書かれていないような、いわゆる「奇問・難問」は出題されません。問題の題材が日常生活や社会の事象であっても、それを解くために必要な知識のピースは、必ず教科書の中にあります。
第二に、教科書は単なる知識の羅列ではなく、物事の背景や因果関係、概念の変遷などが体系的に、かつ論理的に記述されています。例えば、歴史の教科書は単なる年表ではなく、それぞれの出来事がどのような流れの中で発生し、次にどう繋がっていったのかという「物語」として構成されています。この「流れ」や「繋がり」を理解することが、共通テストで問われる思考力の源泉となります。数学や理科の公式も、その導出過程や証明が丁寧に解説されており、これを理解することで、公式を丸暗記するよりもはるかに深く、応用が利く知識として定着します。
したがって、共通テスト対策の第一歩は、「教科書を完璧にする」ことです。具体的には、以下のレベルを目指しましょう。
- 教科書の太字の用語を、自分の言葉で説明できる。
- 章末問題や例題を、何も見ずに自力で解ける。
- 図やグラフ、写真が何を意味しているのかを説明できる。
- 単元間の繋がりや、歴史的な流れを意識して全体像を語れる。
一度読んだだけでは不十分です。何度も繰り返し読み込み、隅々まで理解を深めることが、一見遠回りのようで、実は高得点への最短ルートなのです。
多様な資料から情報を読み解く練習をする
共通テストの最大の特徴は、文章だけでなく、図表、グラフ、写真、イラスト、会話文、4コマ漫画など、極めて多様な資料が問題文に含まれることです。そして、これらの複数の資料から必要な情報を抽出し、整理・比較・統合して解答を導き出す能力が求められます。
この能力は、単に知識を暗記しているだけでは身につきません。意図的なトレーニングが必要です。
- 資料読解に特化した問題集に取り組む
市販されている共通テスト対策の問題集には、こうした資料読解問題が豊富に収録されています。最初は時間がかかっても構わないので、「このグラフは何を表しているのか」「この会話文の登場人物の主張の対立点はどこか」「この図と本文の記述をどう結びつければ良いのか」といったことを、一つひとつ丁寧に考えながら解く練習をしましょう。解説を熟読し、自分がどこで情報を読み間違えたのか、どう考えれば正解にたどり着けたのかを分析することが重要です。 - 科目横断的な視点を持つ
共通テストでは、一見すると無関係に見える複数の科目の知識が融合したような問題が出題されることがあります。例えば、地理の問題で歴史的な背景知識が問われたり、理科の問題で国語的な読解力が求められたりします。日頃から、「この社会問題は、政治・経済の視点だけでなく、倫理的な観点からも考えられるな」「この科学技術の話題は、情報Ⅰで学んだことと関連しているな」というように、物事を多角的に捉える習慣をつけることが有効です。 - 日常の情報にアンテナを張る
新聞やニュース、信頼できるウェブサイトなどで報じられる社会の出来事や科学の話題に触れることも、良いトレーニングになります。そこには、共通テストで題材にされやすいグラフや統計データが豊富に含まれています。「このグラフの縦軸と横軸は何だろう?」「この統計からどんな傾向が読み取れるだろう?」と、普段から意識的に情報を分析する癖をつけることで、初見の資料に対する抵抗感がなくなり、迅速に要点を掴む力が養われます。
資料を「見る」のではなく「読む」意識を持つこと。これが、共通テストの資料読解問題を攻略する鍵です。
過去問や予想問題で時間配分を意識した演習を繰り返す
共通テストは、思考力を要する問題が多い一方で、試験時間は非常にタイトです。十分な知識と読解力があっても、時間内にすべての問題を解ききれなければ高得点は望めません。そこで不可欠となるのが、時間配分を意識した実践的な演習です。
- 過去問演習の重要性
共通テストの過去問は、最高の教材です。出題の意図、問題の形式、難易度、時間設定など、本番の試験を最も忠実に再現しています。最低でも過去3~5年分、できればセンター試験の思考力系の問題も含めて、繰り返し解くことをおすすめします。
演習を行う際は、必ず本番と同じ時間(例:数学Ⅰ・Aなら70分)を計り、途中で中断せずに最後まで解き切ります。 - 「時間戦略」を確立する
演習を通して、自分なりの「時間戦略」を確立していくことが目標です。- 大問ごとの目標時間を設定する:各大問に何分かけるかを事前に決めておき、それを意識しながら解き進めます。
- 解く順番を工夫する:得意な大問や、知識問題中心で時間を短縮できる大問から手をつけるなど、自分にとって最も効率の良い順番を見つけます。
- 「捨てる勇気」を持つ:一定時間考えても解法が思い浮かばない問題は、一旦飛ばして次の問題に進む勇気も必要です。難しい1問に時間をかけるより、解けるはずの他の問題を確実に得点する方が、合計点は高くなります。
- 見直しの時間を確保する:試験時間の最後の5~10分は、マークミスがないか、計算ミスがないかを見直す時間に充てるのが理想です。
- 質の高い予想問題集の活用
過去問の数が限られているため、特に新課程に対応する2025年度入試では、市販の予想問題集や、予備校が作成する模試問題の活用が重要になります。これらは、最新の出題傾向を分析して作られており、本番さながらの演習を積むことができます。
演習後は、点数に一喜一憂するのではなく、「なぜ時間が足りなかったのか」「どの部分で時間を使いすぎたのか」を徹底的に分析します。そして、「次は大問1を5分短縮しよう」「選択肢を吟味する時間をもう少し取ろう」といった具体的な改善策を立て、次の演習で実践します。
この地道な繰り返しこそが、本番で焦らず、持てる力を最大限に発揮するための確実な道筋です。
【科目別】共通テストの出題傾向と対策・勉強法
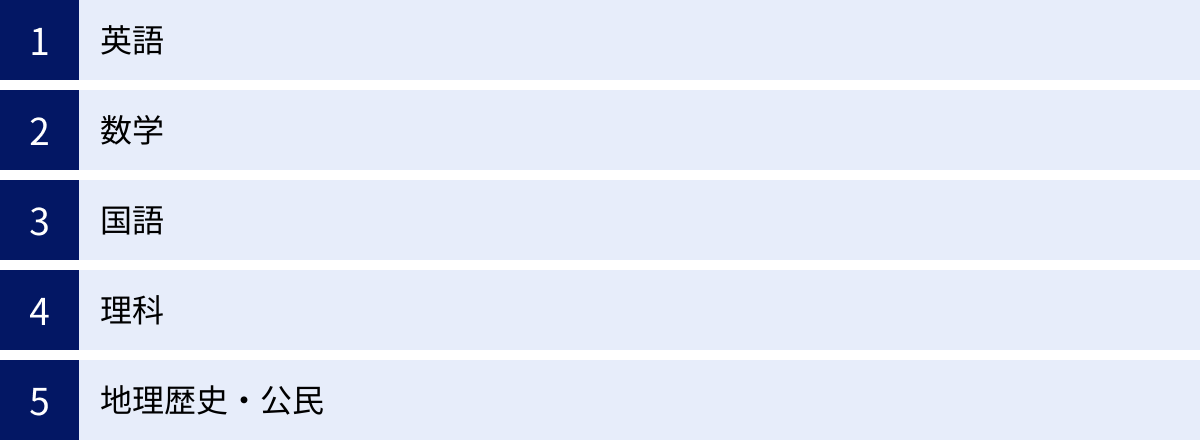
共通テストは科目ごとに特徴があり、それぞれに合わせた対策が求められます。ここでは、主要な教科・科目について、最新の出題傾向と効果的な勉強法を解説します。
英語
共通テストの英語は「リーディング」と「リスニング」の2技能が、それぞれ100点満点で評価されます。センター試験時代に比べてリスニングの比重が大幅に高まり、両技能をバランス良く伸ばすことが不可欠です。
リーディングの傾向と対策
【傾向】
共通テストのリーディングは、情報処理能力を問う試験と言えます。発音・アクセントや文法・語法の独立した問題はなくなり、すべてが長文読解形式で出題されます。題材は、ウェブサイトの記事、広告、メールのやり取り、レビュー、説明書、グラフを含む報告書など、非常に多様です。センター試験よりも総語数が大幅に増加しており、限られた時間内に膨大な量の英文を読み、必要な情報を正確に探し出す「スキャニング能力」と、文章全体の趣旨を把握する「スキミング能力」が求められます。また、複数の情報源から得た情報を比較・検討し、事実(Fact)と意見(Opinion)を区別するような、より高度な思考力を要する問題も特徴です。
【対策・勉強法】
- 語彙力と文法力の徹底強化: 速読の土台は、単語を見て瞬時に意味がわかる語彙力と、文の構造を正確に把握できる文法力です。単語帳は1冊を完璧に仕上げ、文法書も繰り返し復習して、知識を盤石にしましょう。
- 多読・速読トレーニング: 日頃から様々なジャンルの英文に数多く触れることが重要です。時間を計りながら長文を読み、1分あたりに何語読めるか(WPM: Words Per Minute)を意識すると、速読力が向上します。最初は内容が完全に理解できなくても、大意を掴む練習を繰り返しましょう。
- 問題形式に慣れる: 共通テストの過去問や予想問題集を解き、「どのような情報が問われやすいか」を意識しながら演習します。設問を先に読んで、何を探すべきかを頭に入れてから本文を読む「設問先読み」も有効なテクニックです。
- 情報検索の練習: ウェブサイトの記事や図表を含む問題では、全ての文章を精読する必要はありません。問われている情報をピンポイントで見つけ出す練習を積むことが、時間短縮の鍵となります。
リスニングの傾向と対策
【傾向】
リスニングは、センター試験に比べて難易度が上がり、より実践的な聞き取り能力が求められます。特徴的なのは、読み上げ回数が1回の問題が多く含まれることです。これにより、一度で正確に聞き取る集中力と記憶力が不可欠となります。また、話者の国籍も多様で、アメリカ英語だけでなく、イギリス英語や非ネイティブの話す英語も含まれるため、様々なアクセントに慣れておく必要があります。内容は、日常的な会話から講義、ニュースまで幅広く、図表やグラフを見ながら聞き取り、情報を整理する問題も出題されます。
【対策・勉強法】
- 毎日英語の音声に触れる: リスニング力は一朝一夕には伸びません。毎日15分でも良いので、英語の音声を聞く習慣をつけましょう。共通テスト対策用の教材だけでなく、海外のニュースやポッドキャスト、映画などを活用するのも効果的です。
- ディクテーションとシャドーイング: 聞き取った英語を書き取る「ディクテーション」は、自分が聞き取れていない音を特定するのに役立ちます。また、音声に少し遅れて影(シャドー)のようについていく「シャドーイング」は、英語のリズムやイントネーションを身体で覚えるのに最適で、聞き取り能力を飛躍的に向上させます。
- 1回読み問題への対策: 過去問や予想問題集の1回読みの問題を使い、メモを取りながら聞く練習をしましょう。キーワードや数字、登場人物の関係性などを素早く書き留めることで、記憶を補助できます。
- 先読みの徹底: リーディング同様、設問や選択肢を事前に読んでおくことが極めて重要です。何に注意して聞くべきかを把握しておくだけで、聞き取りの精度が格段に上がります。
数学
共通テストの数学は、単なる計算力ではなく、数学的な思考プロセスそのものを問う点が大きな特徴です。日常生活や社会の事象を題材にした長い問題文を読み解き、会話形式で示されるヒントを基に考察を進める問題が多く出題されます。
数学I・Aの傾向と対策
【傾向】
2025年度から試験時間が70分に延長されます。出題範囲は「数と式」「図形と計量」「二次関数」「データの分析」に加え、選択問題として「場合の数と確率」「図形の性質」「整数の性質」が基本となります。特に「データの分析」は、資料の読み取りが中心となり、共通テストの思想を象徴する分野です。問題全体として、公式を当てはめるだけの問題は少なく、問題設定を正しく理解し、どの知識を使えば解決できるかを自分で考える力が求められます。誘導が丁寧な反面、文章量が多く、一つひとつの設問の意味を正確に捉える読解力が必要です。
【対策・勉強法】
- 教科書の徹底理解: 公式や定理は丸暗記せず、なぜその公式が成り立つのかという証明や導出過程まで含めて理解しましょう。この深い理解が、初見の問題に応用を利かせる土台となります。
- 思考プロセスを言語化する: 問題を解く際に、「まず問題の条件を整理し、次にこの定理が使えそうだから試してみる」といったように、自分の考えを言葉にする癖をつけましょう。共通テストの会話形式の問題は、まさにこの思考プロセスを追体験させるものです。
- 「データの分析」を重点的に: この分野は対策が手薄になりがちですが、共通テストでは頻出です。用語の定義(平均値、中央値、分散、相関係数など)を正確に覚え、ヒストグラムや箱ひげ図、散布図から何が読み取れるかを説明できるように練習しましょう。
- 時間配分を意識した演習: 70分という時間をどう使うか、戦略を立てることが重要です。解ける問題から確実に手をつける、難しい問題は後回しにするなど、過去問演習を通して自分なりのペースを確立しましょう。
数学II・Bの傾向と対策
【傾向】
2025年度からは『数学Ⅱ,数学B,数学C』となり、試験時間も70分に延長されます。内容は「様々な式」「図形と方程式」「三角関数」「指数関数・対数関数」「微分法・積分法」に加え、選択問題として「ベクトル」「確率分布と統計的な推測」「平面上の曲線と複素数平面」から2項目を選択する形式になります。数学I・A以上に、複数の分野の知識を融合させた問題や、長い誘導に乗って複雑な計算を正確に実行する力が求められます。特に微分・積分は、面積計算などで計算量が多くなりがちです。
【対策・勉強法】
- 計算力の強化: 思考力はもちろん重要ですが、それを支えるのは迅速かつ正確な計算力です。計算が煩雑な問題も多いため、日頃から計算練習を怠らず、スピードと正確性を高めておきましょう。
- 解法のパターンをストックする: 網羅系の参考書を使い、典型的な問題の解法パターンを頭に入れましょう。共通テストの問題は設定がユニークでも、分解すると基本的な解法の組み合わせであることが多いです。
- 選択問題の早期決定と対策: 新課程の選択問題3つの中から、自分が受験する2項目を早めに決め、集中的に対策する必要があります。学校の進度や自分の得意・不得意を考慮し、夏休み前には決定するのが理想です。
- 図やグラフを自分で描く: 図形と方程式や三角関数、微分・積分などの分野では、問題の状況を正確に図示する能力が不可欠です。フリーハンドで素早く、かつ正確にグラフや図を描く練習を普段から行いましょう。
国語
国語は2025年度から試験時間が90分に延長され、より多角的で深い読解力が問われます。現代文・古文・漢文のいずれも、本文の内容を正確に捉えるだけでなく、表現の意図や文章の構造まで踏み込んだ理解が求められます。
現代文の傾向と対策
【傾向】
従来の評論・小説に加え、詩やエッセイ、実用的な文章(法律の条文、契約書、報告書など)といった多様なジャンルの文章が出題されます。また、一つのテーマについて書かれた異なる文章や、文章と図表・グラフなどを組み合わせて読ませ、それらを比較・検討・統合して考察させる問題が特徴的です。傍線部の意味を問うだけでなく、文章全体の構成や論理展開、表現の効果について説明させるなど、よりメタ的な視点からの読解力が求められます。
【対策・勉強法】
- 論理的な読解力の養成: 評論では、筆者の主張(結論)と、それを支える理由・具体例の関係(論理構造)を把握することが最も重要です。段落ごとの要点をメモしながら、「しかし」などの接続詞に注意して文章の展開を追いましょう。
- 客観的な根拠を探す: 選択肢を選ぶ際は、自分の主観や感覚で判断するのではなく、必ず本文中に書かれている記述を根拠とします。「本文のこの部分にこう書いてあるから、この選択肢が正しい(誤っている)」と、明確に説明できるまで吟味する癖をつけましょう。
- 多様な文章に触れる: 過去問だけでなく、新聞の社説やコラム、新書などを読んで、様々な文体に慣れておくと良いでしょう。実用文対策としては、身の回りにある説明書や規約などを意識して読んでみるのも有効です。
- 語彙力・漢字の強化: 評論で使われるキーワード(概念、アイデンティティなど)の意味を正確に理解しておくことは、読解の助けになります。漢字の書き取り・読みも、得点源として確実におさえましょう。
古文の傾向と対策
【傾向】
基本的な文法知識や単語力が土台となる点は変わりませんが、共通テストではそれらを活用して、本文の内容や登場人物の心情、関係性を正確に読み解くことが重視されます。和歌の解釈や、本文の内容に加えて提示された別の資料(解説文など)を踏まえて考察させる問題も特徴です。単に現代語訳ができるだけでなく、当時の文化や常識を理解しているかが問われます。
【対策・勉強法】
- 古文単語と古典文法のマスター: 単語と文法(特に助動詞の活用と意味、敬語)は古文読解の生命線です。これらが曖昧なままでは、正確な読解は不可能です。単語帳と文法書をそれぞれ1冊決め、夏休み前までには完璧にしましょう。
- 主語を補いながら読む: 古文は主語が省略されることが多いため、誰がその動作をしているのかを常に意識し、補いながら読む練習が不可欠です。登場人物に丸をつけるなど、工夫しながら読み進めましょう。
- 音読: 古文を音読することで、文章のリズム感が身につき、読解スピードの向上に繋がります。意味を考えながら繰り返し音読しましょう。
- 文学史と常識の習得: 作品のジャンル(物語、説話など)や作者、時代背景といった文学史の知識、そして当時の貴族社会の常識(恋愛観、出世など)を知っていると、ストーリーの理解が格段に深まります。
漢文の傾向と対策
【傾向】
古文と同様に、基本的な句形(句法)や重要漢字の知識を前提として、文章の主題や筆者の主張を読み解く力が問われます。対比構造や比喩表現に着目させる問題が多く、簡潔な文章の中から筆者のメッセージを正確に捉える必要があります。漢詩が出題されることもあります。古文・漢文は対策すれば安定して高得点を狙える分野であり、重要な得点源です。
【対策・勉強法】
- 句形と重要漢字の暗記: 漢文は覚えるべき句形の数が限られています。「返り点」のルールに従って書き下し文を作れるようにした上で、主要な句形(使役、受身、否定、疑問・反語など)を瞬時に判断できるよう、繰り返し練習します。
- 返り点の練習: 白文(返り点のない漢文)に自分で返り点を打つ練習をすると、構造理解が深まります。
- 素早い音読(素読): 返り点に従って、書き下し文にせず漢文のまま読んでいく練習をすると、読解スピードが上がります。
- 文脈判断: 漢字の意味は文脈によって変わることがあります。一つの意味に固執せず、前後の文脈から最も自然な意味を推測する柔軟な思考が大切です。
理科
理科は、基礎科目(物理基礎、化学基礎など)と専門科目(物理、化学など)に分かれます。いずれも知識の暗記だけでなく、実験結果の考察やデータ分析、日常生活との関連性を問う問題が多く、科学的な思考力が試されます。
物理の傾向と対策
【傾向】
公式を暗記して数値を代入するだけの問題は少なく、物理現象の根本的な理解を問う問題が中心です。複数の法則が絡み合う複雑な設定や、実験データから法則性を見出す考察問題、現象を説明する文章の正誤を判断する問題などが出題されます。思考力を要する問題が多い反面、複雑な計算は比較的少ない傾向にあります。
【対策・勉強法】
- 原理原則の理解: 公式を導出過程から理解し、「なぜこの現象が起こるのか」を自分の言葉で説明できるようにしましょう。教科書を精読し、現象のイメージを掴むことが重要です。
- 作図の習慣化: 力学では力の矢印、電磁気では電場や磁場など、目に見えないものを図に描いて可視化する習慣が不可欠です。正確な作図が、立式のミスを防ぎます。
- 定性的な理解を深める: 「速さが2倍になると、運動エネルギーは何倍になるか」といった、具体的な数値計算を伴わない定性的な問いに対応できるよう、文字式で物理量を扱う練習を積みましょう。
化学の傾向と対策
【傾向】
知識問題、計算問題、思考力問題がバランス良く出題されます。特に、実験操作やその結果に関する考察問題、グラフや表を含むデータの読み取り問題が頻出です。単なる暗記では対応できない、初見の物質や反応に関する問題も出題され、化学の基本原理に基づいて推論する力が求められます。計算問題も煩雑なものが多く、時間内に正確に処理する能力が必要です。
【対策・勉強法】
- 理論化学の徹底: すべての分野(無機、有機)の土台となる理論化学(物質量、化学反応式、酸・塩基、酸化還元など)の理解を最優先しましょう。ここが曖昧だと、全分野で失点に繋がります。
- 知識の整理: 無機化学は物質の性質や製法、有機化学は官能基の性質や反応系統図など、覚えるべき知識が膨大です。自分でノートにまとめたり、図表を活用したりして、知識を体系的に整理しましょう。
- 実験問題への対策: 教科書に載っている実験の写真や図をよく見て、器具の名称や使い方、操作の意味(例:なぜ冷却するのか)を理解しておきましょう。
生物の傾向と対策
【傾向】
暗記すべき用語が多いのは事実ですが、それ以上に実験考察問題の比重が高いのが特徴です。長いリード文と複雑な実験設定を読み解き、データ(グラフ・表)を分析して仮説を検証する力が求められます。知識を応用して、未知の生命現象について推論させる問題も多く、論理的思考力が試されます。
【対策・勉強法】
- 知識の正確なインプット: まずは教科書レベルの用語や現象を正確に覚えることが大前提です。図や写真と関連付けて、視覚的に記憶しましょう。
- 実験考察問題の演習: 「対照実験」「仮説」「結論」といった、科学的な探究のプロセスを意識しながら問題演習を積みます。なぜその実験が必要だったのか、結果から何が言えるのかを自分の頭で考える練習が不可欠です。
- グラフ作成の練習: データが与えられた際に、自分で簡単なグラフを描いてみる練習は、データの傾向を視覚的に掴む能力を養うのに有効です。
地学の傾向と対策
【傾向】
出題範囲が広く、地質、地球物理、大気、海洋、宇宙と多岐にわたります。図やグラフ、地形図などの資料を読み解く問題が多く、空間的なイメージング能力やデータ分析能力が重要です。物理や化学の知識が必要となる分野もあり、総合的な理科の力が問われます。
【対策・勉強法】
- 図や写真との関連付け: 教科書や資料集の図(地質図、天気図など)や写真を活用し、用語とビジュアルをセットで覚えることが効果的です。
- スケール感の意識: 地学で扱う対象は、ミクロな鉱物からマクロな銀河まで様々です。時間的・空間的なスケール感を常に意識することで、現象の理解が深まります。
- 計算問題の対策: 地震の計算や天体の計算など、典型的な計算問題は確実に解けるように、繰り返し練習しておきましょう。
地理歴史・公民
2025年度から科目が再編され、複数の科目にまたがる知識や、現代社会の課題と歴史を結びつけて考察するような、より総合的な力が求められます。
日本史の傾向と対策
【傾向】
単なる一問一答式の知識問題は減少し、史料(古文書、絵図、写真など)や図表、グラフを読み解き、歴史的な事象を多角的に考察させる問題が増加しています。特定の時代だけでなく、複数の時代をまたぐテーマ史(例:女性の地位の変遷)や、世界史との関連を問う問題も出題されます。出来事の因果関係や背景を深く理解しているかが問われます。
【対策・勉強法】
- 「流れ」の理解: 教科書を通読し、通史(古代から現代まで)の大きな流れを掴むことを最優先します。タテ(時代)とヨコ(政治、経済、文化などの分野)の繋がりを意識しましょう。
- 史料問題への対策: 教科書や資料集に掲載されている史料に普段から目を通し、頻出の史料やキーワードに慣れておきましょう。史料から何が読み取れるかを考える練習が重要です。
- 地図と年表の活用: 出来事がどこで起こったのか(地図)、いつ起こったのか(年表)を常に確認する癖をつけ、知識を立体的に整理しましょう。
世界史の傾向と対策
【傾向】
日本史同様、史料や地図、図表の読解が重視されます。特定の地域だけでなく、ヨーロッパ史とアジア史の交流など、地域間の関連性を問う問題が頻出です。また、現代の世界が抱える問題の歴史的背景を問うなど、近現代史の比重が高いのも特徴です。タテ(時代)とヨコ(地域)の繋がりを総合的に理解する力が求められます。
【対策・勉強法】
- タテとヨコの学習: まずは地域ごとに時代を追う「タテの学習」で流れを掴み、次に同時代の異なる地域で何が起こっていたかを見る「ヨコの学習」で、知識を繋ぎ合わせます。自作の年表などが有効です。
- 地図の活用: 世界史の出来事は必ず地図上で位置を確認しましょう。国の興亡や領土の変遷を地図で追うことで、記憶が定着しやすくなります。
- テーマ史の学習: 「宗教」「民族移動」「貿易」など、特定のテーマに沿って時代や地域を横断して学習すると、知識が有機的に結びつき、理解が深まります。
地理の傾向と対策
【傾向】
統計データ(表、グラフ)や地形図、写真、図など、非常に多くの資料を読み解き、地理的な事象の背景にある原理・原則を考察する問題が中心です。暗記だけでは対応できず、なぜその地域でその産業が発達するのか、なぜその気候になるのかといった「なぜ」を考える力が試されます。系統地理(自然環境、産業など)と地誌(各地域の特色)の両方から出題されます。
【対策・勉強法】
- 地理的思考力の養成: 「なぜ?」を常に考える癖をつけましょう。例えば、雨温図を見たら「なぜこの時期に雨が多いのか?」、人口ピラミッドを見たら「なぜこの形をしているのか?」と、背景にある要因を推論する練習をします。
- 統計データの読解練習: 様々な統計データに触れ、国や地域ごとの特徴を掴みましょう。主要な農産物や鉱産資源の生産国ランキングなどは、大まかに覚えておくと推論の助けになります。
- 地図帳の徹底活用: 地図帳は最高の参考書です。地名や地形だけでなく、気候区分や土地利用、資源分布など、様々な情報が詰まっています。何かを調べるたびに地図帳を開く習慣をつけましょう。
現代社会・倫理・政治・経済の傾向と対策
【傾向】
2025年度からは「公共」をベースとした科目に再編されます。現代社会が抱える具体的な課題(環境問題、格差、情報社会など)を題材に、倫理、政治、経済の多角的な視点から考察させる問題が中心になると予想されます。思想家の考え方をただ暗記するのではなく、その思想を現代の課題にどう応用できるかを問われたり、複雑な制度(選挙制度、社会保障制度など)の仕組みを正確に理解しているかが試されたりします。
【対策・勉強法】
- 基本用語の正確な理解: まずは教科書に出てくる基本用語(思想家名、制度名、経済用語など)の意味を正確に覚えることがスタート地点です。
- 思想・制度の背景理解: なぜその思想が生まれたのか、なぜその制度が必要とされたのか、という背景や目的をセットで理解しましょう。
- 時事問題への関心: 新聞やニュースに日常的に触れ、現代社会の動きに関心を持つことが重要です。学習した知識が、現実の社会でどのように機能しているのかを意識することで、理解が深まります。
- 対比・整理: 似て非なる思想家や制度は、共通点と相違点を表にまとめるなどして、頭の中を整理しましょう。
共通テスト対策におすすめの参考書・問題集
共通テスト対策を効果的に進めるためには、自分のレベルや目的に合った参考書・問題集を選ぶことが非常に重要です。ここでは、どのような種類の教材があり、それぞれをどう使い分ければ良いのか、選び方のポイントを解説します。
英語のおすすめ参考書・問題集
英語の対策では、「単語」「文法」「長文読解」「リスニング」の4つの技能をバランス良く伸ばすための教材選びが鍵となります。
- 単語帳: 共通テストレベルの単語を網羅したものを1冊選び、それを完璧に仕上げることを目指しましょう。音声ダウンロード機能がついているものを選ぶと、発音を確認しながら覚えられるため、リスニング対策にも繋がります。例文の中で覚えるタイプの単語帳は、実際の使われ方がわかりおすすめです。
- 文法書・問題集: 網羅系の参考書(いわゆる「総合英語」と呼ばれるもの)を1冊手元に置き、辞書のように使いながら知識を固めます。並行して、基礎的なレベルから標準レベルまでの4択形式などの文法問題集を繰り返し解き、文法ルールの定着を図りましょう。
- 長文読解問題集: 共通テストのリーディングは情報処理能力が問われるため、様々なテーマや形式の長文を収録した問題集が有効です。最初は、文の構造解説(SVOCなど)が詳しいものから始め、徐々に速読を意識した演習量をこなせる問題集に移行していくと良いでしょう。
- リスニング問題集: スクリプト(放送文)と詳しい解説が付いているものを選びましょう。ただ聞き流すだけでなく、聞き取れなかった部分をスクリプトで確認し、その原因(単語を知らない、音声変化についていけないなど)を分析することが重要です。共通テストの形式に特化した問題集で、1回読みの問題に慣れておくことも必須です。
- 共通テスト対策総合問題集・予想問題集: 秋以降は、本番の形式に沿った総合問題集や、各予備校などが出版する予想問題集が中心となります。時間を計って解き、詳細な解説を読んで復習するサイクルを繰り返すことで、実践力を高めます。
数学のおすすめ参考書・問題集
数学は、基礎の理解から応用力の養成まで、段階に応じた教材選びが求められます。
- 網羅系参考書: 教科書レベルの解説と例題が体系的にまとめられた参考書(「チャート式」や「Focus Gold」などが有名)は、全受験生の必携アイテムです。まずは例題を何も見ずに解けるようになるまで繰り返し、基礎を盤石にしましょう。解説を読んでも理解できない部分は、教科書に戻ったり先生に質問したりして、決して放置しないことが大切です。
- 基礎レベルの問題集: 網羅系参考書が難しいと感じる場合や、特定分野を重点的に固めたい場合は、より解説が丁寧で問題数が絞られた基礎的な問題集から始めると良いでしょう。計算力を鍛えるためのドリルなども有効です。
- 共通テスト対策に特化した問題集: 共通テスト特有の、長い問題文や会話形式の問題に慣れるための問題集です。思考力を問う問題や、データの分析、新課程の選択問題などを集中的に扱っているものを選び、夏休み明け頃から取り組むのがおすすめです。解答に至るまでの「考え方」や「着眼点」が詳しく解説されているものが良書と言えます。
- 過去問・予想問題集: 最終段階では、時間を計って本番同様の演習を積むことが不可欠です。大学入試センターの過去問に加え、質の高い予想問題パックなどを活用し、時間配分の戦略を練りましょう。復習の際は、なぜその解法を思いつかなかったのか、思考のプロセスを振り返ることが重要です。
国語のおすすめ参考書・問題集
国語は、現代文、古文、漢文それぞれの特性に合わせた教材が必要です。
- 現代文の参考書: 「読み方」を解説する参考書と、「解き方」を解説する参考書があります。まずは、評論や小説の論理的な読み方を解説した参考書で、文章構造の把握の仕方や筆者の主張の掴み方を学びましょう。その上で、選択肢の吟味の仕方など、具体的な解法テクニックを解説した問題集に進むのが効率的です。漢字や語彙に関する参考書も1冊用意し、隙間時間に進めましょう。
- 古文単語帳・古典文法書: 古文の基礎となる単語と文法は、それぞれ専用の参考書で徹底的に固めます。古文単語は語源やイラストと関連付けて覚えられるもの、古典文法は助動詞の接続や活用、意味が分かりやすくまとめられたドリル形式のものが取り組みやすいでしょう。
- 古文・漢文の読解問題集: 基礎知識をインプットしたら、易しいレベルの読解問題集から始めます。品詞分解や現代語訳、解説が非常に丁寧なものを選び、自力で訳す練習と解説の照らし合わせを繰り返しましょう。徐々にレベルを上げ、共通テスト形式の問題に移行します。
- 共通テスト対策総合問題集・過去問: 秋以降は、90分という新しい試験時間に対応した演習が必須です。時間を計って解き、現代文・古文・漢文の時間配分を自分なりに確立していくことが目標です。
理科のおすすめ参考書・問題集
理科は、現象の理解を助ける参考書と、演習量を確保する問題集の組み合わせが効果的です。
- 講義形式の参考書: 教科書だけでは理解しにくい概念や現象を、図やイラストを多用して分かりやすく解説してくれる講義形式の参考書は、初学や苦手分野の克服に最適です。なぜそうなるのか、という原理原則の理解に役立ちます。
- 網羅系問題集: 各分野の典型的な問題を一通り網羅した問題集を1冊やり込むことで、知識の定着と解法の習得が図れます。解説が詳しいものを選び、間違えた問題には印をつけて、何度も解き直しましょう。
- 実験・考察問題に特化した問題集: 共通テストで頻出の実験考察問題を集中的に扱った問題集は、思考力を鍛える上で非常に有効です。仮説の設定、対照実験、データ分析といった科学的探究のプロセスを意識しながら取り組むと良いでしょう。
- 共通テスト対策問題集・過去問: 共通テスト特有の、資料の読み取りや正誤選択問題に慣れるために必須です。特に、複数の選択肢の中から正しいものをすべて選ぶ形式など、独特の設問形式への対応力を養います。
地理歴史・公民のおすすめ参考書・問題集
暗記だけでなく、流れの理解や資料読解が重要な地歴公民では、インプットとアウトプットのバランスが大切です。
- 講義形式の参考書・教科書: まずは歴史の大きな流れ(通史)や、各分野の全体像を掴むために、教科書や講義形式の参考書を繰り返し読み込みます。教科書と併用できる、図や写真が豊富な資料集も非常に役立ちます。
- 一問一答形式の問題集: 基本的な用語や人名、年号などを確実に覚えるためのインプットツールとして有効です。ただし、これだけで終わらせず、必ず通史の流れの中でその用語がどういう意味を持つのかを意識しましょう。
- 史料・資料読解問題集: 共通テストで重視される史料や統計データの読解スキルを養成するための問題集です。どのような点に着目すれば良いのか、資料から何を読み取るべきなのか、という着眼点を学びます。
- 共通テスト対策問題集・過去問: 共通テスト形式の問題演習を通して、知識のアウトプット練習と時間配分の習得を目指します。特に地歴公民は時間との勝負になることが多いため、スピーディーに問題を処理する訓練が不可欠です。新課程に対応した予想問題集も積極的に活用しましょう。
直前期(秋〜冬)の共通テスト対策と過ごし方

受験勉強の最終盤である秋から冬にかけての直前期は、これまでの努力を結実させるための非常に重要な時期です。精神的にも肉体的にも負担が大きくなるこの時期をどう過ごすかが、本番のパフォーマンスを大きく左右します。
秋(9月〜11月)の過ごし方
夏までの基礎固めを終え、いよいよ実践力を本格的に高めていくのが秋の時期です。この時期のテーマは「共通テストへの完全シフト」と「弱点の徹底克服」です。
- 共通テスト形式の演習をルーティン化する
この時期からは、学習の中心を共通テストの過去問や予想問題集を用いた演習に置きます。週に1~2回は、本番と同じ時間割で複数科目を連続して解く「共通テスト模試DAY」を自分で設定するのも良いでしょう。これにより、長時間の集中力を維持する訓練や、教科間の頭の切り替えの練習になります。
演習で重要なのは、解きっぱなしにしないこと。「なぜ間違えたのか」「どこで時間をロスしたのか」「次はどうすれば改善できるか」を科目ごとに詳細に分析し、ノートにまとめて可視化しましょう。この「分析ノート」が、自分だけの最強の戦略集になります。 - 模試の積極的な活用と復習
秋には、各予備校が実施する共通テスト模試が数多くあります。これらの模試は、本番に近い雰囲気で自分の実力を試せる絶好の機会です。結果の判定(A判定、B判定など)に一喜一憂するのではなく、模試を「自分の弱点を発見するための診断ツール」と捉えましょう。
模試返却後は、自己採点では気づけなかった間違いや、理解が曖昧だった部分を徹底的に復習します。特に、正答率が高いにもかかわらず自分が間違えてしまった問題は、基礎知識の抜けである可能性が高いです。優先的に潰していきましょう。 - 二次試験・私大対策とのバランス
国公立大学志望者は二次試験の対策、私立大学志望者は個別試験の対策も並行して進める必要があります。共通テスト対策と個別試験対策の時間の比率は、志望校の配点比率を参考に決定しましょう。例えば、平日は個別試験の記述対策、週末は共通テストのマーク対策といったように、曜日や時間帯で区切るのがおすすめです。共通テストでしか使わない科目がある場合は、その学習時間がゼロにならないように計画を立てることが重要です。 - 基礎知識のメンテナンス
演習中心の学習になると、基本的な知識の確認が疎かになりがちです。移動時間や寝る前の短い時間を使って、これまで使ってきた単語帳や一問一答集、公式集などに目を通し、知識のメンテナンスを怠らないようにしましょう。盤石な基礎知識があるからこそ、演習の効果が最大化されます。
冬(12月〜1月)の過ごし方
いよいよ本番まで残り1~2ヶ月となる冬の時期は、最終調整とコンディション維持が最優先事項です。焦りや不安が大きくなる時期ですが、これまでやってきたことを信じ、冷静に取り組むことが大切です。
- 新しい問題集には手を出さない
この時期に新しい参考書や問題集に手を出すのは避けましょう。中途半端に終わり、かえって不安を増大させる原因になります。これまで使ってきた参考書、問題集、模試の解き直し、そして自分で作成した「分析ノート」や「まとめノート」の復習に徹するのが最も効果的です。何度も間違えた問題を完璧に解けるようにすることで、自信にも繋がります。 - 本番を想定したシミュレーション
過去問や最後の予想問題パックを使い、本番と全く同じ時間割で行動するシミュレーションを行いましょう。起床時間から試験開始時間、休憩時間の過ごし方、昼食の内容まで、できるだけ本番に近づけます。これにより、当日の流れが身体に染み付き、余計な緊張を防ぐことができます。特に、リスニングはイヤホンではなくスピーカーで聞くなど、本番の環境を想定した練習も有効です。 - 時間配分の最終確認
これまでの演習で確立してきた、各大問にかける時間配分戦略を再確認し、体に叩き込みます。「この大問は15分、少し難しいから最大20分まで」といった最終的なタイムマネジメントを確定させましょう。また、「もしパニックになったら深呼吸する」「難しい問題は潔く飛ばす」といった、トラブルシューティングのプランをあらかじめ決めておくと、本番で冷静さを保ちやすくなります。 - 体調管理とメンタルケア
直前期において、勉強と同じくらい重要なのが体調管理です。睡眠時間を削っての徹夜は、記憶の定着を妨げ、体調を崩すリスクを高めるだけです。夜はしっかり睡眠をとり、日中の学習効率を上げましょう。生活リズムを朝型に整え、バランスの取れた食事を心がけ、適度な休息や息抜きも大切です。
不安な気持ちになるのは当然のことです。そんな時は、家族や友人、先生に話を聞いてもらったり、少し散歩して気分転換したりするのも良いでしょう。「ここまで頑張ってきたんだ」という自分自身の努力を認め、自信を持って本番に臨むことが、最高のパフォーマンスを引き出します。
共通テスト対策でよくある質問

共通テスト対策を進める中で、多くの受験生が抱くであろう疑問について、Q&A形式で解説します。
共通テストと二次試験(個別試験)の対策はどちらを優先すべき?
これは多くの国公立大学志望者が悩む問題ですが、一概にどちらかを優先すべきとは言えず、志望校の配点比率によって判断するのが正解です。
まず、第一志望校の募集要項を確認し、「共通テストの配点」と「二次試験の配点」の比率を調べましょう。
- 共通テストの配点比率が高い大学・学部の場合(例:共通テスト:二次試験=7:3など)
この場合は、共通テストで高得点を取ることが合格に直結します。秋以降は共通テスト対策にかなりのウェイトを置き、目標点を確実にクリアするための戦略を立てるべきです。ただし、二次試験の対策を全くしないのは危険なので、最低限の記述力の維持は必要です。 - 二次試験の配点比率が高い大学・学部の場合(例:共通テスト:二次試験=3:7など)
難関大学に多いパターンです。この場合は、共通テストは「足切りを突破するための関門」と位置づけ、目標点をクリアできれば良しとして、早期から二次試験の難易度の高い記述問題や論述問題に時間を割く戦略が有効です。ただし、共通テストで大きく失敗すると二次試験での逆転が非常に困難になるため、油断は禁物です。 - 配点比率が半々程度の大学・学部の場合
最もバランスが難しいパターンです。秋までは両方を並行して進め、11月頃からは共通テスト対策の比重を徐々に高め、共通テスト終了後、一気に二次試験対策に切り替えるという進め方が一般的です。
いずれにせよ、共通テスト対策で培った基礎力や読解力は、二次試験でも必ず役立ちます。両者は全く別物ではなく、繋がっていると考えることが重要です。
過去問はいつから、何年分解くのが効果的?
過去問演習は共通テスト対策の核となりますが、始める時期と取り組む量には注意が必要です。
- いつから始めるか: 本格的に時間を計って解き始めるのは、高校3年生の夏休み明け(9月頃)からが一般的です。それ以前の段階では、まだ全範囲の学習が終わっていなかったり、基礎が固まっていなかったりするため、点数が出ずに自信をなくしてしまう可能性があります。ただし、夏休み中に「どのような問題が出るのか」を知る目的で、1~2年分だけ解いてみるのは良いでしょう。
- 何年分解くか: 共通テストは2021年度から始まったため、過去問のストックはまだ多くありません。実施された全ての年度(2021~2024年度)の本試験・追試験は必ず解きましょう。
さらに演習量を積みたい場合は、思考力や資料読解を重視していた近年のセンター試験の過去問(2018~2020年度あたり)も非常に有効です。問題形式は異なりますが、問われている能力には共通点が多くあります。
重要なのは量よりも質です。解いた過去問は、100点が取れるようになるまで何度も復習することが、新しい問題を1回解くよりもはるかに効果的です。
時間配分がうまくなるコツは?
時間配分は、知識と同じくらい重要なスキルです。以下のコツを意識して、演習を繰り返しましょう。
- 大問ごとの目標時間を設定する: 演習を始める前に、「大問1は15分、大問2は20分…」と、各大問にかける目標時間を設定します。そして、解きながら時間を意識する癖をつけます。
- 解く順番を固定化する: 自分の得意・不得意や、問題の性質に合わせて、「自分はこの順番で解くのが最も効率が良い」という流れを確立しましょう。例えば、知識問題が多くて早く解ける大問から手をつける、などです。
- 「捨てる勇気」を持つ: 決められた時間を過ぎても解けない問題は、一旦マークをつけて飛ばし、次の問題に進みましょう。難しい1問に固執して、解けるはずの他の問題を落とすのが最も避けたい事態です。「全問正解」ではなく「合計点で最大点を取る」ことを目指しましょう。
- 見直しの時間をあらかじめ計画に入れておく: 試験時間の最後の5~10分は、見直しのために空けておく計画を立てましょう。この時間があるだけで、焦りが減り、ケアレスミスを発見できます。
共通テスト対策のために塾は必要?
塾や予備校の必要性は、個人の学習スタイルや性格、置かれている環境によって異なります。
- 塾が必要・有効なケース:
- 自己管理が苦手: 学習計画を立てたり、継続したりするのが苦手な人は、塾のカリキュラムやペースメーカーとしての役割が助けになります。
- 質の高い教材や情報が欲しい: 最新の入試情報や、傾向を分析して作られた質の高い教材、模試などを活用したい場合に有効です。
- 競争環境に身を置きたい: 周りに同じ目標を持つ仲間がいることで、モチベーションを維持しやすくなります。
- 質問できる環境が欲しい: 学校の先生以外に、すぐに質問できる専門家がいると安心です。
- 塾が不要・効果が薄いケース:
- 自己管理が得意: 自分で計画を立て、参考書などを使って着実に学習を進められる人は、必ずしも塾は必要ありません。
- 自分のペースで学習したい: 塾の授業ペースが自分に合わない(早すぎる・遅すぎる)と感じる場合、かえって非効率になることがあります。
- 経済的な負担が大きい: 無理をして通塾することが、家庭の負担や精神的なストレスになる場合は、市販の良質な参考書やオンライン教材などを活用する方が良いでしょう。
最終的には、塾に「何を求めるのか」を明確にし、体験授業などに参加して自分に合うかどうかを判断することが大切です。
もし共通テストで失敗してしまったらどうすればいい?
万全の準備をしても、本番で思うような結果が出ないことは誰にでも起こり得ます。大切なのは、その後の行動です。
- すぐに気持ちを切り替える: 試験が終わった直後に自己採点をして、落ち込んでしまう受験生は多いですが、引きずってはいけません。1日だけ思い切り落ち込んだら、翌日からは「次に何をすべきか」に頭を切り替えましょう。
- 正確な自己採点とデータ分析: 気持ちが落ち着いたら、予備校などが発表する解答速報で正確に自己採点をします。その得点をもとに、大手予備校が提供する「共通テストリサーチ」などのサービスを利用し、自分の成績でどの大学・学部が合格圏内にあるのか、客観的なデータを分析します。
- 出願校の見直し: 当初の出願予定校のボーダーラインに届いていない場合は、出願校の変更を検討する必要があります。二次試験での逆転が可能か、それとも共通テストの配点が低い大学や、ランクを下げた大学に出願し直すか、学校の先生や家族と冷静に相談して決めましょう。国公立大学の中期・後期日程や、私立大学の一般入試など、チャンスはまだ残っています。
- 二次試験・個別試験に全力を注ぐ: 出願校を決めたら、過去を振り返らず、目の前の二次試験・個別試験の対策に全力を注ぎましょう。「共通テストのビハインドをここで取り返す」という強い気持ちが、最後の粘りを生みます。
浪人生も共通テストを受ける必要はある?
はい、国公立大学や、私立大学の共通テスト利用入試を考えている浪人生(既卒生)は、現役生と同様に共通テストを受ける必要があります。
浪人生は、現役時に比べて学習に充てられる時間が多いため、より高いレベルの目標設定が可能です。しかし、一方で孤独感やプレッシャーを感じやすい環境でもあります。予備校に通う、学習計画を細かく立てて進捗を可視化するなど、モチベーションを維持する工夫が重要です。
また、2025年度からは新課程入試となるため、現役生との間に情報の差が生まれないよう、変更点を正確に把握し、新課程に対応した対策を行うことが不可欠です。
共通テストのボーダーラインとは?
共通テストにおける「ボーダーライン(ボーダー得点率)」とは、その大学・学部に合格した人と不合格になった人の共通テストの得点が、ちょうど半々くらいになるラインを指します。主に予備校などが、過去の入試結果やその年の共通テストの平均点などから予測して発表します。
- ボーダーラインの活用法:
- 出願校決定の目安: 自分の共通テストの得点が、志望校のボーダーラインを上回っているか下回っているかは、出願を決める際の重要な判断材料になります。
- 二次試験での目標設定: もし自分の得点がボーダーラインより下だった場合、二次試験でどれくらい多く得点すれば逆転合格できるのか、具体的な目標を立てるのに役立ちます。
- 注意点:
- あくまで目安: ボーダーラインは合格を保証するものでも、不合格を確定させるものでもありません。その年の志願者の動向や、二次試験の出来によって、最終的な合否は変わります。
- 二次試験との総合評価: 最終的な合否は、共通テストと二次試験の合計点で決まります。ボーダーラインぴったりでも二次試験で高得点を取れば合格できますし、ボーダーラインを大きく上回っていても二次試験で失敗すれば不合格になることもあります。
ボーダーラインは重要な指標ですが、それに一喜一憂しすぎず、冷静な判断材料の一つとして活用しましょう。
まとめ
大学入学共通テストは、単に知識量を測る試験から、持っている知識を活用して思考し、判断する能力を問う試験へと大きく進化しました。特に2025年度からは新学習指導要領に対応した新課程入試がスタートし、国語や数学の試験時間延長、「情報Ⅰ」の新設など、受験生は大きな変化に対応する必要があります。
この記事で解説してきた通り、共通テスト対策の王道は、一見遠回りに見えても、以下の2つの柱を地道に実践することに尽きます。
- 教科書レベルの知識を、背景や原理原則まで含めて深く、徹底的に理解すること。
- その盤石な基礎知識を土台として、多様な資料を読み解き、時間内に問題を処理する実践的な演習を繰り返すこと。
高校1・2年生は日々の授業と定期テストを大切にし、基礎固めに徹すること。高校3年生は年間計画を立て、夏までに基礎を完成させ、秋以降は本格的な演習で実践力を高めていくことが理想的な流れです。
科目ごとに特性は異なりますが、いずれも表面的な暗記だけでは通用しません。「なぜそうなるのか?」を常に問い続け、知識を有機的に繋げていく学習を心がけましょう。そして、直前期には体調管理とメンタルケアを最優先し、これまで積み重ねてきた努力を信じて本番に臨んでください。
共通テストは大学受験における大きな関門ですが、その対策を通して身につけた思考力や情報処理能力は、大学での学び、さらには社会に出てからも必ず役立つ一生の財産となります。この記事が、皆さんの合格への道のりを照らす一助となれば幸いです。